複数辞典一括検索+![]()
![]()
かっ-ぽじ・る [4] 【掻っ穿じる】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
かっ-ぽじ・る [4] 【掻っ穿じる】 (動ラ五[四])
「ほじる」を強めていう語。「耳の穴を―・ってよく聞けよ」
がっぽり [3] (副)🔗⭐🔉
がっぽり [3] (副)
一時にたくさん入手したり失ったりするさま。「―(と)もうける」「税金に―(と)持って行かれる」
かっぽれ [1]🔗⭐🔉
かっぽれ [1]
(1)〔「カッポレ
 甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕
幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。
(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。
甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕
幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。
(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。

 甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕
幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。
(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。
甘茶でカッポレ」という囃子詞からの名〕
幕末から明治にかけて流行した俗謡と踊り。鳥羽節から願人坊主の住吉踊りに取り入れられて大道芸とされ,豊年斎梅坊主らによって座敷芸となった。
(2){(1)}を取り入れた歌舞伎舞踊の通称。現行のものは河竹黙阿弥作詩による常磐津「初霞空住吉(ハツガスミソラモスミヨシ)」。
がっ-ぽん [0] 【合本】 (名)スル🔗⭐🔉
がっ-ぽん [0] 【合本】 (名)スル
数冊の本を合わせて,一冊の本として製本すること。また,その本。合冊。
かつ-ま 【勝間】🔗⭐🔉
かつ-ま 【勝間】
「堅間(カタマ)」に同じ。「間(マ)なし―の小船を作りて/古事記(上訓)」
かつま [1] 【羯磨】🔗⭐🔉
かつま [1] 【羯磨】
〔梵 karman〕
〔仏〕
〔天台宗・浄土宗など一般には「かつま」と読むが,真言宗・南都諸宗では「こんま」と読む〕
(1)行為。業(ゴウ)。所作。
(2)受戒・懺悔の作法。
(3)「羯磨金剛」の略。
かつま-こんごう ―ガウ [4] 【羯磨金剛】🔗⭐🔉
かつま-こんごう ―ガウ [4] 【羯磨金剛】
三叉(サンサ)の金剛杵(シヨ)を二本,十文字に組み合わせた密教の法具。
羯磨金剛
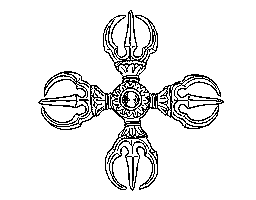 [図]
[図]
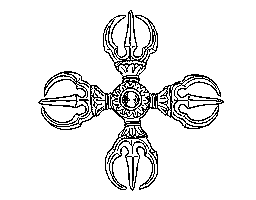 [図]
[図]
かつま-まんだら 【羯磨曼荼羅】🔗⭐🔉
かつま-まんだら 【羯磨曼荼羅】
四種曼荼羅の一。仏のはたらきの姿や菩薩の行為を示したもの。
かつ-また [1] 【且つ又】 (接続)🔗⭐🔉
かつ-また [1] 【且つ又】 (接続)
その上また。「史跡として,―絶景の地として著名である」
かつまた-の-いけ 【勝間田の池】🔗⭐🔉
かつまた-の-いけ 【勝間田の池】
奈良市西の京の唐招提寺と薬師寺付近にあったという池。((歌枕))「―は我知る蓮(ハチス)なし然(シカ)言ふ君がひげなきごとし/万葉 3835」
〔平安時代以降,その所在は不明となり,美作(ミマサカ)・下野(シモツケ)・下総(シモウサ)など,諸説が生まれた〕
大辞林 ページ 141293。