複数辞典一括検索+![]()
![]()
かねしげ-とうよう ―タウヤウ 【金重陶陽】🔗⭐🔉
かねしげ-とうよう ―タウヤウ 【金重陶陽】
(1896-1967) 陶芸家。岡山県生まれ。本名,勇。父に作陶を学び,桃山時代の備前焼の再現に努めた。備前焼中興の祖と称される。
かねしげ 【金重】🔗⭐🔉
かねしげ 【金重】
鎌倉末期・南北朝期の刀工。越前の人で後に美濃に移住,関鍛冶繁栄の基を築いたという。生没年未詳。
かね-じゃく [0] 【曲尺・矩尺】🔗⭐🔉
かね-じゃく [0] 【曲尺・矩尺】
〔金属製であることから〕
(1)大工・建具職人などが用いる直角に曲がった金属製の物差し。表には実寸(表目)の,裏にはその 倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。
(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。
→尺
曲尺(1)
倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。
(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。
→尺
曲尺(1)
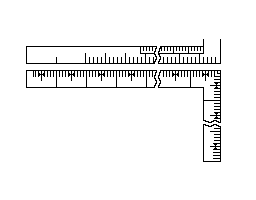 [図]
[図]
 倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。
(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。
→尺
曲尺(1)
倍(裏目),1/π倍(丸目)の目盛りがきざまれている。かね。かねざし。まがりがね。まがりざし。まがりじゃく。さしがね。すみがね。大工金(ダイクガネ)。鉄尺。
(2){(1)}が用いている尺の単位。現在の尺。一尺は30.3センチメートル。鯨尺(クジラジヤク)の八寸にあたる。
→尺
曲尺(1)
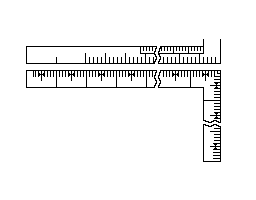 [図]
[図]
かね-ずく ―ヅク [0] 【金尽く】🔗⭐🔉
かね-ずく ―ヅク [0] 【金尽く】
金銭の力だけで物事を解決しようとすること。金銭ずく。かねずくめ。「―で納得させる」
かね-ずくめ ―ヅクメ [3] 【金尽くめ】🔗⭐🔉
かね-ずくめ ―ヅクメ [3] 【金尽くめ】
「金尽(ズ)く」に同じ。
かね-せんじ 【兼ね宣旨】🔗⭐🔉
かね-せんじ 【兼ね宣旨】
⇒けんせんじ(兼宣旨)
かね-そな・える ―ソナヘル [5] 【兼(ね)備える】 (動ア下一)[文]ハ下二 かねそな・ふ🔗⭐🔉
かね-そな・える ―ソナヘル [5] 【兼(ね)備える】 (動ア下一)[文]ハ下二 かねそな・ふ
(両立しがたい二つの要素を)両方とも持ち合わせる。兼備する。「知恵と勇気を―・える」
かね-ぞめ [0] 【鉄漿染(め)】🔗⭐🔉
かね-ぞめ [0] 【鉄漿染(め)】
(1)歯を御歯黒(オハグロ)で黒く染めること。御歯黒染め。
(2)御歯黒で布を紺色に染めること。
かね-だか [2][0] 【金高】🔗⭐🔉
かね-だか [2][0] 【金高】
金銭の額。金額。きんだか。
かね-たたき [3] 【鉦叩】🔗⭐🔉
かね-たたき [3] 【鉦叩】
(1)念仏の際に鉦をたたくこと。また,その人。
(2)鉦をたたく棒。撞木(シユモク)。
(3)鉦をたたきながら経文などを唱え,金品をもらい歩く乞食僧。「彼の京の―/浮世草子・永代蔵 3」
(4)カネタタキ科の昆虫。体長10ミリメートル内外。コオロギに似,体表は灰褐色。雄は前ばねが黒褐色で非常に短く後ろばねを欠き,雌にははねがない。雄は秋にチン,チン,チンと鳴く。関東以南と中国に分布。[季]秋。《暁は宵より淋し―/星野立子》
大辞林 ページ 141364。