複数辞典一括検索+![]()
![]()
かりや-えきさい 【狩谷 斎】🔗⭐🔉
斎】🔗⭐🔉
かりや-えきさい 【狩谷 斎】
(1775-1835) 江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。漢学を修め,特に唐代律令の研究に優れ,また日本の古典・金石文・古辞書・度量衡などの研究にも力を注いだ。著「日本霊異記攷証」「古京遺文」「和名類聚抄箋注」「本朝度量権衡攷」など。
斎】
(1775-1835) 江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。漢学を修め,特に唐代律令の研究に優れ,また日本の古典・金石文・古辞書・度量衡などの研究にも力を注いだ。著「日本霊異記攷証」「古京遺文」「和名類聚抄箋注」「本朝度量権衡攷」など。
 斎】
(1775-1835) 江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。漢学を修め,特に唐代律令の研究に優れ,また日本の古典・金石文・古辞書・度量衡などの研究にも力を注いだ。著「日本霊異記攷証」「古京遺文」「和名類聚抄箋注」「本朝度量権衡攷」など。
斎】
(1775-1835) 江戸後期の考証学者。名は望之。江戸の人。漢学を修め,特に唐代律令の研究に優れ,また日本の古典・金石文・古辞書・度量衡などの研究にも力を注いだ。著「日本霊異記攷証」「古京遺文」「和名類聚抄箋注」「本朝度量権衡攷」など。
かりゃく 【嘉暦】🔗⭐🔉
かりゃく 【嘉暦】
年号(1326.4.26-1329.8.29)。正中の後,元徳の前。後醍醐天皇の代。
かり-やく [0] 【仮役】🔗⭐🔉
かり-やく [0] 【仮役】
(1)臨時の役職。
(2)見習いの役。権官。
かり-やぐら [3] 【仮櫓】🔗⭐🔉
かり-やぐら [3] 【仮櫓】
「控え櫓」に同じ。
かり-やす [0] 【刈安・青茅】🔗⭐🔉
かり-やす [0] 【刈安・青茅】
(1)イネ科の多年草。中部・近畿地方の山地に自生。茎は高さ約1メートル,長線形の葉を根生および茎上につける。夏から秋にかけ,茎頂に数本の花序を直立し,ススキに似た小穂をつける。全草を黄色の染料とする。オウミカリヤス。
(2)伊豆八丈島で,コブナグサをいう。黄八丈の染料に用いる。
(3)「刈安染め」の略。
刈安(1)
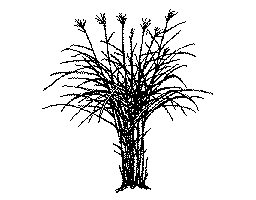 [図]
[図]
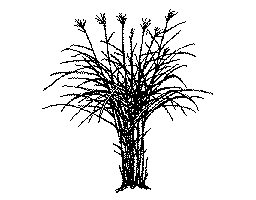 [図]
[図]
かりやす-ぞめ [0] 【刈安染(め)】🔗⭐🔉
かりやす-ぞめ [0] 【刈安染(め)】
カリヤスの茎や葉を煮て染めること。また,染めたもの。かりやす。
かり-やま [0] 【狩(り)山】🔗⭐🔉
かり-やま [0] 【狩(り)山】
(1)「狩り場」に同じ。
(2)山で狩りをすること。
か-りゅう ―リウ [0] 【下流】🔗⭐🔉
か-りゅう ―リウ [0] 【下流】
(1)川の流れの,河口に近い部分。
(2)その地点から見て水の流れて行く方。川下。「ダムの―に村がある」
(3)社会的に低い階層。下層。「近来の小説家の著述にも,―の様を写せしもの頗る多かり/当世書生気質(逍遥)」
か-りゅう ―リウ [0] 【加硫】🔗⭐🔉
か-りゅう ―リウ [0] 【加硫】
(1)生ゴムに硫黄を混ぜて加熱することにより架橋構造をつくり,ゴムの弾性を増加させる操作。和硫。「―ゴム」
(2)有機芳香族化合物に硫黄または硫化ナトリウムを加えて,加熱・融解して硫化染料を作る操作。硫化。和硫。
大辞林 ページ 141587。