複数辞典一括検索+![]()
![]()
がんぎ-ぐるま [4] 【雁木車】🔗⭐🔉
がんぎ-ぐるま [4] 【雁木車】
(1)積み荷の揚げ降ろしにつかう滑車の一。角材の横面をくりぬいて,車をはめこんだもの。せみ。
(2)時計の部品で,アンクルとかみ合いアンクルを介して振り子または天府に力を与える歯の長い歯車。
がんぎ-だな [3] 【雁木棚】🔗⭐🔉
がんぎ-だな [3] 【雁木棚】
床の間の脇などに設ける違い棚の一。三枚の棚板を三段に連なる雁木形に配置したもの。
→床脇棚
がんぎ-だま [0] 【雁木玉】🔗⭐🔉
がんぎ-だま [0] 【雁木玉】
表面に縞模様のあるガラスの丸玉。古墳の副葬品にみられる。
→蜻蛉(トンボ)玉
がんぎ-づくり [4] 【雁木造り】🔗⭐🔉
がんぎ-づくり [4] 【雁木造り】
「雁木{(1)}」に同じ。
がんぎ-ばしご [4] 【雁木梯子】🔗⭐🔉
がんぎ-ばしご [4] 【雁木梯子】
一本の太い木材に踏み段を刻み出すか,太い棒に数本の横木をとりつけた梯子。
雁木梯子
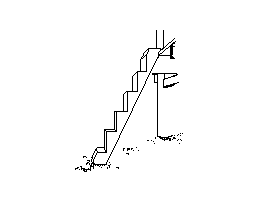 [図]
[図]
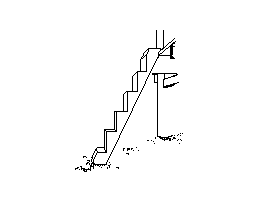 [図]
[図]
がんぎ-やすり [4] 【雁木鑢】🔗⭐🔉
がんぎ-やすり [4] 【雁木鑢】
(1)獣角・金属などを磨く,目の粗いやすり。がんぎ。
(2)がさがさした肌の女をののしっていう語。「―鮫肌/浄瑠璃・日本振袖始」
かんぎ-えん ― ン 【咸宜園】🔗⭐🔉
ン 【咸宜園】🔗⭐🔉
かんぎ-えん ― ン 【咸宜園】
広瀬淡窓(タンソウ)が1817年豊後日田郡堀田村に開いた私塾。広く庶民に開放し,一時は門人三千人にも達した。大村益次郎・高野長英・長三洲らもここに学んだ。1893年(明治26)まで存続。
ン 【咸宜園】
広瀬淡窓(タンソウ)が1817年豊後日田郡堀田村に開いた私塾。広く庶民に開放し,一時は門人三千人にも達した。大村益次郎・高野長英・長三洲らもここに学んだ。1893年(明治26)まで存続。
 ン 【咸宜園】
広瀬淡窓(タンソウ)が1817年豊後日田郡堀田村に開いた私塾。広く庶民に開放し,一時は門人三千人にも達した。大村益次郎・高野長英・長三洲らもここに学んだ。1893年(明治26)まで存続。
ン 【咸宜園】
広瀬淡窓(タンソウ)が1817年豊後日田郡堀田村に開いた私塾。広く庶民に開放し,一時は門人三千人にも達した。大村益次郎・高野長英・長三洲らもここに学んだ。1893年(明治26)まで存続。
かん-ぎく クワン― [1] 【 菊】🔗⭐🔉
菊】🔗⭐🔉
かん-ぎく クワン― [1] 【 菊】
〔「
菊】
〔「 」は「鐶」の当て字〕
家紋の一。菊花を鐶で囲んだもの。
」は「鐶」の当て字〕
家紋の一。菊花を鐶で囲んだもの。
 菊】
〔「
菊】
〔「 」は「鐶」の当て字〕
家紋の一。菊花を鐶で囲んだもの。
」は「鐶」の当て字〕
家紋の一。菊花を鐶で囲んだもの。
かん-ぎく [1][0] 【寒菊】🔗⭐🔉
かん-ぎく [1][0] 【寒菊】
冬に咲く菊の総称。霜に強く,花は小輪で観賞用に栽培される。冬菊。[季]冬。
大辞林 ページ 141707。