複数辞典一括検索+![]()
![]()
かんじょう-どり クワンジヤウ― [5] 【環状土籬】🔗⭐🔉
かんじょう-どり クワンジヤウ― [5] 【環状土籬】
縄文時代後期の北海道に特有の墓地。円形竪穴の周りに堤を設け,多くの墓穴をつくった集団墓。千歳市キウス遺跡が代表例。周堤墓。
かんじょう-はくひ クワンジヤウ― [5] 【環状剥皮】🔗⭐🔉
かんじょう-はくひ クワンジヤウ― [5] 【環状剥皮】
木の幹または太い枝に細く浅い切り込みを入れて樹皮を環状に取り除く方法。剥皮部の上方で不定根が発生しやすくなるため,取り木などの際用いる。環状除皮。
かんじょう-もりど-いこう クワンジヤウ― コウ [8] 【環状盛土遺構】🔗⭐🔉
コウ [8] 【環状盛土遺構】🔗⭐🔉
かんじょう-もりど-いこう クワンジヤウ― コウ [8] 【環状盛土遺構】
盛土をドーナツ状の堤に造った縄文時代の遺構。最初に発見された栃木県小山市寺野東遺跡のものは直径165メートル,高さ5メートル,祭祀儀礼の場と考えられている。
コウ [8] 【環状盛土遺構】
盛土をドーナツ状の堤に造った縄文時代の遺構。最初に発見された栃木県小山市寺野東遺跡のものは直径165メートル,高さ5メートル,祭祀儀礼の場と考えられている。
 コウ [8] 【環状盛土遺構】
盛土をドーナツ状の堤に造った縄文時代の遺構。最初に発見された栃木県小山市寺野東遺跡のものは直径165メートル,高さ5メートル,祭祀儀礼の場と考えられている。
コウ [8] 【環状盛土遺構】
盛土をドーナツ状の堤に造った縄文時代の遺構。最初に発見された栃木県小山市寺野東遺跡のものは直径165メートル,高さ5メートル,祭祀儀礼の場と考えられている。
かんじょう-れっせき クワンジヤウ― [5] 【環状列石】🔗⭐🔉
かんじょう-れっせき クワンジヤウ― [5] 【環状列石】
新石器時代の遺構。立石などを直径数十メートルの円環状に並べたもの。日本では東北・北海道にみられる。ストーン-サークル。
環状列石
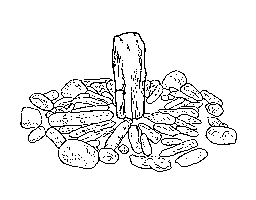 [図]
[図]
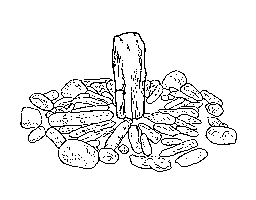 [図]
[図]
かん-じょう クワンヂヤウ [0] 【観場】🔗⭐🔉
かん-じょう クワンヂヤウ [0] 【観場】
展示場。陳列場。「―を開きしときは/西洋聞見録(文夫)」
かん-じょう クワンヂヤウ [0] 【灌頂】🔗⭐🔉
かん-じょう クワンヂヤウ [0] 【灌頂】
〔梵 abhi eka; abhi
eka; abhi ecana の訳。古くインドで,国王の即位,または立太子の際,頭頂に水を注いだ儀式から転じたもの〕
(1)〔仏〕(ア)菩薩が最終の位にはいる時,仏が智慧の水を注ぐこと。(イ)密教の儀式。伝法・授戒・結縁などのとき,香水(コウズイ)を受者の頭に注ぐこと。(ウ)墓参りなどのとき,墓に閼伽(アカ)の水を注ぎかけること。
(2)雅楽・謡物(ウタイモノ)・和歌などで秘曲や秘事を伝授すること。
ecana の訳。古くインドで,国王の即位,または立太子の際,頭頂に水を注いだ儀式から転じたもの〕
(1)〔仏〕(ア)菩薩が最終の位にはいる時,仏が智慧の水を注ぐこと。(イ)密教の儀式。伝法・授戒・結縁などのとき,香水(コウズイ)を受者の頭に注ぐこと。(ウ)墓参りなどのとき,墓に閼伽(アカ)の水を注ぎかけること。
(2)雅楽・謡物(ウタイモノ)・和歌などで秘曲や秘事を伝授すること。
 eka; abhi
eka; abhi ecana の訳。古くインドで,国王の即位,または立太子の際,頭頂に水を注いだ儀式から転じたもの〕
(1)〔仏〕(ア)菩薩が最終の位にはいる時,仏が智慧の水を注ぐこと。(イ)密教の儀式。伝法・授戒・結縁などのとき,香水(コウズイ)を受者の頭に注ぐこと。(ウ)墓参りなどのとき,墓に閼伽(アカ)の水を注ぎかけること。
(2)雅楽・謡物(ウタイモノ)・和歌などで秘曲や秘事を伝授すること。
ecana の訳。古くインドで,国王の即位,または立太子の際,頭頂に水を注いだ儀式から転じたもの〕
(1)〔仏〕(ア)菩薩が最終の位にはいる時,仏が智慧の水を注ぐこと。(イ)密教の儀式。伝法・授戒・結縁などのとき,香水(コウズイ)を受者の頭に注ぐこと。(ウ)墓参りなどのとき,墓に閼伽(アカ)の水を注ぎかけること。
(2)雅楽・謡物(ウタイモノ)・和歌などで秘曲や秘事を伝授すること。
かんじょう-だいほうおうじ クワンヂヤウダイホフワウジ 【灌頂大法王子】🔗⭐🔉
かんじょう-だいほうおうじ クワンヂヤウダイホフワウジ 【灌頂大法王子】
〔仏〕 灌頂を受けた菩薩の尊称。
かんじょう-だん クワンヂヤウ― [3] 【灌頂壇】🔗⭐🔉
かんじょう-だん クワンヂヤウ― [3] 【灌頂壇】
灌頂を行うために設ける壇。
大辞林 ページ 141773。