複数辞典一括検索+![]()
![]()
きかく-ばん [0] 【規格判】🔗⭐🔉
きかく-ばん [0] 【規格判】
ジス(JIS)による,書籍・雑誌・便箋などの紙の仕上げ寸法。
きかく-ひん [0] 【規格品】🔗⭐🔉
きかく-ひん [0] 【規格品】
規格に合わせて作った品物。
き-かく [0] 【棋客】🔗⭐🔉
き-かく [0] 【棋客】
囲碁や将棋をする人。棋士。ききゃく。
きかく 【其角】🔗⭐🔉
きかく 【其角】
⇒榎本(エノモト)其角
き-がく [1] 【貴学】🔗⭐🔉
き-がく [1] 【貴学】
相手の学校(大学)を敬っていう語。
き-がく [1] 【器楽】🔗⭐🔉
き-がく [1] 【器楽】
楽器のみで演奏する音楽。
⇔声楽
きがく-きょく [3] 【器楽曲】🔗⭐🔉
きがく-きょく [3] 【器楽曲】
器楽演奏のための曲。
⇔声楽曲
ぎ-かく [0] 【擬革】🔗⭐🔉
ぎ-かく [0] 【擬革】
人造皮革。
ぎかく-し [3][2] 【擬革紙】🔗⭐🔉
ぎかく-し [3][2] 【擬革紙】
外観を革に似せた紙。強くしなやかな紙に種々の薬品を塗り,型付けなどの特殊な仕上げをしたもの。室内や家具の装飾,書籍の表紙などに用いる。
ぎ-がく [1] 【伎楽】🔗⭐🔉
ぎ-がく [1] 【伎楽】
(1)612年百済(クダラ)から帰化した味摩之(ミマシ)が伝えたという,楽器演奏を伴う無言の仮面劇。法会の供養楽として八世紀後半に最も栄えたが,後伝の声明(シヨウミヨウ)や雅楽によって衰えた。呉楽(クレノガク)((クレガク)・(ゴガク))。くれのうたまい。
(2)仏典で,供養楽また天人の奏楽のこと。
ぎがく-し [3][2] 【伎楽師】🔗⭐🔉
ぎがく-し [3][2] 【伎楽師】
古代,伎楽生(ギガクシヨウ)に伎楽を教授した職。
ぎがく-しょう ―シヤウ [3] 【伎楽生】🔗⭐🔉
ぎがく-しょう ―シヤウ [3] 【伎楽生】
古代,伎楽を伝習した生徒。
ぎがく-めん [3] 【伎楽面】🔗⭐🔉
ぎがく-めん [3] 【伎楽面】
伎楽に用いた仮面。後頭部までもおおうよう大形に作られ,その表情は誇張されている。正倉院・法隆寺・東大寺などに伝存する。
伎楽面
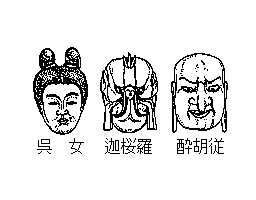 [図]
[図]
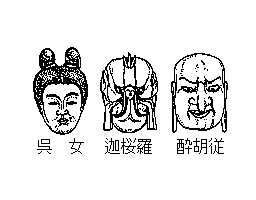 [図]
[図]
ぎ-がく [1] 【妓楽】🔗⭐🔉
ぎ-がく [1] 【妓楽】
妓女の奏する音楽。
ぎ-がく [1] 【偽学】🔗⭐🔉
ぎ-がく [1] 【偽学】
(1)正道にかなっていない学問。
(2)その時代に正統と認められなかった学問。異学。
大辞林 ページ 141955。