複数辞典一括検索+![]()
![]()
きくごろう キクゴラウ 【菊五郎】🔗⭐🔉
きくごろう キクゴラウ 【菊五郎】
⇒尾上(オノエ)菊五郎
きくごろう-ごうし キクゴラウガウ― [6] 【菊五郎格子】🔗⭐🔉
きくごろう-ごうし キクゴラウガウ― [6] 【菊五郎格子】
四本と五本の縞の格子の目に「キ」と「呂」の字を交互に入れた模様。「キ九五呂」に菊五郎をかけたもの。三代目尾上菊五郎の考案という。浴衣(ユカタ)地などに用いる。菊五郎縞。
菊五郎格子
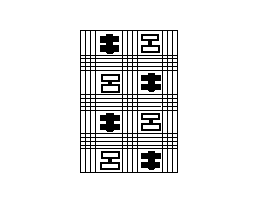 [図]
[図]
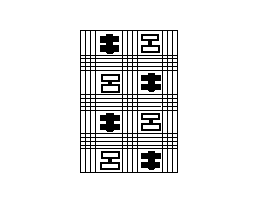 [図]
[図]
きく-ざ [0] 【菊座】🔗⭐🔉
きく-ざ [0] 【菊座】
(1)菊の花をかたどった座金(ザガネ)。武具・扉などに用いる。菊の座。菊重ね。
(2)ニホンカボチャの一品種。果実は扁球形で,深いたてみぞが多数はいる。キクザトウナス。
(3)肛門(コウモン)の異名。転じて,男色。「余程出来のいい―だと見えるなあ/滑稽本・七偏人」
きく-ざいく [3] 【菊細工】🔗⭐🔉
きく-ざいく [3] 【菊細工】
菊の枝を曲げ,花や葉を細工して,人や動物などさまざまの形に作ること。また,その作品。
きく-ざけ [2] 【菊酒】🔗⭐🔉
きく-ざけ [2] 【菊酒】
(1)菊の花を浸した酒。九月九日の重陽(チヨウヨウ)の節句に飲む。菊の酒。菊花の酒。
(2)味醂(ミリン)の一種。濃厚な味で,加賀国・肥後国の名産。
きく-ざし [0] 【菊尺】🔗⭐🔉
きく-ざし [0] 【菊尺】
江戸時代,菊の花の寸法をはかるのに用いた物差し。曲尺(カネジヤク)六寸(約18センチメートル)を一尺とした。きくじゃく。
きく-ざら [2][0] 【菊皿】🔗⭐🔉
きく-ざら [2][0] 【菊皿】
菊の花の形をした皿。また,菊の模様のついた陶器製の皿。
きくじどう 【菊慈童】🔗⭐🔉
きくじどう 【菊慈童】
(1)周の穆王(ボクオウ)に仕えた侍童(ジドウ)。罪あって南陽郡の 県(レキケン)に流され,その地で菊の露を飲み不老不死の仙童となったという。慈童。
→菊水(キクスイ)
(2)能の一。四番目物。{(1)}の伝説を脚色したもの。観世流以外では「枕(マクラ)慈童」。
県(レキケン)に流され,その地で菊の露を飲み不老不死の仙童となったという。慈童。
→菊水(キクスイ)
(2)能の一。四番目物。{(1)}の伝説を脚色したもの。観世流以外では「枕(マクラ)慈童」。
 県(レキケン)に流され,その地で菊の露を飲み不老不死の仙童となったという。慈童。
→菊水(キクスイ)
(2)能の一。四番目物。{(1)}の伝説を脚色したもの。観世流以外では「枕(マクラ)慈童」。
県(レキケン)に流され,その地で菊の露を飲み不老不死の仙童となったという。慈童。
→菊水(キクスイ)
(2)能の一。四番目物。{(1)}の伝説を脚色したもの。観世流以外では「枕(マクラ)慈童」。
大辞林 ページ 141994。