複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぎく-しゃく [1] (副)スル🔗⭐🔉
ぎく-しゃく [1] (副)スル
言葉や動作が滑らかでなく,ぎこちないさま。また,物事が滑らかに進まないさま。「―(と)動きまわる」「―した言い方」「―した関係」
きく-じゅつ [2] 【規矩術】🔗⭐🔉
きく-じゅつ [2] 【規矩術】
指し矩(ガネ)を用いて垂木や隅木などの建築部材の実形を幾何学的に割り出し,材木に墨付けをする技術。江戸幕府大棟梁の平内(ヘイノウチ)延臣(1791-1856)によって大成された。
きく-じゅんじょう [1] 【規矩準縄】🔗⭐🔉
きく-じゅんじょう [1] 【規矩準縄】
〔「孟子(離婁上)」より。「規」はコンパス,「矩」はさしがね,「準」はみずもり,「縄」はすみなわ〕
行為や物事の規準。法則。手本。規則。
きく-じん [0] 【鞠訊・鞫訊】 (名)スル🔗⭐🔉
きく-じん [0] 【鞠訊・鞫訊】 (名)スル
取り調べ,罪を問いただすこと。鞠問。「頻りに―したれども/鬼啾々(夢柳)」
きく-じん ―ヂン [0] 【麹塵】🔗⭐🔉
きく-じん ―ヂン [0] 【麹塵】
(1)色の名。ほとんど灰色みを帯びた黄緑色。古くは刈安(カリヤス)と紫根による染め色,近世は黄と青の糸による織り色をいう。天皇の略式の袍(ホウ)の色で禁色(キンジキ)の一。青色。山鳩。きじん。
(2)「麹塵の袍」の略。
きくじん-の-ほう ―ヂン―ハウ 【麹塵の袍】🔗⭐🔉
きくじん-の-ほう ―ヂン―ハウ 【麹塵の袍】
天皇が略儀に着用した麹塵色の袍。桐・竹・鳳凰(ホウオウ)・麒麟(キリン)を組み合わせて一単位とした文様が用いられた。六位の蔵人(クロウド)が拝領して着用することもあった。青色の袍。
きく・す 【掬す】 (動サ変)🔗⭐🔉
きく・す 【掬す】 (動サ変)
⇒きくする
き-くず ―クヅ [0][2] 【木屑】🔗⭐🔉
き-くず ―クヅ [0][2] 【木屑】
木材を切ったり削ったりしたときに出る屑。
きく-すい [2][0] 【菊水】🔗⭐🔉
きく-すい [2][0] 【菊水】
家紋の一。流水に半輪の菊花が浮かび出たもの。楠木(クスノキ)氏の紋章。
菊水
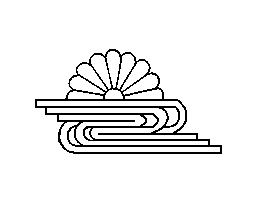 [図]
[図]
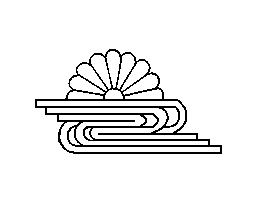 [図]
[図]
きく-すい 【菊水】🔗⭐🔉
きく-すい 【菊水】
中国,河南省内郷県にある河川。白河の支流。谷間に咲く大菊から露がしたたり落ち,川の水を飲んだ者は長寿であったという。また,この水で造った酒。菊の水。
→菊慈童(キクジドウ)
大辞林 ページ 141995。