複数辞典一括検索+![]()
![]()
きぬ-あんどん [3] 【絹行灯】🔗⭐🔉
きぬ-あんどん [3] 【絹行灯】
木や竹のわくに絹の布を張った行灯。
きぬ-いた 【衣板】🔗⭐🔉
きぬ-いた 【衣板】
「砧(キヌタ)」に同じ。[和名抄]
きぬ-いと [0] 【絹糸】🔗⭐🔉
きぬ-いと [0] 【絹糸】
蚕の繭からとった糸。生糸を含めず,精練した糸のみをいうことが多い。けんし。
きぬいと-そう ―サウ [0] 【絹糸草】🔗⭐🔉
きぬいと-そう ―サウ [0] 【絹糸草】
チモシー(オオアワガエリ)の種を水盤の脱脂綿にまいて萌(モ)え出た糸のような芽のこと。その鮮緑色の涼味を観賞する。[季]夏。
→稗蒔(ヒエマ)き
きぬ-うちわ ―ウチハ [4][3] 【絹団扇】🔗⭐🔉
きぬ-うちわ ―ウチハ [4][3] 【絹団扇】
絹の布を張ったうちわ。[季]夏。
きぬ-うんも [3] 【絹雲母】🔗⭐🔉
きぬ-うんも [3] 【絹雲母】
白雲母の一種。微細な鱗片状の鉱物。単斜晶系。絹糸状光沢がある。絹雲母結晶片岩の構成鉱物。また,熱水変質によって生成した粘土として産する。良質のものは陶土として利用。
きぬ-え ― [2] 【絹絵】🔗⭐🔉
[2] 【絹絵】🔗⭐🔉
きぬ-え ― [2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
[2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
 [2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
[2] 【絹絵】
絹の布地に描いた絵。
きぬ-おり [0] 【絹織(り)】🔗⭐🔉
きぬ-おり [0] 【絹織(り)】
絹糸で織ること。また,その織った布。
きぬおり-もの [3][4] 【絹織物】🔗⭐🔉
きぬおり-もの [3][4] 【絹織物】
絹糸で織った織物の総称。しなやかで光沢があり,染色性に富むため衣料として古くから用いられた。羽二重・縮緬(チリメン)・御召・紬(ツムギ)など。
きぬ-がき [2] 【絹垣】🔗⭐🔉
きぬ-がき [2] 【絹垣】
(1)神祭りなどの際,垣のようにめぐらす絹布のとばり。文垣(アヤガキ)。「亦其の山の上に―を張り帷幕を立てて/古事記(中訓)」
(2)神霊遷宮の際,御神体の上面,側面をおおう絹布。
きぬかけ-やま 【衣掛山】🔗⭐🔉
きぬかけ-やま 【衣掛山】
衣笠(キヌガサ)山の異名。宇多法皇が盛夏に雪景色を見ようとして,この山一面に白衣を敷きつめさせたという伝説による名。
きぬ-がさ [3][2] 【衣笠・絹傘・蓋】🔗⭐🔉
きぬ-がさ [3][2] 【衣笠・絹傘・蓋】
(1)絹を張った柄の長い傘。古く,貴人の外出の際,後ろからさしかけるのに用いた。「我が大君は―にせり/万葉 240」
(2)仏像にかざす天蓋(テンガイ)。[和名抄]
衣笠(1)
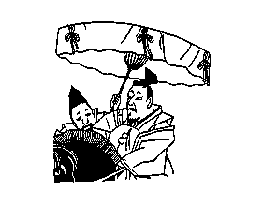 [図]
[図]
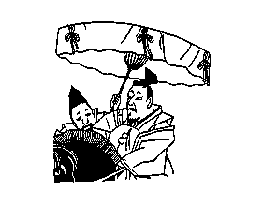 [図]
[図]
大辞林 ページ 142166。