複数辞典一括検索+![]()
![]()
きょうぎ-せっけい キヤウ― [4] 【競技設計】🔗⭐🔉
きょうぎ-せっけい キヤウ― [4] 【競技設計】
建築その他の設計に際し,複数の提案を競技によって求める設計方法。一般から募集する公開競技設計と,提案者を指名する指名競技設計がある。コンペティション。コンペ。
ぎょう-き ゲウ― [1] 【暁起】 (名)スル🔗⭐🔉
ぎょう-き ゲウ― [1] 【暁起】 (名)スル
早起きすること。「―して旅亭を発する/雪中梅(鉄腸)」
ぎょう-き ゲウ― [1] 【澆季】🔗⭐🔉
ぎょう-き ゲウ― [1] 【澆季】
〔「澆」は軽薄,「季」は末の意〕
(1)道義の衰え乱れた末の世。末世。季世。「道徳が腐敗したとか―になつたとか歎息する/一隅より(晶子)」
(2)後の世。後世。末代。「―に是をつたへけり/平治(上・古活字本)」
ぎょうき ギヤウキ 【行基】🔗⭐🔉
ぎょうき ギヤウキ 【行基】
(668-749) 奈良時代の僧。和泉の人。俗姓,高志氏。道昭・義淵らに法相(ホツソウ)教学を学ぶ。のち諸国をめぐり,架橋・築堤など社会事業を行い,民衆を教化し行基菩薩と敬われた。その活動が僧尼令に反するとして弾圧されたが,やがて聖武天皇の帰依を受け,東大寺・国分寺の造営に尽力し,大僧正に任ぜられ,また大菩薩の号を賜った。
ぎょうき-ず ギヤウキヅ [3] 【行基図】🔗⭐🔉
ぎょうき-ず ギヤウキヅ [3] 【行基図】
行基が作ったと伝えられる最古の日本総図。原本は残っていないが,諸図が伝えられている。
ぎょうき-ぶき ギヤウキ― [0] 【行基葺き】🔗⭐🔉
ぎょうき-ぶき ギヤウキ― [0] 【行基葺き】
本瓦葺(ホンカワラブ)きの一。先細りの丸瓦を細い方を上にして用い,少しずつ重ねながら下から上へ葺いていくもの。法隆寺の玉虫厨子(ズシ)宮殿屋根などに見られる。
行基葺き
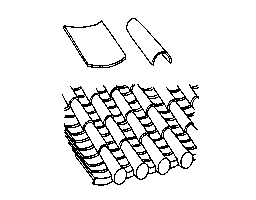 [図]
[図]
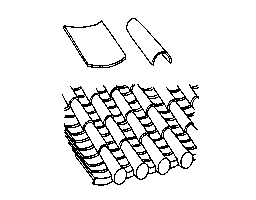 [図]
[図]
ぎょうき-やき ギヤウキ― [0] 【行基焼】🔗⭐🔉
ぎょうき-やき ギヤウキ― [0] 【行基焼】
〔行基が始めたという〕
須恵器(スエキ)の俗称。ねずみ色をした素焼きの土器。
ぎょう-ぎ ギヤウ― [0] 【行儀】🔗⭐🔉
ぎょう-ぎ ギヤウ― [0] 【行儀】
(1)作法にかなうかどうかという点から見た立ち居振る舞い。「―が悪い」「―良くしていなさい」「―を知らない」
(2)おこない。しわざ。したこと。「見限りはてた旦那殿,悉皆盗人の―か/浄瑠璃・大経師(上)」
(3)〔仏〕 法会や修法の定められた方式。「聖(ヒジリ)が―を見給へば/平家 10」
大辞林 ページ 142374。