複数辞典一括検索+![]()
![]()
きょく-ない [2] 【局内】🔗⭐🔉
きょく-ない [2] 【局内】
局と名のつく役所・組織の内部。また,その管轄内。
⇔局外
きょく-のみ [0] 【曲飲み】🔗⭐🔉
きょく-のみ [0] 【曲飲み】
曲芸として,酒などを変わった飲み方で飲んで見せること。
きょく-のり [0] 【曲乗り】 (名)スル🔗⭐🔉
きょく-のり [0] 【曲乗り】 (名)スル
自転車・馬・玉などに曲芸のような変わった乗り方で乗ること。また,それらに乗って曲芸をすること。
きょく-ば [0] 【曲馬】🔗⭐🔉
きょく-ば [0] 【曲馬】
馬の曲乗りや,馬を使った曲芸。
きょくば-し [3] 【曲馬師】🔗⭐🔉
きょくば-し [3] 【曲馬師】
曲馬を演ずる人。
きょくば-だん [3] 【曲馬団】🔗⭐🔉
きょくば-だん [3] 【曲馬団】
馬術の曲芸・猛獣の曲芸・軽業(カルワザ)・手品などを興行して各地をまわる芸人の一座。サーカス。
ぎょく-はい [0] 【玉佩】🔗⭐🔉
ぎょく-はい [0] 【玉佩】
即位・大嘗会(ダイジヨウエ)などの儀式の際に,礼服につけた飾り。五色の玉を貫いた組糸五本を金銅の花形につないで胸から足先に垂らし,歩くと沓(クツ)先に当たって音をたてる。天皇は左右に二本,臣下は右に一本下げる。
玉佩
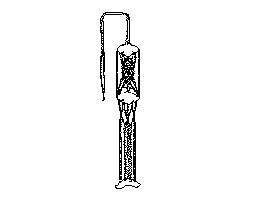 [図]
[図]
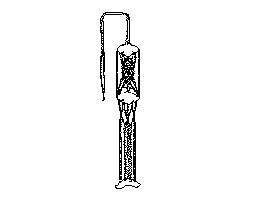 [図]
[図]
ぎょく-はい [0] 【玉杯】🔗⭐🔉
ぎょく-はい [0] 【玉杯】
玉で作った杯。また,杯の美称。
ぎょく-はく [0] 【玉帛】🔗⭐🔉
ぎょく-はく [0] 【玉帛】
玉と絹織物。特に中国古代,諸侯の朝覲(チヨウキン)・聘問(ヘイモン)・会盟のときに用いたもの。
きょく-ばち [0] 【曲撥】🔗⭐🔉
きょく-ばち [0] 【曲撥】
(1)撥で,太鼓の曲打ちまたは三味線の曲弾きをすること。
(2)歌舞伎の下座音楽の一。曲芸の伴奏を取り入れたもの。太鼓・大太鼓の音をおさえて篠笛(シノブエ)を繰り返して吹く。「助六」の引っ込みなどに使う。
きょく-ばん [0] 【局版】🔗⭐🔉
きょく-ばん [0] 【局版】
煎茶席で,風炉の下に敷く陶器・金属・木製の台。風炉台。
きょく-ばん [0] 【局番】🔗⭐🔉
きょく-ばん [0] 【局番】
各電話加入区域および電話交換局につけられた番号。市内局番と市外局番がある。
ぎょく-ばん [0] 【玉盤】🔗⭐🔉
ぎょく-ばん [0] 【玉盤】
玉で飾って作った大皿やたらい。また,皿の美称。
ぎょく-ばん [0] 【玉旛・玉幡】🔗⭐🔉
ぎょく-ばん [0] 【玉旛・玉幡】
〔「旛」「幡」は旗の意〕
高御座(タカミクラ)の八角の棟の下にかける旗の形をした飾り。玉を鎖であやどり,先端に薄金の杏葉(ギヨウヨウ)をつける。
大辞林 ページ 142506。