複数辞典一括検索+![]()
![]()
くかい-せき ククワイ― [2] 【苦灰石】🔗⭐🔉
くかい-せき ククワイ― [2] 【苦灰石】
⇒ドロマイト
くがい-そう ―サウ [0] 【九蓋草】🔗⭐🔉
くがい-そう ―サウ [0] 【九蓋草】
ゴマノハグサ科の多年草。山中に自生。茎は直立し高さ1メートルあまり。葉は広披針形で,一節に数個輪生して数段になる。夏,茎頂に多数の青紫色の小花を穂状につける。根茎は利尿薬。虎の尾。
九蓋草
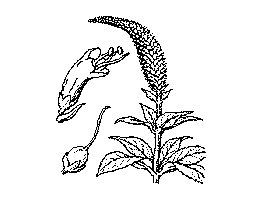 [図]
[図]
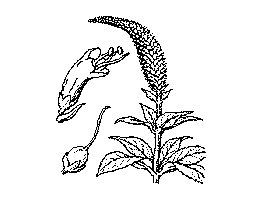 [図]
[図]
く-かく ―クワク [0] 【区画・区劃】 (名)スル🔗⭐🔉
く-かく ―クワク [0] 【区画・区劃】 (名)スル
土地・場所を一定の基準で区切ること。また,その区切られたひとつひとつ。「埋め立て地を―する」「分譲地を一―買う」
くかく-ぎょぎょう ―クワク―ゲフ [4] 【区画漁業】🔗⭐🔉
くかく-ぎょぎょう ―クワク―ゲフ [4] 【区画漁業】
免許漁業の一。水面を区画して行う漁業。海苔(ノリ)・魚類・貝類の養殖業など。
くかく-せいり ―クワク― [4] 【区画整理】🔗⭐🔉
くかく-せいり ―クワク― [4] 【区画整理】
都市計画などで,土地の区画や境界・道路などを変更・整備すること。
→土地区画整理
く-がく [1] 【苦学】 (名)スル🔗⭐🔉
く-がく [1] 【苦学】 (名)スル
(1)働いて学資を得るなど,苦しい生活環境の中で学問をすること。「―して大学を出る」「―生」
(2)苦労して学問をすること。「―力行(リツコウ)」
ぐ-かく [1] 【具格】🔗⭐🔉
ぐ-かく [1] 【具格】
〔instrumental〕
格にかかわる文法範疇の一。手段・道具(…デ)などの意を表す。
くが-じ ―ヂ [0][2] 【陸路】🔗⭐🔉
くが-じ ―ヂ [0][2] 【陸路】
陸上を通る道。りくろ。
⇔海路(ウミジ)
「城を構へて船路・―を支へんとす/太平記 16」
く-かず [2][0] 【句数】🔗⭐🔉
く-かず [2][0] 【句数】
(1)句の数。
(2)連歌・俳諧で,百韻や歌仙一巻中同種の季や題材の句を何句まで続けてもよいか規定したもの。例えば連歌の百韻では春・秋・恋などは五句に,夏・冬・旅などは三句に制限される。
くか-たち [0] 【探湯・誓湯】🔗⭐🔉
くか-たち [0] 【探湯・誓湯】
〔「くがたち」とも〕
上代,事の是非,正邪が決しにくいとき,神意をうかがう方法。神に誓約して熱湯の中に手を入れさせるもので,正しいものは火傷(ヤケド)せず,邪(ヨコシマ)なものは火傷するとされた。「諸の氏姓の人等沐浴(ユカワア)み斎戒(キヨマワ)りて各―をせよ/日本書紀(允恭訓注)」
大辞林 ページ 142776。