複数辞典一括検索+![]()
![]()
くさ-ぶえ [0][3] 【草笛】🔗⭐🔉
くさ-ぶえ [0][3] 【草笛】
(1)草で作った笛。草の葉や茎を口にあて,笛のように吹き鳴らすもの。[季]夏。《―の子や吾を見て又吹ける/星野立子》
(2)雅楽用の笛に対して,俗楽に用いる七孔の横笛。しのぶえ。
くさ-ぶか 【草深】 (名・形動ナリ)🔗⭐🔉
くさ-ぶか 【草深】 (名・形動ナリ)
〔「くさふか」とも〕
草が深く生い茂っているさま。また,その場所。「もとありつる山中の―なり/十訓 1」
くさぶか-ゆり 【草深百合】🔗⭐🔉
くさぶか-ゆり 【草深百合】
草深い所に生えている百合。「道の辺の―の花笑みに/万葉 1257」
くさ-ぶか・い [4] 【草深い】 (形)[文]ク くさぶか・し🔗⭐🔉
くさ-ぶか・い [4] 【草深い】 (形)[文]ク くさぶか・し
〔「くさふかい」とも〕
(1)草が深く茂っている。「―・い原野」
(2)ひなびている。辺鄙(ヘンピ)である。「―・い田舎に育つ」
くさ-ぶき [0] 【草葺き】🔗⭐🔉
くさ-ぶき [0] 【草葺き】
茅(カヤ)・藁(ワラ)などを用いて屋根を葺くこと。また,その屋根。
くさぶき-やね [5] 【草葺き屋根】🔗⭐🔉
くさぶき-やね [5] 【草葺き屋根】
草葺きの屋根。草屋根。くさぶき。
くさ-ふぐ [0][3] 【草河豚】🔗⭐🔉
くさ-ふぐ [0][3] 【草河豚】
フグ目の海魚。全長20センチメートル内外。背面はくすんだ青緑色で小白紋が散在し,腹面は白色。砂中へ潜る習性がある。猛毒をもち,食用にしない。本州以南,沖縄・朝鮮の沿岸に分布。スナフグ。
→フグ
くさ-ふじ ―フヂ [0][2] 【草藤】🔗⭐🔉
くさ-ふじ ―フヂ [0][2] 【草藤】
マメ科のつる性多年草。草地に自生。葉は披針形の小葉からなる羽状複葉。初夏,葉腋に青紫色の蝶形花を総状につける。牧草として利用。
くさ-ぶし 【草臥し】🔗⭐🔉
くさ-ぶし 【草臥し】
(1)鹿などが草の上にふすこと。また,その場所。「さ雄鹿の小野の―いちしろく/万葉 2268」
(2)山野に野宿すること。「から衣きつつならしのおのが―/新撰六帖 5」
くさ-ぼうき ―バウキ [3] 【草箒】🔗⭐🔉
くさ-ぼうき ―バウキ [3] 【草箒】
ホウキグサをたばねて作った手ぼうき。
くさ-ぼけ [0][3] 【草木瓜】🔗⭐🔉
くさ-ぼけ [0][3] 【草木瓜】
バラ科の落葉小低木。日当たりのよい地に群生する。高さ約40センチメートル。葉は倒卵形。早春,朱紅色の五弁花をつける。果実は球形で,黄熟し酸味が強い。シドミ。地梨(ジナシ)。[季]春。
草木瓜
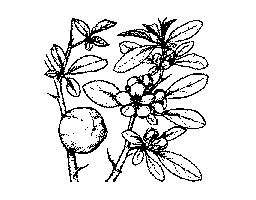 [図]
[図]
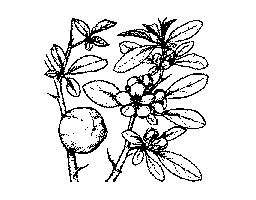 [図]
[図]
大辞林 ページ 142811。