複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぐそく-がね 【具足金】🔗⭐🔉
ぐそく-がね 【具足金】
武士がいざという時の備えに具足櫃に入れておく金。「此時―,十両有りしに/浮世草子・武家義理物語 1」
ぐそく-ざいく [4] 【具足細工】🔗⭐🔉
ぐそく-ざいく [4] 【具足細工】
甲冑(カツチユウ)を細工すること。また,その職人。
ぐそく-し [3] 【具足師】🔗⭐🔉
ぐそく-し [3] 【具足師】
甲冑(カツチユウ)を作る職人。
ぐそく-じた [0] 【具足下】🔗⭐🔉
ぐそく-じた [0] 【具足下】
当世具足の下に着る装束。
ぐそく-だい ―ダヒ [3] 【具足鯛】🔗⭐🔉
ぐそく-だい ―ダヒ [3] 【具足鯛】
エビスダイの別名。
ぐそく-だな [0][3] 【具足棚】🔗⭐🔉
ぐそく-だな [0][3] 【具足棚】
床の間・書院などの脇に設けられる棚の一種。
ぐそく-に [0] 【具足煮】🔗⭐🔉
ぐそく-に [0] 【具足煮】
〔殻を鎧(ヨロイ)に見たてていう〕
イセエビ・クルマエビを殻のついたまま筒切りにして煮た料理。
ぐそく-ばおり [4] 【具足羽織】🔗⭐🔉
ぐそく-ばおり [4] 【具足羽織】
⇒陣羽織(ジンバオリ)
ぐそく-びつ [3] 【具足櫃】🔗⭐🔉
ぐそく-びつ [3] 【具足櫃】
甲冑(カツチユウ)を入れる箱。
具足櫃
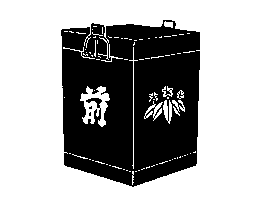 [図]
[図]
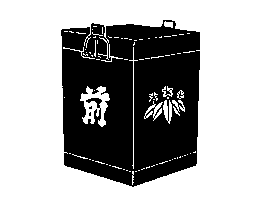 [図]
[図]
ぐそく-びらき 【具足開き】🔗⭐🔉
ぐそく-びらき 【具足開き】
武家の年中行事の一。正月に男子が甲冑(カツチユウ)にそなえた具足餅を,日を決めて食べた。江戸時代,幕府は正月二〇日,1652年からは一一日に行なった。女子の鏡開きに相応する。具足の祝い。具足の鏡開き。
ぐそく-ぶぎょう ―ギヤウ [4] 【具足奉行】🔗⭐🔉
ぐそく-ぶぎょう ―ギヤウ [4] 【具足奉行】
江戸幕府の職名。御留守居支配に属し,甲冑(カツチユウ)の保管をつかさどった。
ぐそく-むしゃ [4] 【具足武者】🔗⭐🔉
ぐそく-むしゃ [4] 【具足武者】
甲冑(カツチユウ)を着用した武士。
ぐそく-もち [3] 【具足餅】🔗⭐🔉
ぐそく-もち [3] 【具足餅】
「鎧餅(ヨロイモチ)」に同じ。
ぐそく-や [0] 【具足屋】🔗⭐🔉
ぐそく-や [0] 【具足屋】
甲冑(カツチユウ)を作り,また商う店。
ぐ-そく [0] 【愚息】🔗⭐🔉
ぐ-そく [0] 【愚息】
自分の息子をへりくだっていう語。豚児。
大辞林 ページ 142866。