複数辞典一括検索+![]()
![]()
くも-たちわき [4] 【雲立ち涌き】🔗⭐🔉
くも-たちわき [4] 【雲立ち涌き】
立ち涌き模様の一。立ち涌きの中に雲形をあしらったもの。上皇・親王・摂政の指貫(サシヌキ),関白の袍(ホウ)の文(モン)に用いる。くもたてわく。
雲立ち涌き
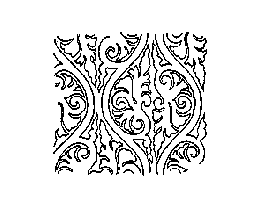 [図]
[図]
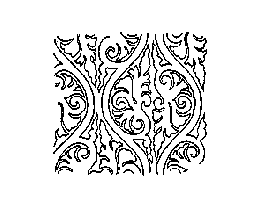 [図]
[図]
く-もつ 【公物】🔗⭐🔉
く-もつ 【公物】
〔「く」は呉音〕
おおやけのもの。官有のもの。こうもつ。「人有りて―を犯す事あらば罰すべし/今昔 2」
く-もつ [1] 【供物】🔗⭐🔉
く-もつ [1] 【供物】
神仏・寺社などに,供養(クヨウ)のためそなえるもの。そなえもの。
くも-で [0] 【蜘蛛手】🔗⭐🔉
くも-で [0] 【蜘蛛手】
(1)蜘蛛の足のように四方八方に出ていること。放射状に広がり,または組み合わされている状態。「水行く河の―なれば/伊勢 9」
(2)橋の梁(ハリ)・桁(ケタ)を支えるため,橋脚から筋交いに渡した材木。「五月雨に水まさるらしうち橋や―にかかる波の白糸/山家(夏)」
(3)細い材を打ち違えに組んだ,灯明皿や手水鉢(チヨウズバチ)などをのせる台。
(4)刀・棒などを四方八方に振り回す動作。「―,かくなわ,十文字,とんばう返り,水車,八方すかさず切つたりけり/平家 4」
(5)あれこれと思い乱れること。「うち渡し長き心は八橋の―に思ふことは絶えせじ/後撰(恋一)」
くもで-ごうし ―ガウ― [4] 【蜘蛛手格子】🔗⭐🔉
くもで-ごうし ―ガウ― [4] 【蜘蛛手格子】
木材や鉄棒などを縦横に交えて厳重にこしらえた格子。獄屋などにとりつける。
くもで-の-はし 【蜘蛛手の橋】🔗⭐🔉
くもで-の-はし 【蜘蛛手の橋】
池の上などに四方へ架け渡した橋。
くも-と [2][0] 【雲斗】🔗⭐🔉
くも-と [2][0] 【雲斗】
雲形の斗(マス)。普通,雲肘木(クモヒジキ)と組み合わせて用いる。法隆寺金堂・五重塔など飛鳥時代の寺院建築にみられる。うんと。
くも-とり 【雲鳥】🔗⭐🔉
くも-とり 【雲鳥】
(1)雲の中を飛ぶ鳥。「―も帰る夕べの山風に/玉葉(雑二)」
(2)雲と鶴(ツル)との模様。雲鶴(ウンカク)。「―の紋の綾をや染むべき/大和 159」
くもとり-の 【雲鳥の】 (枕詞)🔗⭐🔉
くもとり-の 【雲鳥の】 (枕詞)
鶴と雲の文様を綾に用いたことから,「あやに」にかかる。「はかなきことも―あやに叶はぬくせなれば/千載(雑下)」
大辞林 ページ 142998。