複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぐ-ゆう ―イウ [0] 【具有】 (名)スル🔗⭐🔉
ぐ-ゆう ―イウ [0] 【具有】 (名)スル
(性質・能力・条件などを)そなえもっていること。「千手千足千眼を―せる異形の人なるかと/月世界旅行(勤)」
くゆぼ・る (動ラ四)🔗⭐🔉
くゆぼ・る (動ラ四)
声がこもって弱々しく聞こえる。「こわづかひ,少しかれいろにて―・りたるほど/野守鏡」
くゆら-か・す 【燻らかす】 (動サ四)🔗⭐🔉
くゆら-か・す 【燻らかす】 (動サ四)
くゆらせる。「火桶に侍従(=香ノ名)を―・して/源氏(初音)」
くゆら・す [3] 【燻らす】🔗⭐🔉
くゆら・す [3] 【燻らす】
■一■ (動サ五[四])
煙を立てる。煙るように燃す。「葉巻きを―・す」「―・す香もわが命も消ゆる間近き薄煙/浄瑠璃・島原蛙合戦」
〔「くゆる」に対する他動詞〕
■二■ (動サ下二)
⇒くゆらせる
くゆら・せる [4] 【燻らせる】 (動サ下一)[文]サ下二 くゆら・す🔗⭐🔉
くゆら・せる [4] 【燻らせる】 (動サ下一)[文]サ下二 くゆら・す
ゆるやかに煙をたてる。くゆらす。「紫煙を―・せる」
くゆ・る [2] 【燻る・薫る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
くゆ・る [2] 【燻る・薫る】 (動ラ五[四])
(1)炎を出さずに燃えて,煙が立つ。ふすぼる。くすぶる。「タバコが―・る」
(2)表面に出さないで,心の中で思い悩む。「人しれぬ心のうちに燃ゆる火は煙は立たで―・りこそすれ/大和 171」
く-よう ―エウ [0] 【九曜】🔗⭐🔉
く-よう ―エウ [0] 【九曜】
(1)「九曜星」の略。
(2)家紋の一。一個の円の周囲に八個の小円を配した紋。
九曜(2)
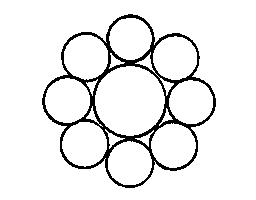 [図]
[図]
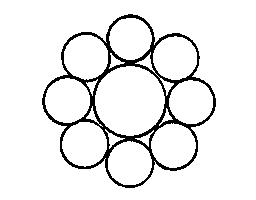 [図]
[図]
くよう-せい ―エウ― [0][2] 【九曜星】🔗⭐🔉
くよう-せい ―エウ― [0][2] 【九曜星】
日・月・木・火・土・金・水の七曜星に羅 (ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。
(ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。
 (ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。
(ラゴ)・計都の二星を加えたもの。仏教の暦法からおこり,陰陽家が人の生年に配当して,運命の吉凶を判ずるようになった。九曜。
く-よう ―ヤウ 【口養】🔗⭐🔉
く-よう ―ヤウ 【口養】
〔「く」は呉音〕
暮らしむき。糊口(ココウ)。生計。「―の資無くして子に後れたる老母は/太平記 11」
く-よう 【公用】🔗⭐🔉
く-よう 【公用】
〔「く」は呉音〕
(1)公の用務。こうよう。
(2)中世,公事(クジ)として賦課された銭貨。公用銭。
大辞林 ページ 143007。