複数辞典一括検索+![]()
![]()
し-き [1][2] 【紫気】🔗⭐🔉
し-き [1][2] 【紫気】
(霞などのために)紫色を帯びた大気。「相模灘上の―いよいよ勢猛く/自然と人生(蘆花)」
しき 【志木】🔗⭐🔉
しき 【志木】
埼玉県中南部の市。近世,奥州から甲州・相州への脇街道の宿場町。現代は住宅地として発展。
しき 【史記】🔗⭐🔉
しき 【史記】
中国最初の紀伝体の通史。二十四史の一。一三〇巻。前漢の司馬遷著。紀元前91年頃完成。上古の黄帝から前漢の武帝までの歴史を記す。本紀一二巻,表一〇巻,書八巻,世家(セイカ)三〇巻,列伝七〇巻から成る。後世,正史の模範とされた。注釈書に南朝の宋の裴 (ハイイン)の「史記集解(シツカイ)」,唐の司馬貞の「史記索隠」,唐の張守節の「史記正義」などがある。太史公書。
(ハイイン)の「史記集解(シツカイ)」,唐の司馬貞の「史記索隠」,唐の張守節の「史記正義」などがある。太史公書。
 (ハイイン)の「史記集解(シツカイ)」,唐の司馬貞の「史記索隠」,唐の張守節の「史記正義」などがある。太史公書。
(ハイイン)の「史記集解(シツカイ)」,唐の司馬貞の「史記索隠」,唐の張守節の「史記正義」などがある。太史公書。
しき (副助)🔗⭐🔉
しき (副助)
〔名詞「しき(式)」から〕
(1)指示代名詞「これ」「それ」「あれ」などに付いて,物事の動作・状態などを取るに足らない程度とみなして軽視する気持ちを表す。くらい。ほど。「これ―のことには驚かない」「それ―の傷で泣くな」
(2)人代名詞に付いて,…みたいなもの,…のようなものなどの意を表す。「我等―にはもつたいないと/洒落本・無頼通説法」「おのれ―ぶち放すも刀の穢れ/浄瑠璃・新版歌祭文」
しぎ [1] 【鴫・鷸】🔗⭐🔉
しぎ [1] 【鴫・鷸】
チドリ目シギ科とその近縁の科の鳥の総称。一般に,長いくちばしと脚をもつ。水辺にすみ,小魚・甲殻類・ゴカイ類・昆虫などを食べる。長距離の渡りを行うものが多く,日本では春・秋に旅鳥として通過する種が大部分である。[季]秋。
鴫
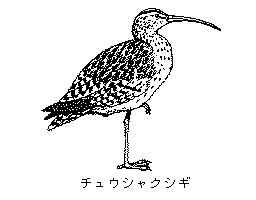 [図]
[図]
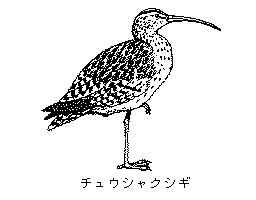 [図]
[図]
――の看経(カンキン)🔗⭐🔉
――の看経(カンキン)
鴫が田や沢に静かにたたずんでいるさまを,経を読む姿に見立てていう語。
――の羽返(ハガエ)し🔗⭐🔉
――の羽返(ハガエ)し
舞の手の名。また,剣術・相撲の手の一。
大辞林 ページ 145446。