複数辞典一括検索+![]()
![]()
しちし-とう ―タウ [3] 【七支刀】🔗⭐🔉
しちし-とう ―タウ [3] 【七支刀】
奈良県天理市石上(イソノカミ)神宮所蔵の古代の鉄剣。長さ75センチメートルで,刀身の左右に三本ずつの枝刀が出ている。刀身の両面に銘文があり,百済から日本に贈られたものであることがわかる。四世紀後半の作。ななつさやのたち。
七支刀
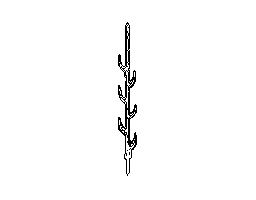 [図]
[図]
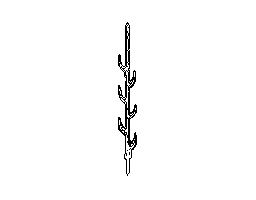 [図]
[図]
しち-しみん [1]-[1] 【私地私民】🔗⭐🔉
しち-しみん [1]-[1] 【私地私民】
私有地と私有民。土地や人民の私的所有が認められること。
⇔公地公民
しち-しゃ 【七社】🔗⭐🔉
しち-しゃ 【七社】
⇒山王七社(サンノウシチシヤ)
しち-しゃく [2] 【七尺】🔗⭐🔉
しち-しゃく [2] 【七尺】
一尺(約30.3センチメートル)の七倍。
――下がって師(シ)の影(カゲ)を踏(フ)まず🔗⭐🔉
――下がって師(シ)の影(カゲ)を踏(フ)まず
⇒三尺(サンジヤク)去(サ)って師の影を踏まず
しち-しゅ [2] 【七衆】🔗⭐🔉
しち-しゅ [2] 【七衆】
〔仏〕 仏弟子を七種に分類したもの。比丘(ビク)・比丘尼・式叉摩那(シキサマナ)・沙弥(シヤミ)・沙弥尼・優婆塞(ウバソク)・優婆夷(ウバイ)をいう。道俗七衆。
しち-しゅう [2][0] 【七宗】🔗⭐🔉
しち-しゅう [2][0] 【七宗】
(1)仏教の七宗派。律宗・法相宗・三論宗・華厳宗・天台宗・真言宗・禅宗をいう。
(2)禅宗の七分派。曹洞宗・雲門宗・法眼(ホウゲン)宗・臨済宗・ 仰(イギヨウ)宗・楊岐(ヨウギ)宗・黄竜宗をいう。
→五家(ゴケ)七宗
仰(イギヨウ)宗・楊岐(ヨウギ)宗・黄竜宗をいう。
→五家(ゴケ)七宗
 仰(イギヨウ)宗・楊岐(ヨウギ)宗・黄竜宗をいう。
→五家(ゴケ)七宗
仰(イギヨウ)宗・楊岐(ヨウギ)宗・黄竜宗をいう。
→五家(ゴケ)七宗
しち-じゅう ―ジフ [3] 【七十】🔗⭐🔉
しち-じゅう ―ジフ [3] 【七十】
(1)一〇の七倍の数。ななじゅう。
(2)七〇歳。
――にして矩(ノリ)をこえず🔗⭐🔉
――にして矩(ノリ)をこえず
〔論語(為政)〕
人間七〇歳ともなれば,心の欲するままに行動しても道理をはずれることはない。
しち-じゅう ―ヂユウ [0] 【七重】🔗⭐🔉
しち-じゅう ―ヂユウ [0] 【七重】
七つ重なっていること。また,そのもの。「―の塔」「―奏」
しちじゅう-ほうじゅ ―ヂユウ― [5] 【七重宝樹】🔗⭐🔉
しちじゅう-ほうじゅ ―ヂユウ― [5] 【七重宝樹】
〔仏〕 極楽にあるという七重に並んだ七種の宝樹。金樹・銀樹・瑠璃(ルリ)樹・玻璃(ハリ)樹・珊瑚(サンゴ)樹・瑪瑙(メノウ)樹・
 (シヤコ)樹。また,黄金の根・紫金(シゴン)の茎・白銀の枝・瑪瑙の条・珊瑚の葉・白玉の花・真珠の菓をもった七宝の宝樹ともいわれる。「鳧雁(フガン)鴛鴦(エンノウ)につばさをならべ,―の梢に翔(カケ)り/謡曲・初雪」
(シヤコ)樹。また,黄金の根・紫金(シゴン)の茎・白銀の枝・瑪瑙の条・珊瑚の葉・白玉の花・真珠の菓をもった七宝の宝樹ともいわれる。「鳧雁(フガン)鴛鴦(エンノウ)につばさをならべ,―の梢に翔(カケ)り/謡曲・初雪」

 (シヤコ)樹。また,黄金の根・紫金(シゴン)の茎・白銀の枝・瑪瑙の条・珊瑚の葉・白玉の花・真珠の菓をもった七宝の宝樹ともいわれる。「鳧雁(フガン)鴛鴦(エンノウ)につばさをならべ,―の梢に翔(カケ)り/謡曲・初雪」
(シヤコ)樹。また,黄金の根・紫金(シゴン)の茎・白銀の枝・瑪瑙の条・珊瑚の葉・白玉の花・真珠の菓をもった七宝の宝樹ともいわれる。「鳧雁(フガン)鴛鴦(エンノウ)につばさをならべ,―の梢に翔(カケ)り/謡曲・初雪」
大辞林 ページ 145691。