複数辞典一括検索+![]()
![]()
じゃ-おどり ―ヲドリ [2] 【蛇踊り】🔗⭐🔉
じゃ-おどり ―ヲドリ [2] 【蛇踊り】
蛇腹胴(ジヤバラドウ)の張り子の大きな竜を棒に結び,十数人でささげて練り回る踊り。もと中国で行われた踊りが長崎のおくんち祭(竜踊(ジヤオドリ))などに伝わったもの。
シャオビン [2] 【焼餅】🔗⭐🔉
シャオビン [2] 【焼餅】
〔中国語〕
小麦粉の生地を発酵させ,丸く延ばして焼いたもの。
しゃ-おり [0] 【紗織(り)】🔗⭐🔉
しゃ-おり [0] 【紗織(り)】
「紗(シヤ)」に同じ。
しゃ-おん [0] 【謝恩】 (名)スル🔗⭐🔉
しゃ-おん [0] 【謝恩】 (名)スル
受けた恩に対する感謝の気持ち。また,その気持ちを表すこと。
しゃおん-かい ―クワイ [2][0] 【謝恩会】🔗⭐🔉
しゃおん-かい ―クワイ [2][0] 【謝恩会】
感謝の気持ちを表すための会。普通,学生・生徒が卒業するとき教職員に感謝する意味で開く会をいう。
しゃおん-さい [2] 【謝恩祭】🔗⭐🔉
しゃおん-さい [2] 【謝恩祭】
「酬恩祭(シユウオンサイ)」に同じ。
しゃおん-もじ [4] 【写音文字】🔗⭐🔉
しゃおん-もじ [4] 【写音文字】
(1)言語学で,音声を表すために作った特殊な文字。音声符号。
(2)「表音文字」に同じ。
しゃ-か [1] 【社歌】🔗⭐🔉
しゃ-か [1] 【社歌】
その会社・結社の設立の精神をあらわし,行事などで歌う歌。
しゃ-か [1] 【瀉下】 (名)スル🔗⭐🔉
しゃ-か [1] 【瀉下】 (名)スル
(1)水などを激しくそそぎくだすこと。「五六丈の懸崖を―す/十和田湖(桂月)」
(2)下痢(ゲリ)。
しゃか 【釈迦】🔗⭐🔉
しゃか 【釈迦】
〔梵 
 kya〕
(1)紀元前七〜六世紀頃,ヒマラヤ山麓ネパールに居住していた部族。釈迦{(2)}も釈迦族の出身。
(2)仏教の開祖。世界四聖の一人。姓はゴータマ,名はシッタルタ。中部ネパールの釈迦族の中心地迦毘羅(カビラ)城に浄飯王(ジヨウボンノウ)の子として生まれる。母は摩耶夫人(マヤブニン)。二九歳で出家,三五歳で悟りを得た。のち鹿野園(ロクヤオン)で五人の修行者を教化し(仏教教団の成立),以後八〇歳で入滅(ニユウメツ)するまで教化の旅を続けた。教説は四諦(シタイ)・八正道(ハツシヨウドウ)・十二縁起などでまとめられる。生没年は紀元前463〜383年,同560〜480年など諸説ある。釈迦牟尼(シヤカムニ)。釈尊。釈迦如来。
釈迦(2)
kya〕
(1)紀元前七〜六世紀頃,ヒマラヤ山麓ネパールに居住していた部族。釈迦{(2)}も釈迦族の出身。
(2)仏教の開祖。世界四聖の一人。姓はゴータマ,名はシッタルタ。中部ネパールの釈迦族の中心地迦毘羅(カビラ)城に浄飯王(ジヨウボンノウ)の子として生まれる。母は摩耶夫人(マヤブニン)。二九歳で出家,三五歳で悟りを得た。のち鹿野園(ロクヤオン)で五人の修行者を教化し(仏教教団の成立),以後八〇歳で入滅(ニユウメツ)するまで教化の旅を続けた。教説は四諦(シタイ)・八正道(ハツシヨウドウ)・十二縁起などでまとめられる。生没年は紀元前463〜383年,同560〜480年など諸説ある。釈迦牟尼(シヤカムニ)。釈尊。釈迦如来。
釈迦(2)
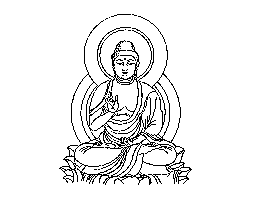 [図]
[図]

 kya〕
(1)紀元前七〜六世紀頃,ヒマラヤ山麓ネパールに居住していた部族。釈迦{(2)}も釈迦族の出身。
(2)仏教の開祖。世界四聖の一人。姓はゴータマ,名はシッタルタ。中部ネパールの釈迦族の中心地迦毘羅(カビラ)城に浄飯王(ジヨウボンノウ)の子として生まれる。母は摩耶夫人(マヤブニン)。二九歳で出家,三五歳で悟りを得た。のち鹿野園(ロクヤオン)で五人の修行者を教化し(仏教教団の成立),以後八〇歳で入滅(ニユウメツ)するまで教化の旅を続けた。教説は四諦(シタイ)・八正道(ハツシヨウドウ)・十二縁起などでまとめられる。生没年は紀元前463〜383年,同560〜480年など諸説ある。釈迦牟尼(シヤカムニ)。釈尊。釈迦如来。
釈迦(2)
kya〕
(1)紀元前七〜六世紀頃,ヒマラヤ山麓ネパールに居住していた部族。釈迦{(2)}も釈迦族の出身。
(2)仏教の開祖。世界四聖の一人。姓はゴータマ,名はシッタルタ。中部ネパールの釈迦族の中心地迦毘羅(カビラ)城に浄飯王(ジヨウボンノウ)の子として生まれる。母は摩耶夫人(マヤブニン)。二九歳で出家,三五歳で悟りを得た。のち鹿野園(ロクヤオン)で五人の修行者を教化し(仏教教団の成立),以後八〇歳で入滅(ニユウメツ)するまで教化の旅を続けた。教説は四諦(シタイ)・八正道(ハツシヨウドウ)・十二縁起などでまとめられる。生没年は紀元前463〜383年,同560〜480年など諸説ある。釈迦牟尼(シヤカムニ)。釈尊。釈迦如来。
釈迦(2)
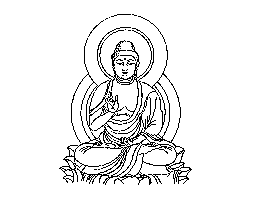 [図]
[図]
大辞林 ページ 145989。