複数辞典一括検索+![]()
![]()
す-さき [0] 【洲崎】🔗⭐🔉
す-さき [0] 【洲崎】
(1)州がみさきのように海中または河中に突き出た所。
(2){(1)}の形をした模様。「正月布子と見えてもえぎ色に染かのこの―/浮世草子・胸算用 5」
すさき 【洲崎】🔗⭐🔉
すさき 【洲崎】
東京都江東区木場東隣一帯の通称。元禄年間(1688-1704),埋め立てでできた新地。洲崎神社がある。
すさき 【須崎】🔗⭐🔉
すさき 【須崎】
高知県中部,須崎湾に臨む市。鰹漁港として栄え,現在は水産加工・養殖,石灰・セメント工業が盛ん。
すざく [1][0] 【朱雀】🔗⭐🔉
すざく [1][0] 【朱雀】
(1)四方をつかさどる天の四神(シジン)の一。鳥の姿で表され,南方に配する。朱鳥。しゅじゃく。
(2)二十八宿のうち,南方七宿の総称。
(3)「朱雀大路」「朱雀門」の略。
朱雀(1)
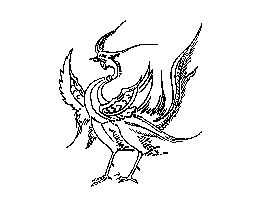 [図]
[図]
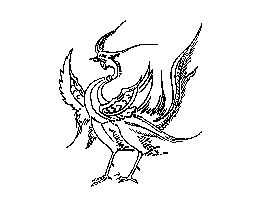 [図]
[図]
すざく-いん ― ン 【朱雀院】🔗⭐🔉
ン 【朱雀院】🔗⭐🔉
すざく-いん ― ン 【朱雀院】
平安時代の後院の一。嵯峨天皇以後,代々の天皇が譲位後に住んだ御所。朱雀大路の西,三条の南に八町を占めていた。
ン 【朱雀院】
平安時代の後院の一。嵯峨天皇以後,代々の天皇が譲位後に住んだ御所。朱雀大路の西,三条の南に八町を占めていた。
 ン 【朱雀院】
平安時代の後院の一。嵯峨天皇以後,代々の天皇が譲位後に住んだ御所。朱雀大路の西,三条の南に八町を占めていた。
ン 【朱雀院】
平安時代の後院の一。嵯峨天皇以後,代々の天皇が譲位後に住んだ御所。朱雀大路の西,三条の南に八町を占めていた。
すざく-おおじ ―オホヂ 【朱雀大路】🔗⭐🔉
すざく-おおじ ―オホヂ 【朱雀大路】
平城京・平安京の中央を南北に走る大路。大内裏の南面の朱雀門から南端の羅城門に至る。この大路の東を左京,西を右京という。今の京都市では千本通りがほぼこれにあたる。しゅじゃくおおじ。
すざく-もん 【朱雀門】🔗⭐🔉
すざく-もん 【朱雀門】
平安京大内裏の外郭十二門の一。南面中央にある。南門。しゅじゃくもん。
→大内裏
すざく-てんのう ―テンワウ 【朱雀天皇】🔗⭐🔉
すざく-てんのう ―テンワウ 【朱雀天皇】
(923-952) 第六一代天皇(在位930-946)。名は寛明(ユタアキラ)。醍醐天皇第一一皇子。
すさのお-の-みこと スサノヲ― 【素戔嗚尊・須佐之男命】🔗⭐🔉
すさのお-の-みこと スサノヲ― 【素戔嗚尊・須佐之男命】
記紀神話で出雲系神統の祖とされる神。伊弉諾(イザナキ)・伊弉冉(イザナミ)二尊の子。天照大神(アマテラスオオミカミ)の弟。粗野な性格から天の石屋戸の事件を起こしたため根の国に追放されたが,途中,出雲国で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治して奇稲田姫(クシナダヒメ)を救い,大蛇の尾から天叢雲剣(アマノムラクモノツルギ)を得て天照大神に献じた。新羅に渡って金・銀・木材を持ち帰り,また植林を伝えたともいわれる。「出雲国風土記」では温和な農耕神とされる。
大辞林 ページ 147288。