複数辞典一括検索+![]()
![]()
てんま-いん [3] 【伝馬印】🔗⭐🔉
てんま-いん [3] 【伝馬印】
戦国大名がその分国内における伝馬の使用を許可・命令する文書(伝馬手形)に押した朱印。伝馬朱印。
てんま-おくり [4] 【伝馬送り】🔗⭐🔉
てんま-おくり [4] 【伝馬送り】
「宿(シユク)継ぎ」に同じ。
てんま-こみ [0] 【伝馬込み】🔗⭐🔉
てんま-こみ [0] 【伝馬込み】
大型の和船の船体中央部に設けた,伝馬船を引き入れるための出入り口。はしけこみ。
→和船
てんま-しゅいん [4] 【伝馬朱印】🔗⭐🔉
てんま-しゅいん [4] 【伝馬朱印】
⇒伝馬印(テンマイン)
てんま-じょ [0][4] 【伝馬所】🔗⭐🔉
てんま-じょ [0][4] 【伝馬所】
江戸時代,諸街道の宿場で,運送に携わる人足・馬匹のために指定された特定の家屋・場所。
てんま-せん [0] 【伝馬船】🔗⭐🔉
てんま-せん [0] 【伝馬船】
小型の和船。普通,本船に搭載され岸との間の荷物の積み降ろしに用いられた。橋船。はしけ。てんまぶね。
伝馬船
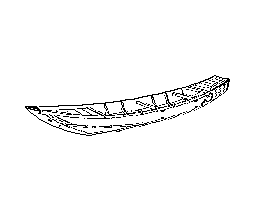 [図]
[図]
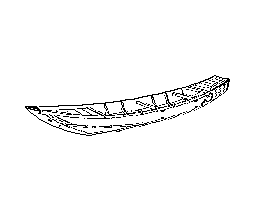 [図]
[図]
てんま-そうどう ―サウ― 【伝馬騒動】🔗⭐🔉
てんま-そうどう ―サウ― 【伝馬騒動】
1764〜65年,幕府の伝馬助郷役への増助郷(マシスケゴウ)に反対して起きた広域農民一揆。武蔵・上野(コウズケ)・下野(シモツケ)・信濃四国に広がりをみせたが,関東郡代伊奈半左衛門は要求受け入れを約し,農民側の勝利のうちに収拾。主謀者,関兵内(セキノヘイナイ)はのち獄門に処された。
てんま-ちょう ―チヤウ 【伝馬町】🔗⭐🔉
てんま-ちょう ―チヤウ 【伝馬町】
(1)江戸開府の際,伝馬を業とする人々が集住した,現在の東京都中央区日本橋付近の町名。大伝馬町・小伝馬町に分かれる。のちに江戸を代表する問屋街となった。また,小伝馬町には幕府の牢屋敷が置かれた。
(2)牢屋の異称。「朝帰り座敷へ―が出来/柳多留 22」
てんま-やく [3] 【伝馬役】🔗⭐🔉
てんま-やく [3] 【伝馬役】
伝馬の提供,またそれに伴う労を提供する課役。戦国時代より行われたが,江戸時代に最も発達。
大辞林 ページ 150283。