複数辞典一括検索+![]()
![]()
とけい-しゅう ―シウ [2] 【徒刑囚】🔗⭐🔉
とけい-しゅう ―シウ [2] 【徒刑囚】
徒刑に処せられた囚人。
とけい-ば [0] 【徒刑場】🔗⭐🔉
とけい-ば [0] 【徒刑場】
徒刑囚が服役する所。
と-けい [0] 【時計・土圭】🔗⭐🔉
と-けい [0] 【時計・土圭】
時間を計ったり,時刻を示したりする機械。錘(オモリ)・ぜんまい・電気などの力で運動させて,振り子または天府の振動の等時性を利用して,歯車で指針を等時的に進ませる装置。これを機械時計といい,これ以前には日時計・水時計・砂時計・火時計などがあった。現在では水晶発振や分子振動の等時性を利用したきわめて精度の高いものが開発,実用化されている。形式・用途によって懐中時計・腕時計・置き時計・掛け時計・ストップ-ウォッチ・クロノメーターなどの種類があり,時刻の表示方式によりアナログ式とデジタル式のものに大別される。液晶デジタル表示により,機械的な部品を全く必要としないものが普及している。
〔「時計」は,中国周代に用いられた緯度測定器「土圭」の当て字という〕
とけい-ざ [0] 【時計座】🔗⭐🔉
とけい-ざ [0] 【時計座】
〔(ラテン) Horologium〕
一月上旬の宵に南中する南天の星座。日本からは北の一部だけが見える。
とけい-ざら [2] 【時計皿】🔗⭐🔉
とけい-ざら [2] 【時計皿】
理化学実験に使用する,直径約2〜20センチメートルくらいの時計のふたのようなガラス皿。
とけい-じかけ [4] 【時計仕掛(け)】🔗⭐🔉
とけい-じかけ [4] 【時計仕掛(け)】
時計の働きによって,一定の時限に作動するようにした装置。
とけい-しんかん ―クワン [4] 【時計信管】🔗⭐🔉
とけい-しんかん ―クワン [4] 【時計信管】
時計装置を用いた時限信管。高射砲弾などに用いる。
とけい-すうじ [4] 【時計数字】🔗⭐🔉
とけい-すうじ [4] 【時計数字】
〔時計の文字盤の時刻を表す数字が多くこれを用いることから〕
ローマ数字。
とけい-そう ―サウ [0] 【時計草】🔗⭐🔉
とけい-そう ―サウ [0] 【時計草】
トケイソウ科のつる性常緑多年草。ブラジル原産。日本には享保年間(1716-1736)に渡来。葉は互生し,掌状に深裂。夏,葉腋の花柄に径8センチメートル内外の花を付ける。萼(ガク)片・花弁は各五個ずつあり,ほぼ同形の長楕円形で平開してつき,白色ときに淡紅色を帯びる。その内側に多数の淡紫色の糸状体から成る副冠がある。果実は卵形の液果。花を時計に見立てこの名がある。観賞用。ボロンカズラ。パッシフロラ。
時計草
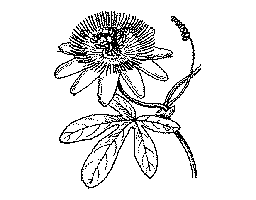 [図]
[図]
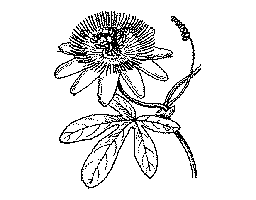 [図]
[図]
大辞林 ページ 150636。