複数辞典一括検索+![]()
![]()
な-るい [1] 【菜類】🔗⭐🔉
な-るい [1] 【菜類】
葉や茎を食用とする野菜。葉菜(ヨウサイ)類。
なる・い 【緩い】 (形)🔗⭐🔉
なる・い 【緩い】 (形)
(1)〔近世語〕
なまぬるい。「―・くいふとつきあがつて/滑稽本・続膝栗毛(七上)」
(2)ゆるやかである。なだらかである。
〔主に西日本で用いられる〕
なる-いた 【鳴る板】🔗⭐🔉
なる-いた 【鳴る板】
「見参(ゲンザン)の板」に同じ。
なる-かみ 【鳴る神】🔗⭐🔉
なる-かみ 【鳴る神】
かみなり。
なるかみ-の 【鳴る神の】 (枕詞)🔗⭐🔉
なるかみ-の 【鳴る神の】 (枕詞)
雷は音だけが聞こえて姿が見えないことから,「音(オト)」もしくは「音のみ聞く」にかかる。「―音のみ聞きしみ吉野の真木立つ山ゆ見下ろせば/万葉 915」
なるかみ 【鳴神】🔗⭐🔉
なるかみ 【鳴神】
歌舞伎十八番の一。1684年に江戸中村座上演の「門松四天王」が原拠かといわれる。現在上演されているものは,津打半十郎ら合作で,1742年大坂大西芝居で初演された「雷神(ナルカミ)不動北山桜」の四幕目が原典。能の「一角仙人」から取材し,朝廷に恨みをもつ鳴神上人が竜神を封じこめるが,雲の絶間姫の色香に迷い呪法が破れ雨が降るという筋。
なる-くち 【成る口】🔗⭐🔉
なる-くち 【成る口】
飲める口。酒の飲める人。「二人ながら―ゆゑ,あひのおさへのと飲みかけ/滑稽本・膝栗毛(初)」
なる-こ [0] 【鳴子】🔗⭐🔉
なる-こ [0] 【鳴子】
田畑の害獣・害鳥を追い払う具。数本の竹筒を小板に並べてぶら下げたもの。張った縄につるしたり竿(サオ)の先につけたりし,縄の端を引くなどして揺らして鳴らす。[季]秋。
鳴子
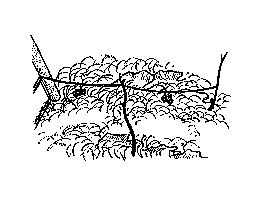 [図]
[図]
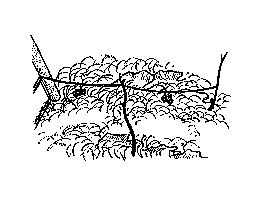 [図]
[図]
大辞林 ページ 151289。
 Narkissos
Narkissos