複数辞典一括検索+![]()
![]()
にかえし-ず ―カヘシ― [4] 【煮返し酢】🔗⭐🔉
にかえし-ず ―カヘシ― [4] 【煮返し酢】
塩を入れて煮立てた酢。さまして料理・漬物などに用いる。
に-かえ・す ―カヘス [3][2] 【煮返す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
に-かえ・す ―カヘス [3][2] 【煮返す】 (動サ五[四])
一度煮たものをもう一度煮る。煮直す。「おでんを―・す」
に-がお ―ガホ [0] 【似顔】🔗⭐🔉
に-がお ―ガホ [0] 【似顔】
「似顔絵」の略。「芳幾(ヨシイク)に―を画(カカ)せて/安愚楽鍋(魯文)」
にがお-え ―ガホ [0] 【似顔絵】🔗⭐🔉
[0] 【似顔絵】🔗⭐🔉
にがお-え ―ガホ [0] 【似顔絵】
(1)ある人の顔に似せて描いた絵。
(2)浮世絵で,役者絵・美人絵のこと。
[0] 【似顔絵】
(1)ある人の顔に似せて描いた絵。
(2)浮世絵で,役者絵・美人絵のこと。
 [0] 【似顔絵】
(1)ある人の顔に似せて描いた絵。
(2)浮世絵で,役者絵・美人絵のこと。
[0] 【似顔絵】
(1)ある人の顔に似せて描いた絵。
(2)浮世絵で,役者絵・美人絵のこと。
にか-かい ニクワクワイ 【二科会】🔗⭐🔉
にか-かい ニクワクワイ 【二科会】
美術団体。1914年(大正3)設立。文展洋画部に第二部設置を求めて入れられなかった石井柏亭・有島生馬らが結成。毎秋,公募展を開催。
にが-かしゅう [3] 【苦何首烏】🔗⭐🔉
にが-かしゅう [3] 【苦何首烏】
ヤマノイモ科のつる性多年草。山地の林縁に自生。地下にひげ根のある丸い黒色の塊根があるが,苦みが多く,食用にならない。塊根を食用にするカシュウイモはこの栽培品種。
にが-き [0] 【苦木】🔗⭐🔉
にが-き [0] 【苦木】
ニガキ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル。葉は互生し,大形の羽状複葉。小葉は対生する。枝・葉に強い苦みがある。木部を苦味健胃薬とし,材は緻密で器具・細工物とする。クボク。
苦木
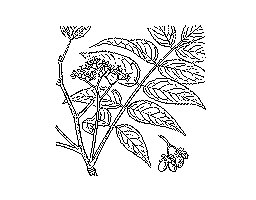 [図]
[図]
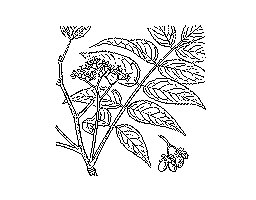 [図]
[図]
にが-ぐち [0] 【苦口】🔗⭐🔉
にが-ぐち [0] 【苦口】
憎らしく感じさせる物言い。憎まれ口。「さしてもない事,―言ふて/浄瑠璃・薩摩歌」
にが-くりたけ [4][3] 【苦栗茸】🔗⭐🔉
にが-くりたけ [4][3] 【苦栗茸】
坦子菌類ハラタケ目の毒きのこ。春から秋にかけて各地の林の中の切り株などに多数群生する。食用のクリタケに似るが小形で傘は径2〜5センチメートル,全体が硫黄色で苦みがある。
に-がさ [0] 【荷嵩】🔗⭐🔉
に-がさ [0] 【荷嵩】
荷物がかさばること。荷物のかさ。
にが・し 【苦し】 (形ク)🔗⭐🔉
にが・し 【苦し】 (形ク)
⇒にがい(苦)
にが-しお ―シホ [0] 【苦塩】🔗⭐🔉
にが-しお ―シホ [0] 【苦塩】
「苦汁(ニガリ)」に同じ。
にが-しお ―シホ [0] 【苦潮】🔗⭐🔉
にが-しお ―シホ [0] 【苦潮】
赤潮(アカシオ)の別名。[季]夏。
大辞林 ページ 151374。