複数辞典一括検索+![]()
![]()
にっ-と [0] (副)スル🔗⭐🔉
にっ-と [0] (副)スル
声を立てずに歯を見せてちょっと笑うさま。「―笑う」
にっ-とう ―タウ [0] 【入唐】 (名)スル🔗⭐🔉
にっ-とう ―タウ [0] 【入唐】 (名)スル
奈良・平安時代,日本から僧や留学生が中国の唐に行くこと。
にっとう-し ―タウ― [3] 【入唐使】🔗⭐🔉
にっとう-し ―タウ― [3] 【入唐使】
奈良・平安時代に日本から唐に派遣された使節。遣唐使。
にっとう-たいし ―タウ― [5] 【入唐大使】🔗⭐🔉
にっとう-たいし ―タウ― [5] 【入唐大使】
遣唐使の長官。
にっとう-はっけ ―タウ― 【入唐八家】🔗⭐🔉
にっとう-はっけ ―タウ― 【入唐八家】
平安初期,唐に渡り密教を学んだ八人の僧侶。最澄・空海・常暁・円行・円仁・慧運・円珍・宗叡の八人。
にっ-とう ―タウ [0] 【日当】🔗⭐🔉
にっ-とう ―タウ [0] 【日当】
一日単位に支払われる給料。日給。
にっ-とう [0] 【日東】🔗⭐🔉
にっ-とう [0] 【日東】
〔中国から見て,日の昇る東方の国の意〕
日本の称。
にっとうぐほうじゅんれいこうき ニツタウグホフジユンレイカウキ 【入唐求法巡礼行記】🔗⭐🔉
にっとうぐほうじゅんれいこうき ニツタウグホフジユンレイカウキ 【入唐求法巡礼行記】
中国旅行記。四巻。円仁著。838年入唐してから各地の霊場を巡り,847年に帰国するまでの日記体の見聞記。入唐巡礼記。
ニッパー [1]  nipper
nipper 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ニッパー [1]  nipper
nipper 主として銅線の切断,電線の被覆をむくのに用いる電気用工具。
ニッパー
主として銅線の切断,電線の被覆をむくのに用いる電気用工具。
ニッパー
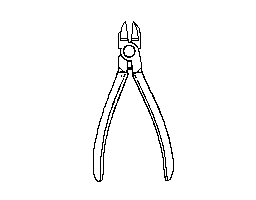 [図]
[図]
 nipper
nipper 主として銅線の切断,電線の被覆をむくのに用いる電気用工具。
ニッパー
主として銅線の切断,電線の被覆をむくのに用いる電気用工具。
ニッパー
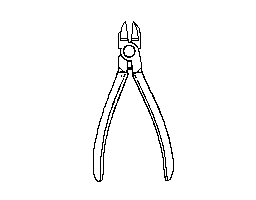 [図]
[図]
にっ-ぱい 【日牌】🔗⭐🔉
にっ-ぱい 【日牌】
位牌の前で毎日読経供養すること。また,その位牌。「―を供へ申すにつき/浄瑠璃・万年草(上)」
にっ-ぱち [0] 【二八】🔗⭐🔉
にっ-ぱち [0] 【二八】
二月と八月。商売や興行などで不景気な月とされる。
ニッパ-やし [4] 【―椰子】🔗⭐🔉
ニッパ-やし [4] 【―椰子】
〔(マレー) nipah〕
ヤシ科の常緑低木。インド・太平洋諸島に広く分布。マングローブの林に近接して群生。幹はなく,泥土中をはう根茎から,長さ3〜10メートルに達する羽状複葉を直立。果実は大形の集合果で,食用となる。柄を切って得る汁から砂糖・酒を造る。葉は屋根ふき材料とし,また,籠や帽子を編む。
にっぱら 【日原】🔗⭐🔉
にっぱら 【日原】
東京都奥多摩町北部の地域。日原川上流域で,鍾乳洞がある。
大辞林 ページ 151483。