複数辞典一括検索+![]()
![]()
のろのろ・し 【呪呪し】 (形シク)🔗⭐🔉
のろのろ・し 【呪呪し】 (形シク)
のろわしい。いまいましい。恨めしい。「―・しき事ども多かり/栄花(花山)」
のろ-ま [0] 【鈍間・野呂松】🔗⭐🔉
のろ-ま [0] 【鈍間・野呂松】
■一■ (名・形動)
〔■二■の意から〕
(1)動作がにぶく,気がきかない・こと(さま)。そのような人にもいう。「―な男」
(2)「のろま色」の略。「銅杓子かして―にして返し/柳多留(初)」
■二■ (名)
「野呂松(ノロマ)人形」の略。
のろま-いろ 【鈍間色】🔗⭐🔉
のろま-いろ 【鈍間色】
〔野呂松(ノロマ)人形の顔の色から〕
青黒い色。「板じめの―になつたほそおびをしめ/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」
のろま-ざる [4] 【鈍間猿】🔗⭐🔉
のろま-ざる [4] 【鈍間猿】
⇒ロリス
のろま-づかい ―ヅカヒ [4] 【野呂松遣い】🔗⭐🔉
のろま-づかい ―ヅカヒ [4] 【野呂松遣い】
野呂松人形を遣う人形遣い。寛文(1661-1673)・延宝(1673-1681)期の江戸和泉太夫芝居の野呂松勘兵衛や貞享(1684-1688)・元禄(1688-1704)期ののろま治兵衛が名高い。
のろま-にんぎょう ―ギヤウ [4] 【野呂松人形・野呂間人形】🔗⭐🔉
のろま-にんぎょう ―ギヤウ [4] 【野呂松人形・野呂間人形】
人形浄瑠璃の間(アイ)狂言として演じられた道化人形。頭が平たく顔の青黒い,卑しげな一人遣いの人形で,俗語を交えた狂言風の台詞(セリフ)で演じる。間狂言は1715年の「国性爺合戦」上演から除かれ,劇場からは脱落して現在は新潟県佐渡などにわずかに伝承されている。
→曾呂間(ソロマ)人形
野呂松人形
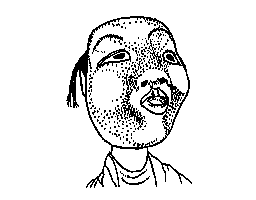 [図]
[図]
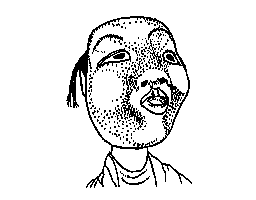 [図]
[図]
のろり [2][3] (副)🔗⭐🔉
のろり [2][3] (副)
(多く「と」を伴って)
(1)動作の鈍いさま。のろのろ。のんびり。「―と人の顔を見る/大内旅宿(虚子)」
(2)なんとなく。ふらりと。「ゆふべ―と帰つた所が,内へは這入られねえから/滑稽本・浮世風呂 3」
のろわし・い ノロハシイ [4] 【呪わしい】 (形)[文]シク のろは・し🔗⭐🔉
のろわし・い ノロハシイ [4] 【呪わしい】 (形)[文]シク のろは・し
〔動詞「のろう」の形容詞化〕
のろいたい気持ちである。「―・い戦争の爪跡(ツメアト)」
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
大辞林 ページ 151928。