複数辞典一括検索+![]()
![]()
はちのへ-せん 【八戸線】🔗⭐🔉
はちのへ-せん 【八戸線】
JR 東日本の鉄道線。青森県八戸・岩手県久慈間,64.9キロメートル。三陸縦貫鉄道の一部をなす。
はちのへ-だいがく 【八戸大学】🔗⭐🔉
はちのへ-だいがく 【八戸大学】
私立大学の一。1981年(昭和56)設立。本部は八戸市。
はち-の-み 【鉢の実】🔗⭐🔉
はち-の-み 【鉢の実】
〔中世女性語〕
すりこぎ。[日葡]
はちはい-どうふ [5] 【八杯豆腐】🔗⭐🔉
はちはい-どうふ [5] 【八杯豆腐】
豆腐料理の一。水四杯,醤油二杯,酒二杯の割合の汁で拍子木に切った豆腐を煮たもの。
はち-はち [0] 【八八】🔗⭐🔉
はち-はち [0] 【八八】
花札の遊び方で,勝負を決める最高得点目標を八八点におくもの。
はち-はち 【鉢鉢】 (感)🔗⭐🔉
はち-はち 【鉢鉢】 (感)
托鉢僧が物を乞う時に言う語。「御ぞんじの坊主―浮世ぢやな―昔ぢやな―/浮世草子・椀久一世(下)」
ぱち-ぱち [1] (副)スル🔗⭐🔉
ぱち-ぱち [1] (副)スル
(1)小さくて硬いものが繰り返し当たって発する軽快な音を表す語。「―(と)手をたたく」「算盤(ソロバン)を―と入れる」
(2)熱せられたものがはじけたり,火花が散る音を表す語。「ゴマが―はぜる」
(3)しきりにまばたきをするさま。「驚いて目を―させる」
はちはち-かんたい 【八八艦隊】🔗⭐🔉
はちはち-かんたい 【八八艦隊】
アメリカを仮想敵とし,戦艦八隻,巡洋戦艦八隻を主力とする,旧日本海軍の建艦計画。1920年(大正9)予算措置が講じられたが,翌年のワシントン軍縮会議の結果中止となった。
は-ちびき [2] 【葉血引】🔗⭐🔉
は-ちびき [2] 【葉血引】
魚,チビキの別名。
はち-びたい ―ビタヒ 【鉢額】🔗⭐🔉
はち-びたい ―ビタヒ 【鉢額】
はげ上がって,広く突き出た額。
はち-びょう ―ビヤウ [0][2] 【八病】🔗⭐🔉
はち-びょう ―ビヤウ [0][2] 【八病】
⇒詩八病(シハチヘイ)
ばち-びん [0] 【撥鬢】🔗⭐🔉
ばち-びん [0] 【撥鬢】
元禄(1688-1704)の頃流行した男の髪形の一。鬢を,耳の上を細く,後ろへゆくほど広くしたもの。
撥鬢
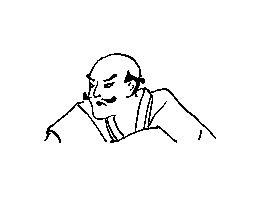 [図]
[図]
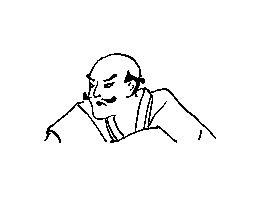 [図]
[図]
ばちびん-しょうせつ ―セウ― [5] 【撥鬢小説】🔗⭐🔉
ばちびん-しょうせつ ―セウ― [5] 【撥鬢小説】
村上浪六の「三日月」をはじめとする撥鬢奴の達引(タテヒ)きを描いた小説の称。明治30年代に流行。
大辞林 ページ 152259。