複数辞典一括検索+![]()
![]()
はち-ひんし [3] 【八品詞】🔗⭐🔉
はち-ひんし [3] 【八品詞】
西欧語の文法で立てられる八つの品詞分類。名詞・代名詞・動詞・形容詞・副詞・接続詞・前置詞・感動詞の称。
〔明治前期,大槻文彦は,それにならって日本語について名詞・動詞・形容詞・助動詞・副詞・接続詞・てにをは(=助詞)・感動詞の八品詞を認めた〕
はち-ぶ [2] 【八分】🔗⭐🔉
はち-ぶ [2] 【八分】
(1)全体の八割。十割にやや満たない程度。「―通り読んだ」「腹―」
(2)仲間から除外すること。のけものにすること。「 茶番の役不足をいうて―されたるくやしみ/滑稽本・客者評判記」
→村八分
はちぶ-おんぷ [4] 【八分音符】🔗⭐🔉
はちぶ-おんぷ [4] 【八分音符】
全音符の八分の一,四分音符の半分の長さを表す音符。はちぶんおんぷ。
音符(1)
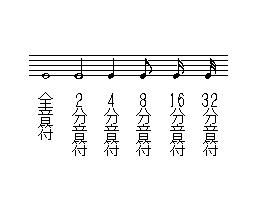 [図]
[図]
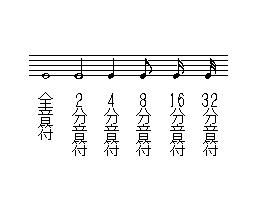 [図]
[図]
はち-ぶ [2] 【八部】🔗⭐🔉
はち-ぶ [2] 【八部】
「八部衆」の略。
はちぶ-しゅう [3] 【八部衆】🔗⭐🔉
はちぶ-しゅう [3] 【八部衆】
(1)仏法守護の八体一組みの釈迦の眷属(ケンゾク)。
(2)特に「天竜(テンリユウ)八部衆」のこと。
はち-ぶ・く 【蜂吹く】 (動カ四)🔗⭐🔉
はち-ぶ・く 【蜂吹く】 (動カ四)
不満気な顔をする。ふくれ面をする。「鼻などうち赤めつつ,―・きいへば/源氏(松風)」
はち-ふくでん [4][3] 【八福田】🔗⭐🔉
はち-ふくでん [4][3] 【八福田】
〔仏〕
〔尊敬・供養または施しをすれば福徳を生ずる八種の田の意〕
仏・聖人・和尚(オシヨウ)・阿闍梨(アジヤリ)・僧・父・母・病人の八つをいう。
はち-ふり [0] 【鉢振(り)】🔗⭐🔉
はち-ふり [0] 【鉢振(り)】
先のとがった陣笠。戊辰(ボシン)戦争の頃用いられた。
はちぶん-ぎ [3] 【八分儀】🔗⭐🔉
はちぶん-ぎ [3] 【八分儀】
航海に用いた簡易天文測量器械。天体の高度を測って船の位置を決めるのに使った。四五度(円周の八分の一)の円弧を用いるのでこの名がある。六分儀の前身。オクタント。
はちぶんぎ-ざ [0] 【八分儀座】🔗⭐🔉
はちぶんぎ-ざ [0] 【八分儀座】
〔(ラテン) Octans〕
天の南極を含む星座。日本からは見えない。
はちぶん-め [5][0] 【八分目】🔗⭐🔉
はちぶん-め [5][0] 【八分目】
全体の八割程度。また,内輪にとどめておくこと。「腹―」
大辞林 ページ 152260。