複数辞典一括検索+![]()
![]()
はち-へいじ [3] 【八平氏】🔗⭐🔉
はち-へいじ [3] 【八平氏】
〔「はちへいし」とも〕
桓武平氏の末流で,関東に土着した八家の豪族。千葉・上総・三浦・土肥・秩父・大庭・梶原・長尾の八氏。坂東八平氏。
はちべえ ハチベ 【八兵衛】🔗⭐🔉
【八兵衛】🔗⭐🔉
はちべえ ハチベ 【八兵衛】
(1)近世,庶民の代表的な名。また,田舎者の通称。「権兵衛が褄褸(サシコ)から―が羽二重に移り/滑稽本・浮世風呂(前)」
(2)下総国船橋の飯盛り女。「あるじ出て,―なんめさるべくやといひたるを/滑稽本・旅眼石」
(3)「権兵衛{(2)}」に同じ。
【八兵衛】
(1)近世,庶民の代表的な名。また,田舎者の通称。「権兵衛が褄褸(サシコ)から―が羽二重に移り/滑稽本・浮世風呂(前)」
(2)下総国船橋の飯盛り女。「あるじ出て,―なんめさるべくやといひたるを/滑稽本・旅眼石」
(3)「権兵衛{(2)}」に同じ。
 【八兵衛】
(1)近世,庶民の代表的な名。また,田舎者の通称。「権兵衛が褄褸(サシコ)から―が羽二重に移り/滑稽本・浮世風呂(前)」
(2)下総国船橋の飯盛り女。「あるじ出て,―なんめさるべくやといひたるを/滑稽本・旅眼石」
(3)「権兵衛{(2)}」に同じ。
【八兵衛】
(1)近世,庶民の代表的な名。また,田舎者の通称。「権兵衛が褄褸(サシコ)から―が羽二重に移り/滑稽本・浮世風呂(前)」
(2)下総国船橋の飯盛り女。「あるじ出て,―なんめさるべくやといひたるを/滑稽本・旅眼石」
(3)「権兵衛{(2)}」に同じ。
はち-ぼうず ―バウズ [3] 【鉢坊主】🔗⭐🔉
はち-ぼうず ―バウズ [3] 【鉢坊主】
托鉢をしてまわる乞食坊主。鉢坊。はっちぼうず。鉢開き坊主。「天王寺に―に衣の日借しを渡世にする出家あり/浮世草子・織留 5」
鉢坊主
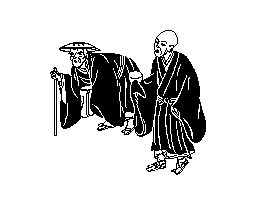 [図]
[図]
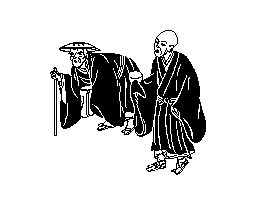 [図]
[図]
はち-ぼく [0] 【八木】🔗⭐🔉
はち-ぼく [0] 【八木】
(1)〔「米」の字を分解すると「八」「木」の二字になるので〕
米の異名。「難波の入湊に―の商売をして/浮世草子・永代蔵 1」
(2)八種の木。すなわち,松・柏・竹・楡(ニレ)・桑・棗(ナツメ)・柘(ツゲ)・橘の称。はつぼく。
はち-まい [2] 【八枚】🔗⭐🔉
はち-まい [2] 【八枚】
紙・板など薄く平たいもの八つ。
はちまい-がた 【八枚肩】🔗⭐🔉
はちまい-がた 【八枚肩】
かご一丁に人夫が八人つき,交代でかつぐこと。また,そのかご。「乗り物やれ,参れと伝へて―/浄瑠璃・会稽山」
はちまい-かんばん [5] 【八枚看板】🔗⭐🔉
はちまい-かんばん [5] 【八枚看板】
主として京坂の歌舞伎劇場で,一座の主だった俳優八人の名を記して木戸前に掲げた看板。寛政(1789-1801)期には一〇枚,一二枚と増え,実態を失った。表八枚。表付(ヒヨウヅケ)。
はちまい-きしょう ―シヤウ [5] 【八枚起請】🔗⭐🔉
はちまい-きしょう ―シヤウ [5] 【八枚起請】
午王(ゴオウ)の印のある料紙八枚続きの起請文。起請の特に念入りなもの。
はち-まえ ―マヘ [0] 【鉢前】🔗⭐🔉
はち-まえ ―マヘ [0] 【鉢前】
茶庭で,手水鉢を置くために設けられた樹や石の構え。
はち-まき [2] 【鉢巻(き)】 (名)スル🔗⭐🔉
はち-まき [2] 【鉢巻(き)】 (名)スル
(1)額から耳の上を通って,頭を布などできつく巻くこと。また,その布。「手ぬぐいで―する」「ねじり―」
(2)土蔵造りで,防火のために軒下を特に厚く塗ること。また,その部分。
(3)武士などが,兜(カブト)の下の烏帽子(エボシ)がずれないように,その縁を布で巻いたこと。また,その布。
大辞林 ページ 152261。