複数辞典一括検索+![]()
![]()
はん [1] 【藩】🔗⭐🔉
はん [1] 【藩】
〔「かき」「かこい」,また,王室の守りとなるもの,の意〕
(1)江戸時代の大名の支配領域および支配機構の総称。
(2)1868年(明治1)維新政府が旧幕府領に府県を置いたのに対して,旧大名領を指していった称(藩の用語の公式使用の最初)。71年廃藩置県により廃止。
ハン [1] 【恨】🔗⭐🔉
ハン [1] 【恨】
〔朝鮮語〕
植民地時代の抑圧の中で,朝鮮の民衆の中に蓄積されてきた痛恨・悲哀・怒りなどの感情。
ハン [1]  khan
khan 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ハン [1]  khan
khan モンゴル・トルコ・ツングースなど北方遊牧民族の君主の称号。汗(カン)。可汗(カカン)。
モンゴル・トルコ・ツングースなど北方遊牧民族の君主の称号。汗(カン)。可汗(カカン)。
 khan
khan モンゴル・トルコ・ツングースなど北方遊牧民族の君主の称号。汗(カン)。可汗(カカン)。
モンゴル・トルコ・ツングースなど北方遊牧民族の君主の称号。汗(カン)。可汗(カカン)。
はん 【汎】 (接頭)🔗⭐🔉
はん 【汎】 (接頭)
〔英語の接頭辞 pan の音訳〕
名詞に付いて,広くそのすべてにわたるという意を表す。「―アジア主義」「―アメリカ会議」「―理論」
はん (接尾)🔗⭐🔉
はん (接尾)
〔「さん」の転〕
「さん」に同じ。主に関西地方で用いる。「おいえ―」「あんた―」「山田―」
ばん [0] 【晩】🔗⭐🔉
ばん [0] 【晩】
(1)日暮れ。夕方。
(2)夜。「―のうちに雨が降った」
(3)晩飯。夕食。「―のおかず」
ばん 【番】🔗⭐🔉
ばん 【番】
■一■ [1] (名)
(1)かわるがわる事を行う場合の順序。「今度は君の―だ」「―がまわってくる」「掃除の―に当たる」
(2)見張りをすること。番人。「店の―をする」
(3)順番によって行う勤め。当番。特に宿直のことをいう。「おのが―に当りて,いささかなる事もあらせじ/源氏(浮舟)」
(4)名詞の上に付いて複合語をつくり,常用のもの,あるいは粗末なものの意を表す。当番の人の用いる物の意からの転。「―茶」「―傘」
■二■ (接尾)
助数詞。
(1)順序・等級・番号などを表すのに用いる。「一―」「一丁目三―」
(2)勝負の数を表すのに用いる。「三―とも勝つ」「七十一―職人歌合」
(3)能狂言の曲数を表すのに用いる。「狂言をたてつづけに三―見る」
ばん [1] 【幡】🔗⭐🔉
ばん [1] 【幡】
〔仏〕 仏・菩薩の権威や力を示す荘厳具(シヨウゴング)として用いる旗の総称。
→幢(ドウ)
幡
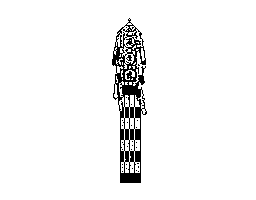 [図]
[図]
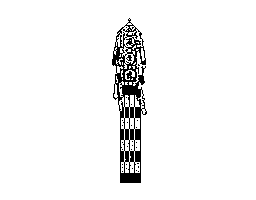 [図]
[図]
大辞林 ページ 152569。