複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひざ-ぐち [0] 【膝口】🔗⭐🔉
ひざ-ぐち [0] 【膝口】
膝の先。膝頭(ヒザガシラ)。
ひさくに 【久国】🔗⭐🔉
ひさくに 【久国】
(?-1226) 鎌倉初期の山城粟田口の刀工。藤次郎と称し,大隅権守を受領。国家の次男。兄国友とともに後鳥羽院御番鍛冶となり,山城国鍛冶の長者に任ぜられたと伝える。
ひざ-ぐみ [0][4] 【膝組み】🔗⭐🔉
ひざ-ぐみ [0][4] 【膝組み】
(1)あぐらをかくこと。
(2)膝をつき合わせて対座すること。「男と男が出あひて,―にて堪忍の成り難き時は/甲陽軍鑑(品一五)」
ひ-ざくら [2] 【緋桜】🔗⭐🔉
ひ-ざくら [2] 【緋桜】
バラ科の落葉高木。台湾や中国南部に自生し,暖地に栽植される。一〜三月,緋紅色の五弁花をつける。花弁は平開しない。緋寒桜。薩摩緋桜。
ひざ-ぐり [0] 【膝繰り】🔗⭐🔉
ひざ-ぐり [0] 【膝繰り】
「膝送り」に同じ。
ひざ-くりげ [3] 【膝栗毛】🔗⭐🔉
ひざ-くりげ [3] 【膝栗毛】
(1)〔膝を栗毛の馬の代用とする意から〕
徒歩で旅行すること。
(2)十返舎一九作の「東海道中膝栗毛」をはじめとする一連の作品の称。
びさく-るい [3] 【尾索類】🔗⭐🔉
びさく-るい [3] 【尾索類】
原索動物門の一綱を成す無脊椎動物の総称。ナメクジウオ類以外の原索動物。すべて海産。プランクトンとして魚類の天然飼料となるものもある。成体はゼラチン状の層におおわれる。ホヤ・サルパなどを含む。被嚢(ヒノウ)類。
ひざ-ぐるま [3] 【膝車】🔗⭐🔉
ひざ-ぐるま [3] 【膝車】
(1)ひざがしら。
(2)柔道の技の名。相手の一方の膝頭(ヒザガシラ)に自分の片足をあてて支えながら,相手の上体を引き寄せて投げる足技。
ひさげ [0] 【提子・提】🔗⭐🔉
ひさげ [0] 【提子・提】
〔動詞「提(ヒサ)ぐ」の連用形から〕
注ぎ口とつるのある銀・錫(スズ)製小鍋形の器。初め水・粥(カユ)・酒などを持ち運んだり温めたりしたが,のちにはもっぱら酒に用いた。かないろ。くわえ。
提子
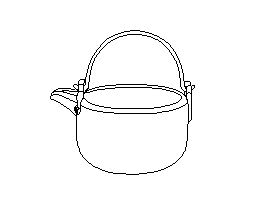 [図]
[図]
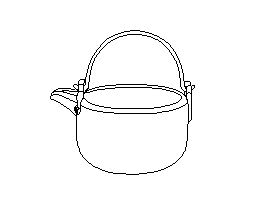 [図]
[図]
ひざ-げり [0] 【膝蹴り】🔗⭐🔉
ひざ-げり [0] 【膝蹴り】
(格闘技のわざで)ひざで相手を蹴ること。
ひさ・げる [0] 【提げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 ひさ・ぐ🔗⭐🔉
ひさ・げる [0] 【提げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 ひさ・ぐ
〔「引き下ぐ」の転の「ひっさぐ」が転じたもの〕
下げて持つ。携帯する。「下婢(ミズシメ)が,行灯(アンドン)―・げていでゆけば,後は一面暗(ヤミ)の幕/当世書生気質(逍遥)」
大辞林 ページ 152823。