複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひのくま-がわ ―ガハ 【檜隈川】🔗⭐🔉
ひのくま-がわ ―ガハ 【檜隈川】
奈良県高取町の高取山に発し,高市郡明日香村檜前(ヒノクマ)を北流する川。((歌枕))「ささのくま―に駒とめて/古今(神遊びの歌)」
ひのくま-じんぐう 【日前神宮】🔗⭐🔉
ひのくま-じんぐう 【日前神宮】
和歌山市秋月にある神社。祭神は日前大神。同一境内に国懸(クニカカス)神宮が並ぶ。
ビノグラードフ  Ivan Matveevich Vinogradov
Ivan Matveevich Vinogradov 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ビノグラードフ  Ivan Matveevich Vinogradov
Ivan Matveevich Vinogradov (1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。
(1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。
 Ivan Matveevich Vinogradov
Ivan Matveevich Vinogradov (1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。
(1891-1983) ソ連の数学者。整数論の研究者で,「十分に大きな奇数は三つの素数の和で表される」ことを証明,事実上「ゴールドバッハの第一予想」を解いたことで知られる。
ひ-の-くるま [1][0] 【火の車】🔗⭐🔉
ひ-の-くるま [1][0] 【火の車】
(1)〔仏〕「火車(カシヤ)」を訓読みした語。
(2)家計のきわめて苦しいこと。経済状態が非常に苦しいこと。「台所は―だ」
ひ-の-くれ [0] 【日の暮れ】🔗⭐🔉
ひ-の-くれ [0] 【日の暮れ】
太陽が沈んで暗くなる頃。夕暮れ。夕方。
ひ-の-け [1][0] 【火の気】🔗⭐🔉
ひ-の-け [1][0] 【火の気】
(1)火のある気配。火のあたたかみ。「―の全くない部屋」
(2)火事の元となるような火。火気(カキ)。「―のない所から出火した」
ひ-の-こ [1] 【火の粉】🔗⭐🔉
ひ-の-こ [1] 【火の粉】
火が燃える時に飛び散る小さな火。
ひ-の-ござ 【昼の御座】🔗⭐🔉
ひ-の-ござ 【昼の御座】
⇒ひのおまし(昼御座)
ひ-の-こし [1] 【火の輿】🔗⭐🔉
ひ-の-こし [1] 【火の輿】
葬儀のときに,火をともした小壺を置いて葬列に従う輿。
ひ-の-ころも [0] 【緋の衣】🔗⭐🔉
ひ-の-ころも [0] 【緋の衣】
(1)僧正の位にある者が着けた緋色の衣。
(2)僧がエビをいう隠語。
ひ-のし [3] 【火熨斗】🔗⭐🔉
ひ-のし [3] 【火熨斗】
布の皺(シワ)をのばしたり,襞(ヒダ)をつけたりするための底の滑らかな金属製の器具。内部に炭火を入れ,熱した底を布にあてて用いる。
火熨斗
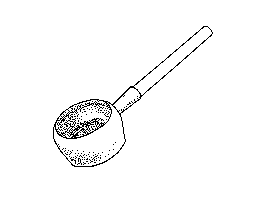 [図]
[図]
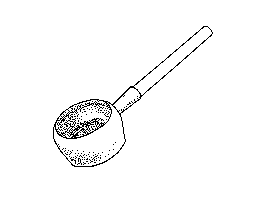 [図]
[図]
ひのし-ずり [0] 【火熨斗摺り】🔗⭐🔉
ひのし-ずり [0] 【火熨斗摺り】
火熨斗をかけそこなって布をだめにしてしまうこと。
ひ-の-した 【日の下】🔗⭐🔉
ひ-の-した 【日の下】
(1)あめのした。天下。世界。この世。「―に住し給ふ諸の神の/盛衰記 39」
(2)手紙などの日付の下。[ロドリゲス]
大辞林 ページ 153009。