複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひょうきん-もの ヘウ― [0] 【剽軽者】🔗⭐🔉
ひょうきん-もの ヘウ― [0] 【剽軽者】
ひょうきんな人。
びょう-きん ビヤウ― [0] 【病菌】🔗⭐🔉
びょう-きん ビヤウ― [0] 【病菌】
病原菌。
ひょう-ぐ ヒヤウ― [1] 【兵具】🔗⭐🔉
ひょう-ぐ ヒヤウ― [1] 【兵具】
甲冑(カツチユウ)・刀剣・弓矢など,戦いに用いる道具。武具。へいぐ。
ひょうぐ-ぐさり ヒヤウ― [4] 【兵具鎖・兵具 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
ひょうぐ-ぐさり ヒヤウ― [4] 【兵具鎖・兵具 】
長円形の鐶(カン)を二つ折りにしたものを連ねて作った鎖。金銅などで作る。ことに馬具や太刀に多く用いるため兵具鎖とよぶ。訛(ナマ)って兵庫鎖ともいったために兵庫寮の細工人が製作するものと誤解されるに至った。
兵具鎖
】
長円形の鐶(カン)を二つ折りにしたものを連ねて作った鎖。金銅などで作る。ことに馬具や太刀に多く用いるため兵具鎖とよぶ。訛(ナマ)って兵庫鎖ともいったために兵庫寮の細工人が製作するものと誤解されるに至った。
兵具鎖
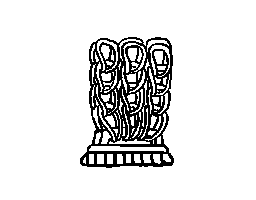 [図]
[図]
 】
長円形の鐶(カン)を二つ折りにしたものを連ねて作った鎖。金銅などで作る。ことに馬具や太刀に多く用いるため兵具鎖とよぶ。訛(ナマ)って兵庫鎖ともいったために兵庫寮の細工人が製作するものと誤解されるに至った。
兵具鎖
】
長円形の鐶(カン)を二つ折りにしたものを連ねて作った鎖。金銅などで作る。ことに馬具や太刀に多く用いるため兵具鎖とよぶ。訛(ナマ)って兵庫鎖ともいったために兵庫寮の細工人が製作するものと誤解されるに至った。
兵具鎖
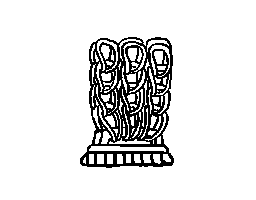 [図]
[図]
ひょうぐ-ぐさり-の-たち ヒヤウ― 【兵具鎖の太刀】🔗⭐🔉
ひょうぐ-ぐさり-の-たち ヒヤウ― 【兵具鎖の太刀】
帯執(オビトリ)に兵具鎖を用いた太刀。藤原時代から行われ,鞘(サヤ)を金銅・銀銅の板や透金物(スキカナモノ)で包み,覆輪をかけ,また彫金物を多用したものが多く,堅牢さと華麗さで兵仗(ヒヨウジヨウ)や奉納用として盛行したが,鎌倉中期以後威儀化して衰退した。
ひょう-ぐ ヘウ― [3][0] 【表具・ 具】🔗⭐🔉
具】🔗⭐🔉
ひょう-ぐ ヘウ― [3][0] 【表具・ 具】
布や紙をはって,巻物・掛物・屏風(ビヨウブ)・襖(フスマ)などに仕立てること。表装。背帖(ハイチヨウ)。
具】
布や紙をはって,巻物・掛物・屏風(ビヨウブ)・襖(フスマ)などに仕立てること。表装。背帖(ハイチヨウ)。
 具】
布や紙をはって,巻物・掛物・屏風(ビヨウブ)・襖(フスマ)などに仕立てること。表装。背帖(ハイチヨウ)。
具】
布や紙をはって,巻物・掛物・屏風(ビヨウブ)・襖(フスマ)などに仕立てること。表装。背帖(ハイチヨウ)。
ひょうぐ-し ヘウ― [3] 【表具師】🔗⭐🔉
ひょうぐ-し ヘウ― [3] 【表具師】
軸物や額を作ったり,襖(フスマ)や屏風(ビヨウブ)を仕立てたりすることを職業とする人。経師屋。
ひょうぐ-じ ヘウ―ヂ [3] 【表具地】🔗⭐🔉
ひょうぐ-じ ヘウ―ヂ [3] 【表具地】
表具用の生地。模様を織り出したものが多い。
ひょうぐ-や ヘウ― [0] 【表具屋】🔗⭐🔉
ひょうぐ-や ヘウ― [0] 【表具屋】
表具師。また,その店。経師屋。
ひょうぐ-や-ぶし ヘウ― 【表具屋節】🔗⭐🔉
ひょうぐ-や-ぶし ヘウ― 【表具屋節】
上方浄瑠璃の一。大坂の太夫表具屋又四郎が,貞享(1684-1688)・元禄(1688-1704)頃に語って流行したもの。
大辞林 ページ 153100。