複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひわず ヒハヅ 【繊弱】 (形動ナリ)🔗⭐🔉
ひわず ヒハヅ 【繊弱】 (形動ナリ)
弱々しいさま。ひよわなさま。「いと若う,―なり/源氏(竹河)」
ひ-わせいおん [3] 【非和声音】🔗⭐🔉
ひ-わせいおん [3] 【非和声音】
和音構成音(和声音)に属さず,旋律的な装飾と解釈される音の総称。和声外音。
ひ-わだ ―ハダ [0] 【檜皮】🔗⭐🔉
ひ-わだ ―ハダ [0] 【檜皮】
(1)檜(ヒノキ)の皮。ひはだ。
(2)「檜皮葺(ブ)き」の略。
(3)襲(カサネ)の色目の名。表は黒みの紅,裏は同色か薄い藍色,老人は白。中年以後に着用。
ひわだ-いろ ―ハダ― [0] 【檜皮色】🔗⭐🔉
ひわだ-いろ ―ハダ― [0] 【檜皮色】
(1)染め色の一。赤黄みの濃い茶色。
(2)経(タテ)浅葱(アサギ),緯(ヨコ)赤の織り色。
ひわだ-ぶき ―ハダ― [0] 【檜皮葺き】🔗⭐🔉
ひわだ-ぶき ―ハダ― [0] 【檜皮葺き】
檜(ヒノキ)の皮で屋根を葺くこと。また,その屋根。ひわだ。
ひわだ-や ―ハダ― [3] 【檜皮屋】🔗⭐🔉
ひわだ-や ―ハダ― [3] 【檜皮屋】
檜皮で葺(フ)いてある家。檜皮葺きの家。
ひ-わたり [2] 【火渡り】🔗⭐🔉
ひ-わたり [2] 【火渡り】
修験道の行者などが祈祷(キトウ)などの際に行う術の一つ。燃えている火の上を,呪文を唱えながらはだしで渡るもの。
ひわ-ちゃ ヒハ― [2] 【鶸茶】🔗⭐🔉
ひわ-ちゃ ヒハ― [2] 【鶸茶】
黄緑色がかった茶色。
びわ-ほうし ビハホフシ [3] 【琵琶法師】🔗⭐🔉
びわ-ほうし ビハホフシ [3] 【琵琶法師】
琵琶の弾き語りを職業とした僧体(法師姿)の盲人音楽家。平安時代から存在した放浪芸人の一種。中世以後は,経文読誦(ドクジユ)を表芸とする盲僧と,専ら平曲を演奏する者の二系統に分かれた。主に後者をさす。
琵琶法師
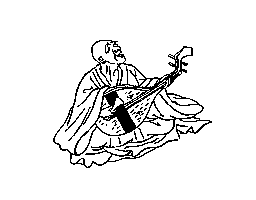 [図]
[図]
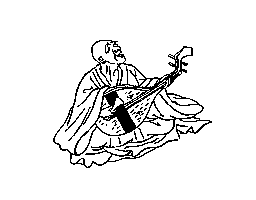 [図]
[図]
びわ-ます ビハ― [2] 【琵琶鱒】🔗⭐🔉
びわ-ます ビハ― [2] 【琵琶鱒】
サケ目の淡水魚。全長60センチメートルに達する。幼魚は体側に小判形の斑紋が並び朱点が散在するが,成長すると消失し,体色は銀白色となる。原産は琵琶湖とされるが,諏訪湖・芦 湖などにも分布。美味で釣りの対象魚。アメノウオ。アメ。
→アマゴ
湖などにも分布。美味で釣りの対象魚。アメノウオ。アメ。
→アマゴ
 湖などにも分布。美味で釣りの対象魚。アメノウオ。アメ。
→アマゴ
湖などにも分布。美味で釣りの対象魚。アメノウオ。アメ。
→アマゴ
ひわ-やか ヒハ― 【繊弱やか】 (形動ナリ)🔗⭐🔉
ひわ-やか ヒハ― 【繊弱やか】 (形動ナリ)
弱々しいさま。なよなよとして上品なさま。「宮いみじう―にめでたくて入らせ給ふ/栄花(音楽)」
大辞林 ページ 153210。