複数辞典一括検索+![]()
![]()
へび-とんぼ [3] 【蛇蜻蛉】🔗⭐🔉
へび-とんぼ [3] 【蛇蜻蛉】
脈翅目の昆虫。体長約4センチメートル。体形はややトンボに似る。幼虫は川底に生息し,孫太郎虫と呼ばれ,黒焼きにして子供の疳(カン)の薬とされる。九州以北の日本各地と東アジアに分布。
へび-の-きぬ [1]-[1] 【蛇の衣】🔗⭐🔉
へび-の-きぬ [1]-[1] 【蛇の衣】
脱皮した,蛇のぬけがら。蛇の殻(カラ)。[季]夏。《―傍にあり憩ひけり/虚子》
へび-の-ねござ [1] 【蛇寝御座】🔗⭐🔉
へび-の-ねござ [1] 【蛇寝御座】
オシダ科の夏緑性シダ植物。日本各地に分布。塊状の根茎から二回羽状複葉を叢生(ソウセイ)する。高さ20〜60センチメートル。胞子嚢(ホウシノウ)群は鈎(カギ)形または短い線形の包膜に包まれ,小羽片の中軸と葉縁との中間に並ぶ。カナヤマシダ。
蛇寝御座
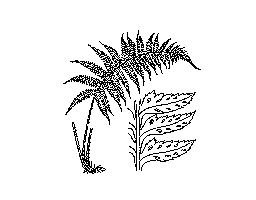 [図]
[図]
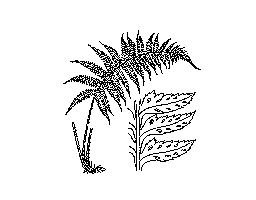 [図]
[図]
へび-のぼらず [3] 【蛇上らず】🔗⭐🔉
へび-のぼらず [3] 【蛇上らず】
メギ科の落葉低木。本州中部以西の山野に生える。高さ約60センチメートル。枝に鋭いとげがある。葉は狭卵形で,縁に細かいとげを密生。初夏,黄色の花をつけ,液果は赤く熟す。トリトマラズ。
へび-むこいり [3] 【蛇婿入り】🔗⭐🔉
へび-むこいり [3] 【蛇婿入り】
昔話の一。男性に身を変えた蛇が娘に求婚するもの。毎晩訪れてくる男の着物に針を通し,翌朝糸をたどって正体が蛇であることを知るという話の類。
へ-ひり [3] 【放屁】🔗⭐🔉
へ-ひり [3] 【放屁】
屁をひること。また,その人。
へひり-むし [3] 【放屁虫】🔗⭐🔉
へひり-むし [3] 【放屁虫】
触ると臭いにおいを出す昆虫,ミイデラゴミムシ・ホソクビゴミムシ・カメムシなどの俗称。へこきむし。へっぴりむし。[季]秋。
ヘファイストス  H
H phaistos
phaistos 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ヘファイストス  H
H phaistos
phaistos ギリシャ神話のオリンポス十二神の一。火と鍛冶の神。妻はアフロディテ。ローマ神話のウルカヌスと同一視される。ヘパイストス。
ギリシャ神話のオリンポス十二神の一。火と鍛冶の神。妻はアフロディテ。ローマ神話のウルカヌスと同一視される。ヘパイストス。
 H
H phaistos
phaistos ギリシャ神話のオリンポス十二神の一。火と鍛冶の神。妻はアフロディテ。ローマ神話のウルカヌスと同一視される。ヘパイストス。
ギリシャ神話のオリンポス十二神の一。火と鍛冶の神。妻はアフロディテ。ローマ神話のウルカヌスと同一視される。ヘパイストス。
ペプシン [1]  pepsin
pepsin 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ペプシン [1]  pepsin
pepsin タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)の一。脊椎動物の胃液中に前駆体ペプシノーゲンとして分泌され,塩酸または既存のペプシンの作用でペプシンに変わり,タンパク質を分解する。
タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)の一。脊椎動物の胃液中に前駆体ペプシノーゲンとして分泌され,塩酸または既存のペプシンの作用でペプシンに変わり,タンパク質を分解する。
 pepsin
pepsin タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)の一。脊椎動物の胃液中に前駆体ペプシノーゲンとして分泌され,塩酸または既存のペプシンの作用でペプシンに変わり,タンパク質を分解する。
タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)の一。脊椎動物の胃液中に前駆体ペプシノーゲンとして分泌され,塩酸または既存のペプシンの作用でペプシンに変わり,タンパク質を分解する。
大辞林 ページ 154036。