複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぼう-がん [0] 【帽岩】🔗⭐🔉
ぼう-がん [0] 【帽岩】
⇒キャップ-ロック
ほうかん-げきたく ハウクワン― [0] 【抱関撃柝】🔗⭐🔉
ほうかん-げきたく ハウクワン― [0] 【抱関撃柝】
門番と拍子木を打って夜警をする人。また,身分の低い小役人。
ほうかん-じ ホフクワン― 【法観寺】🔗⭐🔉
ほうかん-じ ホフクワン― 【法観寺】
京都市東山区八坂上町にある臨済宗建仁寺派の寺。山号,霊応山。聖徳太子の建立と伝える。五重の塔は1440年に再興。八坂寺。
ぼうかん-れい ボウクワン― [3] 【貿管令】🔗⭐🔉
ぼうかん-れい ボウクワン― [3] 【貿管令】
「輸出貿易管理令」の略。
ほうき ハウキ [0][1] 【箒・帚】 (名)スル🔗⭐🔉
ほうき ハウキ [0][1] 【箒・帚】 (名)スル
〔「ははき」の転〕
(1)塵(チリ)やごみを掃く道具。竹・草・棕梠(シユロ)などで作る。
(2)遊里で,次々に芸妓と関係すること。また,そのような男。浮気者。「―しちやあいやよ/おかめ笹(荷風)」「―客」
ほうき-がみ ハウキ― [3] 【箒神】🔗⭐🔉
ほうき-がみ ハウキ― [3] 【箒神】
産神(ウブガミ)のこと。出産の際に,安産を願って妊婦の枕元に箒を逆さに立てておいたり,箒で腹をなでたりすることがある。
ほうき-ぎ ハウキ― [3][0] 【箒木】🔗⭐🔉
ほうき-ぎ ハウキ― [3][0] 【箒木】
アカザ科の一年草。高さ約1メートル。多数枝分かれし,狭披針形の葉を密に互生。夏,葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。果実は小球形で,「とんぶり」と呼ばれ食用。茎は干して庭箒を作る。箒草。ハハキギ。
帚木
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ほうき-ぐさ ハウキ― [3] 【箒草】🔗⭐🔉
ほうき-ぐさ ハウキ― [3] 【箒草】
ホウキギの別名。ははきぐさ。[季]夏。
ほうき-ざや ハウキ― [3] 【箒鞘】🔗⭐🔉
ほうき-ざや ハウキ― [3] 【箒鞘】
〔草箒に似ているところから〕
毛皮で作った尻鞘。
ほうき-じり ハウキ― [0] 【箒尻】🔗⭐🔉
ほうき-じり ハウキ― [0] 【箒尻】
江戸時代,敲(タタキ)・拷問に用いた棒。割竹二本を麻苧(アサオ)で包み,上を観世こよりで巻き,持つ所に白革を巻いたもの。
ほうき-たけ ハウキ― [3] 【箒茸】🔗⭐🔉
ほうき-たけ ハウキ― [3] 【箒茸】
担子菌類ヒダナシタケ目のきのこ。秋,林内の地上に発生。高さ15センチメートル,径15センチメートルに達する。茎は白色で太い。よく分枝し先端は樹枝状となり,淡紅ないし淡紫色で美しい。食用。ネズミタケ。
箒茸
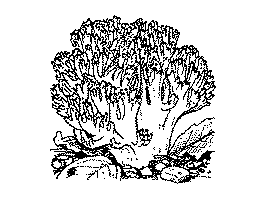 [図]
[図]
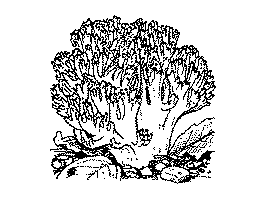 [図]
[図]
大辞林 ページ 154170。
 bow gun
bow gun