複数辞典一括検索+![]()
![]()
ほう-だて ハウ― [4] 【方立】🔗⭐🔉
ほう-だて ハウ― [4] 【方立】
〔「方立」は当て字か〕
(1)円柱や柱のない壁などに建具を取り付けるために立てる縦長の角材。柱寄(ハシラヨセ)。方立柱。ほおだて。
(2)牛車の前後の入り口の左右にある柱。
(3)箙(エビラ)の下方の箱の部分。頬立。
(4)高欄の端に突き出ている反り木。
方立(1)
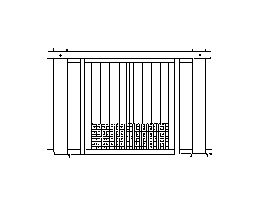 [図]
[図]
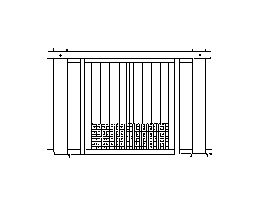 [図]
[図]
ほうだて-いた ハウ― [5] 【方立板】🔗⭐🔉
ほうだて-いた ハウ― [5] 【方立板】
(1)方立{(1)}に用いた板。
(2)箪笥や書棚などの側面の板。帆立(ホダテ)板。
ほうだて-ばしら ハウ― [5] 【方立柱】🔗⭐🔉
ほうだて-ばしら ハウ― [5] 【方立柱】
「方立{(1)}」に同じ。
ぼう-だま バウ― [0] 【棒球】🔗⭐🔉
ぼう-だま バウ― [0] 【棒球】
投手の投げた球で,威力のない直球。
ぼう-だら バウ― [0] 【棒鱈】🔗⭐🔉
ぼう-だら バウ― [0] 【棒鱈】
(1)真鱈を三枚におろし,素干しにしたもの。[季]春。
→干鱈(ヒダラ)
(2)酔っ払い。「わたくしが酒に酔ひまして―になりまするは/歌舞伎・吾嬬鑑」
(3)役立たず。ぼんくら。「おらがはうの―八が鼻のあなからは/滑稽本・膝栗毛 6」
ほう-たん ハウ― [3][0] 【放胆】 (名・形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
ほう-たん ハウ― [3][0] 【放胆】 (名・形動)[文]ナリ
あれこれと迷わずに思い切りよく大胆に事をなす・こと(さま)。「―な男」「―に振る舞う」
[派生] ――さ(名)
ほうたん-ぶん ハウ― [3] 【放胆文】🔗⭐🔉
ほうたん-ぶん ハウ― [3] 【放胆文】
漢文の文体の一。修辞・文法にこだわらず,思うところを自由に大胆に述べるもの。文章の修練のため初めに学ぶべきものとされる。
⇔小心文
ほうたん 【鳳潭】🔗⭐🔉
ほうたん 【鳳潭】
(1654-1738) 江戸中期の華厳宗の僧。鉄眼道光に禅を学ぶ。華厳宗中興の祖と呼ばれる。著「華厳五教章匡真鈔」など。
ほう-だん ハウ― [0] 【放談】 (名)スル🔗⭐🔉
ほう-だん ハウ― [0] 【放談】 (名)スル
言いたいことを自由に語ること。また,その談話。「時事―」
ほう-だん ホフ― [0] 【法談】🔗⭐🔉
ほう-だん ホフ― [0] 【法談】
仏法の教義や信仰のあり方を説いた話。説法。
大辞林 ページ 154243。