複数辞典一括検索+![]()
![]()
ほっ-しん [0][1] 【発心】 (名)スル🔗⭐🔉
ほっ-しん [0][1] 【発心】 (名)スル
(1)〔仏〕 菩提心を起こすこと。仏となり最高の悟りに達しようと決心すること。また,出家や遁世(トンセイ)をすること。発意。発起。発菩提心。
(2)思い立つこと。決心すること。発起。「―して仕事に励む」
ほっ-しん [0] 【発疹】🔗⭐🔉
ほっ-しん [0] 【発疹】
⇒はっしん(発疹)
ほっしん-チフス [5] 【発疹―】🔗⭐🔉
ほっしん-チフス [5] 【発疹―】
⇒はっしん(発疹)チフス
ほっしん-ねつ [3] 【発疹熱】🔗⭐🔉
ほっしん-ねつ [3] 【発疹熱】
リケッチアにより起こる軽い発疹チフスに似た症状をきたす病気。発熱と淡紅色から暗赤色に変わる発疹をみる。
ほっしんしゅう ―シフ 【発心集】🔗⭐🔉
ほっしんしゅう ―シフ 【発心集】
説話集。三巻本・五巻本・八巻本がある。鴨長明編。1215年頃までに成立か。発心談・遁世談・極楽往生談など仏教関係の説話が多く,後代への影響も大きい。長明発心集。
ほっ-しんのう ―シンワウ [3][5] 【法親王】🔗⭐🔉
ほっ-しんのう ―シンワウ [3][5] 【法親王】
⇒ほうしんのう(法親王)
ほっ-す [0] 【払子】🔗⭐🔉
ほっ-す [0] 【払子】
〔「ほっ」「す」共に唐音〕
もとインドで,虫や塵(チリ)を払うための具。獣毛や麻などを束ねて柄をつけたもの。後世,中国・日本で僧が説法などで威儀を正すために用いる法具。真宗以外の各派で用いる。
→麈尾(シユビ)
払子
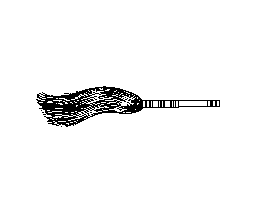 [図]
[図]
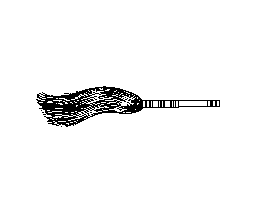 [図]
[図]
ほっす-がい ―ガヒ [3] 【払子貝】🔗⭐🔉
ほっす-がい ―ガヒ [3] 【払子貝】
海綿動物の一種。体はコップ状で高さ約12センチメートル。体の底部から長さ50センチメートルあまりのケイ質の柄が伸び,先端は海底の泥中に入る。相模湾や駿河湾の深海底に分布する。ウミホッス。
ほっ-す [0][1] 【法主】🔗⭐🔉
ほっ-す [0][1] 【法主】
〔「す」は呉音〕
「ほうしゅ(法主)」に同じ。
ほつ・す [2] 【解す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
ほつ・す [2] 【解す】 (動サ五[四])
「ほぐす(解)」に同じ。[ヘボン(三版)]
ほっ-すう [3] 【法数】🔗⭐🔉
ほっ-すう [3] 【法数】
仏教の教えを整理要約して,数を含む言葉で表現したもの。「四諦」「六波羅蜜」「十二因縁」など。ほうすう。
大辞林 ページ 154433。