複数辞典一括検索+![]()
![]()
ほん-ちゅう [1] 【本中】🔗⭐🔉
ほん-ちゅう [1] 【本中】
番付にのらない前相撲で,二連勝の白星(連勝して初めて一つの白星となる)二つをとった力士が進む地位。ここでさらに二連勝の白星二つをとると,新序と称して次の場所から番付の五段目にのる。
ほん-ちゅう [0] 【本注】🔗⭐🔉
ほん-ちゅう [0] 【本注】
平安時代に,明経(ミヨウギヨウ)家が用いた五経・論語・孝経の注釈。漢魏(ギ)の古注で,宋儒の新注と区別していう。
ほん-ちゅう [0] 【奔注】 (名)スル🔗⭐🔉
ほん-ちゅう [0] 【奔注】 (名)スル
水が勢いよく流れ注ぐこと。「道は宛然河の如く,濁流脚下に―して/義血侠血(鏡花)」
ポンチョ [1]  (スペイン) poncho
(スペイン) poncho 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ポンチョ [1]  (スペイン) poncho
(スペイン) poncho (1)中南米の男女の用いる外衣。四角形の布の真ん中に頭の通る穴をあけたもの。
(2){(1)}に形を似せて作った雨具。
ポンチョ(1)
(1)中南米の男女の用いる外衣。四角形の布の真ん中に頭の通る穴をあけたもの。
(2){(1)}に形を似せて作った雨具。
ポンチョ(1)
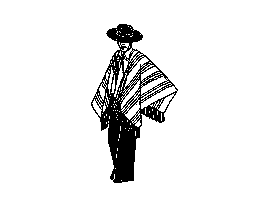 [図]
[図]
 (スペイン) poncho
(スペイン) poncho (1)中南米の男女の用いる外衣。四角形の布の真ん中に頭の通る穴をあけたもの。
(2){(1)}に形を似せて作った雨具。
ポンチョ(1)
(1)中南米の男女の用いる外衣。四角形の布の真ん中に頭の通る穴をあけたもの。
(2){(1)}に形を似せて作った雨具。
ポンチョ(1)
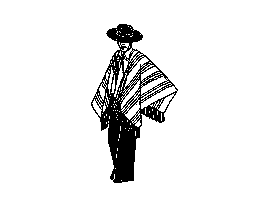 [図]
[図]
ほん-ちょう ―チヤウ 【本庁】🔗⭐🔉
ほん-ちょう ―チヤウ 【本庁】
(1) [0][1]
支庁その他出先機関などに対して中心となる庁。中央官庁。
(2) [1]
この庁。
ほん-ちょう ―テウ [1] 【本朝】🔗⭐🔉
ほん-ちょう ―テウ [1] 【本朝】
我が国の朝廷。また,我が国。国朝。
⇔異朝
ぼんちょう ボンテウ 【凡兆】🔗⭐🔉
ぼんちょう ボンテウ 【凡兆】
(?-1714) 江戸前・中期の俳人。金沢の生まれ。野沢氏または宮城氏・宮部氏・越野氏とも。別号,加生。京都で医を業とする。芭蕉の門人で,去来と「猿蓑」を共編。のち,芭蕉から離れた。作風は印象鮮明。
ほんちょうおういんひじ ホンテウアウインヒジ 【本朝桜陰比事】🔗⭐🔉
ほんちょうおういんひじ ホンテウアウインヒジ 【本朝桜陰比事】
〔書名は宋の「棠陰(トウイン)比事」のもじり〕
浮世草子。五巻。井原西鶴作。1689年刊。名判官の裁決を題材とした四四の短編を集めたもの。
ほんちょうぐんきこう ホンテウグンキカウ 【本朝軍器考】🔗⭐🔉
ほんちょうぐんきこう ホンテウグンキカウ 【本朝軍器考】
武器考証書。一二巻。新井白石著。1736年刊。古代から近世に至る武器の沿革を弓矢・甲冑など一二類一五一条に部類して考証を加える。
ほんちょうげつれい ホンテウ― 【本朝月令】🔗⭐🔉
ほんちょうげつれい ホンテウ― 【本朝月令】
〔「ほんちょうがつりょう」とも〕
有職書。惟宗(コレムネ)公方著というが未詳。平安時代の朝廷の各月ごとの年中行事について,その旧事・由来を説いたもの。四〜六月分一巻が残存。もと四巻あるいは六巻か。
大辞林 ページ 154565。