複数辞典一括検索+![]()
![]()
みぞ-しだ [2][3] 【溝羊歯】🔗⭐🔉
みぞ-しだ [2][3] 【溝羊歯】
オシダ科の夏緑性シダ植物。山野の湿地に生える。高さ約60センチメートル。葉は羽状複葉で,羽片はとがる。胞子嚢(ノウ)群は葉脈に沿ってつく。
ミソジニー [3]  misogyny
misogyny 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ミソジニー [3]  misogyny
misogyny 女嫌い。
女嫌い。
 misogyny
misogyny 女嫌い。
女嫌い。
みそ-しる [3] 【味噌汁】🔗⭐🔉
みそ-しる [3] 【味噌汁】
だし汁に味噌を溶かし込んで味をつけた汁。野菜・豆腐などの実を入れて作る。おみおつけ。おつけ。
みそ-すり [4] 【味噌擂り】🔗⭐🔉
みそ-すり [4] 【味噌擂り】
(1)味噌を擂り鉢ですること。
(2)へつらうこと。また,その人。ごますり。
(3)「味噌擂り坊主」の略。
みそすり-ぼうず ―バウ― [5] 【味噌擂り坊主】🔗⭐🔉
みそすり-ぼうず ―バウ― [5] 【味噌擂り坊主】
(1)寺院で,炊事など下働きをする僧。
(2)僧をののしっていう語。
みぞ-そば [0] 【溝蕎麦】🔗⭐🔉
みぞ-そば [0] 【溝蕎麦】
タデ科の一年草。田の畔(アゼ)や小川の岸などに生える。高さ約40センチメートル。茎は下向きのとげがあり,ほこ形の葉を互生。夏から秋,枝先に淡紅色の小花を球状につける。ウシノヒタイ。[季]秋。
溝蕎麦
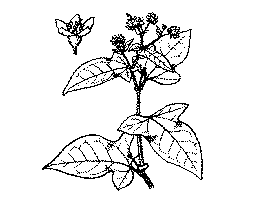 [図]
[図]
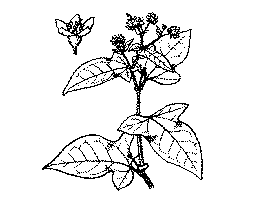 [図]
[図]
みそ-だま [0] 【味噌玉】🔗⭐🔉
みそ-だま [0] 【味噌玉】
(1)「玉味噌」に同じ。
(2)つまらぬ者をののしっていう語。「こりや,そな―奴よ/歌舞伎・幼稚子敵討」
みそっ-かす [4] 【味噌っ滓】🔗⭐🔉
みそっ-かす [4] 【味噌っ滓】
〔「みそかす」の転〕
(1)味噌をこした滓。価値のないものにたとえられる。
(2)子供の遊びなどで,一人前にみなされない子供。みそ。
みそ-つき [2] 【味噌搗き】🔗⭐🔉
みそ-つき [2] 【味噌搗き】
味噌を作るために,よく煮た大豆をつくこと。味噌豆をつくこと。[季]冬。
みそ-づけ [0] 【味噌漬(け)】🔗⭐🔉
みそ-づけ [0] 【味噌漬(け)】
味噌に肉・魚・野菜などを漬けること。また,漬けたもの。
みそっ-ぱ [2] 【味噌っ歯】🔗⭐🔉
みそっ-ぱ [2] 【味噌っ歯】
欠けて黒っぽくなった歯。子供に多い。
みそな・う ミソナフ 【見行ふ】 (動ハ四)🔗⭐🔉
みそな・う ミソナフ 【見行ふ】 (動ハ四)
「みそなわす」に同じ。「神も仏も我を―・へ/新古今(釈教)」
みそ-なおし ―ナホシ [3] 【味噌直】🔗⭐🔉
みそ-なおし ―ナホシ [3] 【味噌直】
マメ科の草本状の低木。山野に自生。葉は三出複葉で,小葉は狭長楕円形。八,九月,白色の小花を総状花序につける。古くは,いたんだ味噌に茎葉を入れて味を良くし,また,わいた蛆(ウジ)を殺すのに用いた。味噌草。蛆草(ウジクサ)。漢名,小槐花。
大辞林 ページ 155067。