複数辞典一括検索+![]()
![]()
むく-どり [2] 【椋鳥】🔗⭐🔉
むく-どり [2] 【椋鳥】
(1)スズメ目ムクドリ科の鳥の総称。旧世界に約一一〇種が知られる。
(2){(1)}の一種。全長25センチメートル内外。黒褐色で顔と腰が白く,くちばしと脚は橙黄色。平野部に多く,数千羽もの群れをなすことが多い。昆虫や果実を食べる。巣箱をよく利用し,都会地にも多い。アジア北東部に分布し,日本各地でも繁殖。ハクトウオウ。ムク。[季]秋。
(3)田舎から都へ来た者をあざけっていう語。「―も毎年来ると江戸雀/柳多留 73」
椋鳥(2)
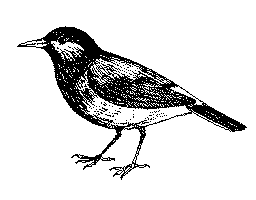 [図]
[図]
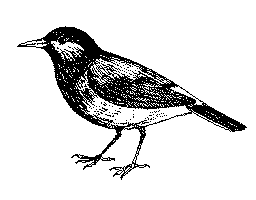 [図]
[図]
むく-の-き [1] 【椋木・樸樹】🔗⭐🔉
むく-の-き [1] 【椋木・樸樹】
ニレ科の落葉高木。高さ20メートルに達し,老木の樹皮ははがれやすい。山地に生え,庭木ともする。葉は卵形で先はとがり,表面はざらつく。雌雄同株で,五月頃開花。果実は径約1センチメートルの卵球形で黒熟し,甘くて食べられる。葉は細工物を磨くのに用い,材は床柱・器具などとする。ムク。ムクエノキ。
椋木
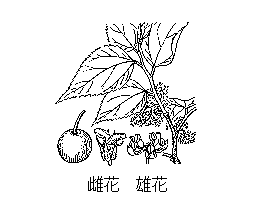 [図]
[図]
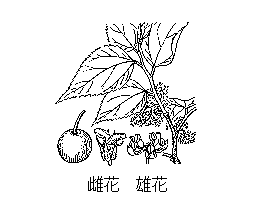 [図]
[図]
むくはら-でら 【向原寺】🔗⭐🔉
むくはら-でら 【向原寺】
奈良県明日香村豊浦(トユラ)にあった日本最初の寺。552年,蘇我稲目(ソガノイナメ)が百済(クダラ)王から献じられた仏像・経論を小墾田(オハリダ)の家に安置し,のち向原の家に移して寺としたという。推古朝期(592-628)には豊浦に移り,豊浦寺と称した。現在その跡地に浄土真宗の向原(コウゲン)寺(広厳寺とも)がある。小墾田寺。豊浦寺。建興寺。桜井寺。
むくみ [3][0] 【浮腫】🔗⭐🔉
むくみ [3][0] 【浮腫】
むくむこと。また,むくんだもの。ふしゅ。「足に―がくる」「―がとれる」
むく・む [2][0] 【浮腫む】 (動マ五[四])🔗⭐🔉
むく・む [2][0] 【浮腫む】 (動マ五[四])
水気などがたまって,体の一部あるいは全体がはれてふくれる。「脚気で足が―・む」「寝過ぎで―・んだ顔」
大辞林 ページ 155293。