複数辞典一括検索+![]()
![]()
めがね-ごし [0] 【眼鏡越し】🔗⭐🔉
めがね-ごし [0] 【眼鏡越し】
(1)上目(ウワメ)遣いに,眼鏡の上から見ること。「―に見つめる」
(2)眼鏡を通して見ること。
めがね-ざる [4] 【眼鏡猿】🔗⭐🔉
めがね-ざる [4] 【眼鏡猿】
霊長目メガネザル科に属する哺乳類の総称。原猿類の一種。小形で,頭胴長10〜15センチメートル。尾長約20センチメートル。体は淡黄色あるいは灰褐色から暗褐色。目は大きく,夜行性で樹上にすむ。昆虫・トカゲなどを食べる。フィリピン・スラウェシ・カリマンタン・スマトラなどに分布。三種に分かれる。
眼鏡猿
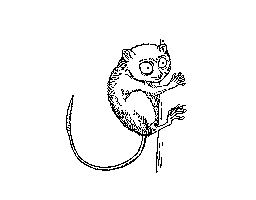 [図]
[図]
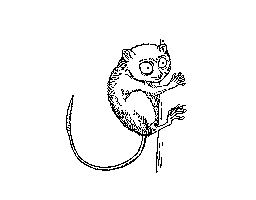 [図]
[図]
めがね-ちがい ―チガヒ [4] 【眼鏡違い】🔗⭐🔉
めがね-ちがい ―チガヒ [4] 【眼鏡違い】
人物や物のよしあしの判断を誤ること。
めがね-ばし [3] 【眼鏡橋】🔗⭐🔉
めがね-ばし [3] 【眼鏡橋】
石造りのアーチ橋の通称。江戸時代に中国から伝えられ,長崎を中心に九州各地に造られた。
眼鏡橋
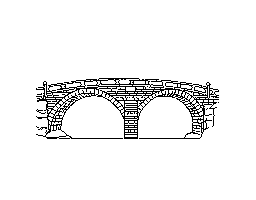 [図]
[図]
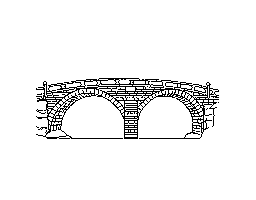 [図]
[図]
めがね-へび [4] 【眼鏡蛇】🔗⭐🔉
めがね-へび [4] 【眼鏡蛇】
コブラの代表種。有毒蛇。敵を威嚇するとき,前半身を立てて首近くの肋骨を広げ,体を大きく見せる。また,背の黄色の斑紋が大きな目のようになる。インドに分布。
メガネウラ [3]  (ラテン) Meganeura
(ラテン) Meganeura 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
メガネウラ [3]  (ラテン) Meganeura
(ラテン) Meganeura 古生代石炭紀に栄えたトンボに近縁の化石昆虫。史上最大の昆虫といわれ,はねを広げると65センチメートルに達した。
古生代石炭紀に栄えたトンボに近縁の化石昆虫。史上最大の昆虫といわれ,はねを広げると65センチメートルに達した。
 (ラテン) Meganeura
(ラテン) Meganeura 古生代石炭紀に栄えたトンボに近縁の化石昆虫。史上最大の昆虫といわれ,はねを広げると65センチメートルに達した。
古生代石炭紀に栄えたトンボに近縁の化石昆虫。史上最大の昆虫といわれ,はねを広げると65センチメートルに達した。
め-かぶ [1] 【和布蕪】🔗⭐🔉
め-かぶ [1] 【和布蕪】
「めかぶら(和布蕪){(1)}」に同じ。
め-かぶ [1] 【雌株】🔗⭐🔉
め-かぶ [1] 【雌株】
雌雄異株の植物で,雌花だけをつける株。
⇔雄株
め-かぶら [2] 【和布蕪】🔗⭐🔉
め-かぶら [2] 【和布蕪】
(1)ワカメの茎の両縁にできるひだ状の成実葉。歯ごたえがあり,ぬめりが強い。めかぶ。
(2)的矢の矢じりの一種。{(1)}を乾かし固めて作ったもの。
大辞林 ページ 155479。