複数辞典一括検索+![]()
![]()
もろ-がけ [0] 【諸駆け】🔗⭐🔉
もろ-がけ [0] 【諸駆け】
いっしょに駆けること。
もろ-かざり [3] 【諸飾り】🔗⭐🔉
もろ-かざり [3] 【諸飾り】
(1)道具を書院や座敷に飾る一方式。三幅一対の掛物の前に卓(シヨク)を据え,その上に花瓶と燭台を一対ずつ置き合わせる。
(2)茶室の床飾りで,初座に掛物と花入を同時に飾ること。
もろ-かずら ―カヅラ [3] 【諸葛・諸鬘】🔗⭐🔉
もろ-かずら ―カヅラ [3] 【諸葛・諸鬘】
(1)フタバアオイの異名。「あしびきの山に生ふてふ―/後撰(恋二)」
(2)髪飾りにする桂(カツラ)と葵(アオイ)の二つ。賀茂祭のとき頭にさした。「―落葉を何に拾ひけむ名はむつましき挿頭(カザシ)なれども/源氏(若菜下)」
もろ-がみ [2][0] 【諸神】🔗⭐🔉
もろ-がみ [2][0] 【諸神】
多くの神。しょしん。
もろき-ふね 【同船】🔗⭐🔉
もろき-ふね 【同船】
〔諸木船の意〕
多くの木材を合わせて造った船。合木船。「大舶(ツム)と―と三艘(ミツ)を賜ふ/日本書紀(皇極訓注)」
もろ-きゅう ―キウ [2]🔗⭐🔉
もろ-きゅう ―キウ [2]
キュウリにもろみを添えて食すもの。
もろ-ぐそく [3] 【諸具足】🔗⭐🔉
もろ-ぐそく [3] 【諸具足】
戦いに出るため,太刀を身に帯び,靫(ユギ)を背につけて矢を入れ,弓を持った装束。また,籠手(コテ)・臑当(スネアテ)および腹当をつけた装束にもいう。
もろ-くち 【諸口】🔗⭐🔉
もろ-くち 【諸口】
(1)多くの人の意見。「下の―と申す事は,えいなび給はぬ事なり/宇津保(国譲中)」
(2)馬を引くのに,二人以上で両側の手綱を取ること。
⇔片口
「或は乗り口にひかせ,或は―にひかせ/平家 9」
もろく-も [1] 【脆くも】 (副)🔗⭐🔉
もろく-も [1] 【脆くも】 (副)
簡単に。あっけなく。「―初戦で敗退した」
もろ-こ [0] 【諸子】🔗⭐🔉
もろ-こ [0] 【諸子】
(1)コイ目コイ科モロコ属やイトモロコ属などの淡水魚の総称。全長8〜12センチメートル。タモロコ・ヒナモロコ・カワバタモロコ・デメモロコなど七種がいる。
(2){(1)}の一種。全長12センチメートルほど。体は細く長い紡錘形でやや側扁し,一対の口ひげをもつ。体色は背面が暗緑褐色,体側・腹面は黄みをおびた銀白色で,側線に沿ってやや太い暗色の帯がはしる。照り焼きやモロコ鮨(ズシ)などにして食べる。琵琶湖特産であったが,各地で繁殖している。ホンモロコ。[季]春。
(3)クエの老成魚の異名。
諸子(2)
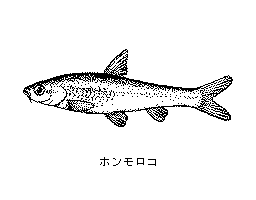 [図]
[図]
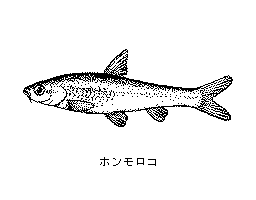 [図]
[図]
大辞林 ページ 155774。