複数辞典一括検索+![]()
![]()
よつ-がな [0] 【四つ仮名】🔗⭐🔉
よつ-がな [0] 【四つ仮名】
「じ」「ぢ」「ず」「づ」の四つの仮名,および,その仮名で表される音をいう語。古くは,「じ」と「ぢ」,「ず」と「づ」は,それぞれ異なる音(「じ」「ず」は摩擦音の [ i][zu],「ぢ」「づ」は破裂音の [di][du])で発音されたが,室町末期になると「ぢ」「づ」が破擦音化して [d
i][zu],「ぢ」「づ」は破裂音の [di][du])で発音されたが,室町末期になると「ぢ」「づ」が破擦音化して [d i][dzu] となり,以後「じ」「ず」との混乱がみられるようになり,一七世紀末には現代と同じようになった。このために,「じ」と「ぢ」,「ず」と「づ」の間には,それぞれ仮名遣いの上でも,その使い方が大きな問題になった。
→蜆縮涼鼓集(ケンシユクリヨウコシユウ)
i][dzu] となり,以後「じ」「ず」との混乱がみられるようになり,一七世紀末には現代と同じようになった。このために,「じ」と「ぢ」,「ず」と「づ」の間には,それぞれ仮名遣いの上でも,その使い方が大きな問題になった。
→蜆縮涼鼓集(ケンシユクリヨウコシユウ)
 i][zu],「ぢ」「づ」は破裂音の [di][du])で発音されたが,室町末期になると「ぢ」「づ」が破擦音化して [d
i][zu],「ぢ」「づ」は破裂音の [di][du])で発音されたが,室町末期になると「ぢ」「づ」が破擦音化して [d i][dzu] となり,以後「じ」「ず」との混乱がみられるようになり,一七世紀末には現代と同じようになった。このために,「じ」と「ぢ」,「ず」と「づ」の間には,それぞれ仮名遣いの上でも,その使い方が大きな問題になった。
→蜆縮涼鼓集(ケンシユクリヨウコシユウ)
i][dzu] となり,以後「じ」「ず」との混乱がみられるようになり,一七世紀末には現代と同じようになった。このために,「じ」と「ぢ」,「ず」と「づ」の間には,それぞれ仮名遣いの上でも,その使い方が大きな問題になった。
→蜆縮涼鼓集(ケンシユクリヨウコシユウ)
よ-づかわ・し ―ヅカハシ 【世付かはし】 (形シク)🔗⭐🔉
よ-づかわ・し ―ヅカハシ 【世付かはし】 (形シク)
〔動詞「世付く」の形容詞化〕
男女の情を理解しているようすである。「―・しう,かるがるしき御名の立ち給ふべきを/源氏(夕霧)」
よつ-かわり ―カハリ [3] 【四つ変(わ)り】🔗⭐🔉
よつ-かわり ―カハリ [3] 【四つ変(わ)り】
(1)和服で,身頃の右半分・左半分と袖をそれぞれ別の布で仕立てること。また,その着物。「―の大ふり袖/浮世草子・一代男 5」
(2)四色の段染め。「吉弥笠に―のくけ紐を付て/浮世草子・五人女 3」
四つ変わり(1)
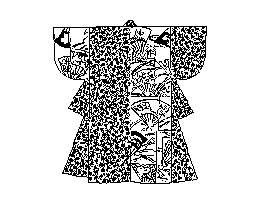 [図]
[図]
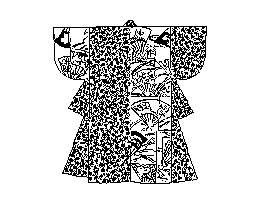 [図]
[図]
よ-つぎ [0][3] 【世継(ぎ)・世嗣】🔗⭐🔉
よ-つぎ [0][3] 【世継(ぎ)・世嗣】
(1)家督を相続すること。また,その人。
(2)統治者としての天皇の位を継ぐこと。
(3)歴代の天皇の事蹟を代々語り伝えること。また,伝える人。「―の翁の物語/徒然 6」
(4)歴代の天皇の事蹟を仮名で書き記した歴史書。「栄花物語」「大鏡」など。
よつぎ-ものがたり 【世継物語】🔗⭐🔉
よつぎ-ものがたり 【世継物語】
(1)「栄花物語」の別名。
(2)「大鏡」の別名。
(3)説話集。一巻。編者未詳。鎌倉時代成立。平安時代から鎌倉時代にかけての和歌説話を中心に五六話を収める。
よっ-きゃく ヨク― [0] 【浴客】🔗⭐🔉
よっ-きゃく ヨク― [0] 【浴客】
風呂屋・温泉に来る客。よっかく。
大辞林 ページ 156397。