複数辞典一括検索+![]()
![]()
かや【茅・萱】🔗⭐🔉
かや [1] 【茅・萱】
屋根を葺(フ)く丈の高い草の総称。イネ科植物のススキ・ヨシ・チガヤ・カルカヤ・カヤツリグサ科植物のスゲなど。[季]秋。
茅
 [図]
[図]
 [図]
[図]
かや【榧】🔗⭐🔉
かや [1] 【榧】
イチイ科の常緑針葉樹。山地に自生し,また庭木として栽植。高さ約20メートルに達する。葉は広線形で二列につく。四,五月頃に開花し,翌年の秋,楕円形で紫褐色に熟する種子をつける。材は碁盤などとし,種子は油をとるほか食用にする。
〔「榧の実」は [季]秋〕
かや【蚊帳・蚊屋】🔗⭐🔉
かや [0] 【蚊帳・蚊屋】
蚊を防ぐために寝床を覆う寝具。目の粗い麻・木綿などの布で作り,四隅をつって覆う。かちょう。「―を吊(ツ)る」[季]夏。《起きて見つ寝て見つ―の広さかな/浮橋》
蚊帳
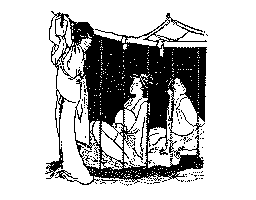 [図]
[図]
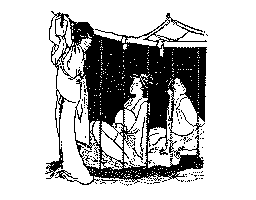 [図]
[図]
かや【加舎】🔗⭐🔉
かや 【加舎】
姓氏の一。
かや-しらお【加舎白雄】🔗⭐🔉
かや-しらお ―シラヲ 【加舎白雄】
(1738-1791) 江戸中期の俳人。名は吉春。烏明・烏酔に師事。江戸に春秋庵を構え,諸国を遊歴。すぐれた門下生が多い。平明温雅な作風。著「面影集」「加佐里那止」「春秋稿」「寂栞」など。
かや【加悦】🔗⭐🔉
かや 【加悦】
京都府北西部,与謝(ヨサ)郡の町。大江山の北西麓にあり,丹後縮緬の産地。
かや【伽耶・伽 ・加耶】🔗⭐🔉
・加耶】🔗⭐🔉
かや 【伽耶・伽 ・加耶】
⇒加羅(カラ)
・加耶】
⇒加羅(カラ)
 ・加耶】
⇒加羅(カラ)
・加耶】
⇒加羅(カラ)
かや【賀陽】🔗⭐🔉
かや 【賀陽】
姓氏の一。
かや-の-とよとし【賀陽豊年】🔗⭐🔉
かや-の-とよとし 【賀陽豊年】
(751-815) 平安初期の漢学者。東宮学士・式部大輔・播磨守などを歴任。経史に通じ,また「凌雲集」の撰進に参画した。
か-や🔗⭐🔉
か-や (連語)
□一□〔詠嘆の終助詞「か」に間投助詞「や」の付いたもの。上代語〕
感動・詠嘆の意を表す。…ことだなあ。「うれたき―,大丈夫(マスラオ)にして/日本書紀(神武訓注)」
□二□〔係助詞「か」に間投助詞「や」の付いたもの〕
(1)(多く「とかや」の形で)不確実な伝聞または不定の意を表す。「落ちぐりと―何と―,昔の人のめでたうしける袷の袴一具/源氏(行幸)」「遠き物を宝とせずとも,また,得がたき貨(タカラ)を貴(トウト)まずとも,文(フミ)にも侍ると―/徒然 120」
(2)感動を込めて,疑問の意を表す。「世にかかる美しき姫君も有る―/御伽草子・のせ猿」
(3)反語の意を表す。「時の間もながらふべき我が身―。とても思ひに堪へかねば,生きてあるべき命ならず/太平記 11」
かや-いん【紙屋院】🔗⭐🔉
かや-いん ― ン 【紙屋院】
⇒かみやいん(紙屋院)
ン 【紙屋院】
⇒かみやいん(紙屋院)
 ン 【紙屋院】
⇒かみやいん(紙屋院)
ン 【紙屋院】
⇒かみやいん(紙屋院)
かや-おい【茅負】🔗⭐🔉
かや-おい ―オヒ [2][0][3] 【茅負】
建築で軒先の垂木(タルキ)の先端部の上,裏甲(ウラゴウ)との間に渡した横材。
かや-かや🔗⭐🔉
かや-かや (副)
(多く「と」を伴って)
(1)「がやがや」に同じ。「御随身ども―と言ふを制し給ひて/源氏(宿木)」
(2)声高に笑うさま。「よよと泣いたり,―と笑つたり/滑稽本・八笑人」
かや-きり【茅螽 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
かや-きり [3][2] 【茅螽 】
キリギリスの一種。体長約50ミリメートル。体は太く頭頂がとがる。緑色ないし褐色で,背に白線が二本ある。成虫は夏出現し,雄は強い連続音で鳴く。
】
キリギリスの一種。体長約50ミリメートル。体は太く頭頂がとがる。緑色ないし褐色で,背に白線が二本ある。成虫は夏出現し,雄は強い連続音で鳴く。
 】
キリギリスの一種。体長約50ミリメートル。体は太く頭頂がとがる。緑色ないし褐色で,背に白線が二本ある。成虫は夏出現し,雄は強い連続音で鳴く。
】
キリギリスの一種。体長約50ミリメートル。体は太く頭頂がとがる。緑色ないし褐色で,背に白線が二本ある。成虫は夏出現し,雄は強い連続音で鳴く。
かや-きん【伽 琴】🔗⭐🔉
琴】🔗⭐🔉
かや-きん [2] 【伽 琴】
朝鮮の撥弦(ハツゲン)楽器の一。一二弦の箏(ソウ)。奈良時代に日本にも伝わった。新羅琴(シラギゴト)。
→伽
琴】
朝鮮の撥弦(ハツゲン)楽器の一。一二弦の箏(ソウ)。奈良時代に日本にも伝わった。新羅琴(シラギゴト)。
→伽 琴[音声] 琴[音声]">
琴[音声] 琴[音声]">
 琴】
朝鮮の撥弦(ハツゲン)楽器の一。一二弦の箏(ソウ)。奈良時代に日本にも伝わった。新羅琴(シラギゴト)。
→伽
琴】
朝鮮の撥弦(ハツゲン)楽器の一。一二弦の箏(ソウ)。奈良時代に日本にも伝わった。新羅琴(シラギゴト)。
→伽 琴[音声] 琴[音声]">
琴[音声] 琴[音声]">か-やく【火薬】🔗⭐🔉
か-やく クワ― [0] 【火薬】
衝撃・点火などによって瞬間的に燃焼または分解反応を起こして多量の熱と気体を生じ,破壊・推進などの作用を行う物質。狭義には発射薬・推進薬を指し,広義には一般に爆発に伴って発生するエネルギーを有効に利用し得る爆発性物質を指す。後者は火薬類と呼ばれ,火薬類取締法では,火薬・爆薬・火工品に分けられる。黒色火薬のような混合火薬と,ニトログリセリンのような化合火薬とがあり,用途によって炸薬(サクヤク)・爆破薬・発射薬・起爆薬に分けられる。
かやく-こ【火薬庫】🔗⭐🔉
かやく-こ クワ― [3] 【火薬庫】
(1)火薬類を保管しておく倉庫。
(2)大事件・大変事を引き起こす危険性をはらんでいる所。
かやく-るい-とりしまりほう【火薬類取締法】🔗⭐🔉
かやく-るい-とりしまりほう クワ―ハフ 【火薬類取締法】
火薬類の製造・販売を許可制とし,貯蔵・運搬・消費その他の取り扱いについて,災害の防止,公共の安全の確保の見地から規制した法律。1950年(昭和25)制定。
か-やく【加役】🔗⭐🔉
か-やく [0] 【加役】
(1)本職以外の役を臨時に勤めること。また,その人。
(2)歌舞伎で,自分の持ち役以外の役を演じること。立役(タチヤク)が女形や老け役を受けもったりすること。また,そうした時に受ける特別手当。
(3)江戸時代の火付盗賊改(ヒツケトウゾクアラタメ)の称。
か-やく【加薬】🔗⭐🔉
か-やく [0] 【加薬】
(1)香辛料として料理に添えるもの。やくみ。
(2)漢方で,主薬に少量の補助の薬を加えること,またその薬。
(3)関西で,五目飯などに入れる肉や野菜。具(グ)。かやくもの。
かやく-うどん【加薬饂飩】🔗⭐🔉
かやく-うどん [4] 【加薬饂飩】
関西で,かまぼこ・松茸・のりなど種々の具をいれたうどん。
かやく-めし【加薬飯】🔗⭐🔉
かやく-めし [3][0] 【加薬飯】
関西で,魚・肉・野菜などを炊き込んだり,味付けして混ぜたりした飯をいう。かやくごはん。五目飯。
か-やく【課役】🔗⭐🔉
か-やく クワ― [0] 【課役】
(1)仕事を割りあてること。また割りあてられた仕事。
(2)律令制下,国家が人民に課した調・庸(ヨウ)・雑徭(ゾウヨウ)の総称。
(3)中世・近世,租税一般の呼称。かえき。
かや-くぐり【茅潜】🔗⭐🔉
かや-くぐり [3] 【茅潜】
スズメ目イワヒバリ科の小鳥。全長約14センチメートルほど。背面は赤褐色に黒褐色の縦斑,腹面はねずみ色の地味な鳥。日本特産種。昆虫・種子を食べる。高山のハイマツ帯で繁殖し,冬は本州以南の平地に移る。
かや-さん【伽 山】🔗⭐🔉
山】🔗⭐🔉
かや-さん 【伽 山】
韓国南部,大邱の北西68キロメートルにある山。海抜1430メートル。山中に海印寺がある。カヤ-サン。
山】
韓国南部,大邱の北西68キロメートルにある山。海抜1430メートル。山中に海印寺がある。カヤ-サン。
 山】
韓国南部,大邱の北西68キロメートルにある山。海抜1430メートル。山中に海印寺がある。カヤ-サン。
山】
韓国南部,大邱の北西68キロメートルにある山。海抜1430メートル。山中に海印寺がある。カヤ-サン。
かや・す【返す】🔗⭐🔉
かや・す 【返す】 (動サ四)
「かえす(返)」の転。「返(カエ)すものを―・さずにおく/浄瑠璃・万年草(中)」
〔現在も関西地方で用いる〕
か-やす・し【か易し】🔗⭐🔉
か-やす・し 【か易し】 (形ク)
〔「か」は接頭語〕
(1)たやすい。容易だ。簡単だ。「手放れもをちも―・き/万葉 4011」
(2)かるがるしい。気軽だ。「―・き身ならば,忍びていと逢はまほしくこそ/源氏(若菜上)」
か-やつ【彼奴】🔗⭐🔉
か-やつ 【彼奴】 (代)
三人称。話し手・聞き手以外の者をいやしめののしっていう語。きゃつ。あいつ。「ほととぎす,おれ,―よ/枕草子 226」
カヤック kayak
kayak 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
カヤック [2][1]  kayak
kayak (1)イヌイットやアメリカ-インディアンなどが使う,海豹(アザラシ)の皮を張って作った小舟。
(2)競技用カヌーの一。両端に水掻(ミズカ)き(ブレード)のある櫂(カイ)(パドル)を使う。
カヤック(1)
(1)イヌイットやアメリカ-インディアンなどが使う,海豹(アザラシ)の皮を張って作った小舟。
(2)競技用カヌーの一。両端に水掻(ミズカ)き(ブレード)のある櫂(カイ)(パドル)を使う。
カヤック(1)
 [図]
[図]
 kayak
kayak (1)イヌイットやアメリカ-インディアンなどが使う,海豹(アザラシ)の皮を張って作った小舟。
(2)競技用カヌーの一。両端に水掻(ミズカ)き(ブレード)のある櫂(カイ)(パドル)を使う。
カヤック(1)
(1)イヌイットやアメリカ-インディアンなどが使う,海豹(アザラシ)の皮を張って作った小舟。
(2)競技用カヌーの一。両端に水掻(ミズカ)き(ブレード)のある櫂(カイ)(パドル)を使う。
カヤック(1)
 [図]
[図]
かや-つり-ぐさ【蚊帳吊草・莎草】🔗⭐🔉
かや-つり-ぐさ [4] 【蚊帳吊草・莎草】
(1)カヤツリグサ科カヤツリグサ属の草本の総称。カヤツリグサ・コゴメガヤツリ・アゼガヤツリ・チャガヤツリ・ウシクグなど。三角柱状の茎を両端から裂いていくと真ん中で四本に分かれ四角形ができるのを蚊帳や枡(マス)に見立てての名。マスクサ。[季]夏。《かたくなに一人遊ぶ子―/富安風生》
(2)カヤツリグサ科の一年草。日当たりのよい畑・草地に自生。高さ30〜40センチメートル。葉は根生し,線形。夏,茎頂に細長い苞葉と黄褐色の穂を数個つける。
蚊帳吊草(2)
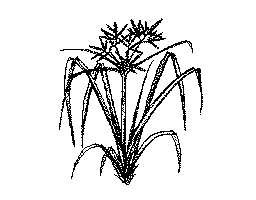 [図]
[図]
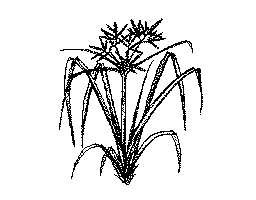 [図]
[図]
かやつりぐさ-か【蚊帳吊草科】🔗⭐🔉
かやつりぐさ-か ―クワ [0] 【蚊帳吊草科】
単子葉植物の一科。世界に七〇属約四〇〇〇種。葉は線形でイネ科植物と似ているが,茎は三角柱状で中実。カヤツリグサ・スゲ・アブラガヤ・クログワイの類を含む。
かや-と【茅戸・萱所】🔗⭐🔉
かや-と [0] 【茅戸・萱所】
山中の茅におおわれている尾根や斜面。
〔登山者や山村でいう語〕
かや-ねずみ【萱鼠】🔗⭐🔉
かや-ねずみ [3] 【萱鼠】
ネズミ科の哺乳類。日本のネズミ類中で最小。体長は5〜7センチメートル,尾もほぼ同長。背部は黄褐色で腹部は白色。尾をまきつけて巧みに草木に登る。湿地を好み,カヤなどの葉や茎を編み,地上数十センチメートルの所に球状の巣をつくる。穀類・種子などを食べる。
萱鼠
 [図]
[図]
 [図]
[図]
かや-の【茅野・萱野】🔗⭐🔉
かや-の [0] 【茅野・萱野】
茅が生えている野原。かやはら。
かやの【萱野】🔗⭐🔉
かやの 【萱野】
姓氏の一。
かやの-さんぺい【萱野三平】🔗⭐🔉
かやの-さんぺい 【萱野三平】
(1675-1702) 赤穂藩士。名は重実。義士に加わろうとしたが父の反対にあい,自刃(ジジン)した。浄瑠璃などで早野勘平として脚色。
かや-の-あぶら【榧の油】🔗⭐🔉
かや-の-あぶら [1] 【榧の油】
榧の実を圧搾して得た油。上質の植物性油で,食用・灯用・理髪用とする。
かや-の-いん【高陽院・賀陽院】🔗⭐🔉
かや-の-いん ― ン 【高陽院・賀陽院】
(1)桓武天皇の皇子賀陽(カヤ)親王の邸宅。平安京左京中御門の南,大炊(オオイ)御門の北,西洞院(ニシノトウイン)の東,堀川の西にあった。後冷泉・後三条天皇の内裏ともなる。のち藤原摂関家の邸宅。
(2)(1095-1155) 鳥羽上皇の皇后。名は勲子。のち泰子。1139年院号宣下。
ン 【高陽院・賀陽院】
(1)桓武天皇の皇子賀陽(カヤ)親王の邸宅。平安京左京中御門の南,大炊(オオイ)御門の北,西洞院(ニシノトウイン)の東,堀川の西にあった。後冷泉・後三条天皇の内裏ともなる。のち藤原摂関家の邸宅。
(2)(1095-1155) 鳥羽上皇の皇后。名は勲子。のち泰子。1139年院号宣下。
 ン 【高陽院・賀陽院】
(1)桓武天皇の皇子賀陽(カヤ)親王の邸宅。平安京左京中御門の南,大炊(オオイ)御門の北,西洞院(ニシノトウイン)の東,堀川の西にあった。後冷泉・後三条天皇の内裏ともなる。のち藤原摂関家の邸宅。
(2)(1095-1155) 鳥羽上皇の皇后。名は勲子。のち泰子。1139年院号宣下。
ン 【高陽院・賀陽院】
(1)桓武天皇の皇子賀陽(カヤ)親王の邸宅。平安京左京中御門の南,大炊(オオイ)御門の北,西洞院(ニシノトウイン)の東,堀川の西にあった。後冷泉・後三条天皇の内裏ともなる。のち藤原摂関家の邸宅。
(2)(1095-1155) 鳥羽上皇の皇后。名は勲子。のち泰子。1139年院号宣下。
かや-の-みや【賀陽宮】🔗⭐🔉
かや-の-みや 【賀陽宮】
旧宮家。伏見宮邦家親王の第四王子朝彦(アサヒコ)親王が1863年中川宮と称し,翌年改称したもの。朝彦親王はその後幽居の身となって宮号は止められ,再興後は久邇宮(クニノミヤ)と称したため,賀陽宮の称号は1892年(明治25)その子邦憲王が復興した。
かや-ば【茅場・萱場】🔗⭐🔉
かや-ば [0] 【茅場・萱場】
(1)屋根を葺(フ)く茅の茂ったところ。
(2)秣(マグサ)を刈るところ。まぐさば。
かやば-ちょう【茅場町】🔗⭐🔉
かやば-ちょう ―チヤウ 【茅場町】
東京都中央区の町名。隣接する兜町(カブトチヨウ)とともに証券会社が集中する。
かや-ぶき【茅葺き】🔗⭐🔉
かや-ぶき [0] 【茅葺き】
茅で屋根をふくこと。また,その屋根。「―屋根」
かや-ぶね【茅船・萱船】🔗⭐🔉
かや-ぶね [3] 【茅船・萱船】
茅を積んだ船。昔,船軍(フナイクサ)の際,茅に火をつけて敵船の間に放った。
かや-みそ【榧味噌】🔗⭐🔉
かや-みそ [0] 【榧味噌】
榧の実を炒(イ)って渋皮をとり,すりつぶして胡麻(ゴマ)・砂糖などと味噌に混ぜ合わせたもの。
かや-もん【茅門・萱門】🔗⭐🔉
かや-もん [0][2] 【茅門・萱門】
庭園・数寄屋の露地の入り口などに設ける茅葺(ブ)きの簡素で風雅な門。
か-やり【蚊遣り】🔗⭐🔉
か-やり [0] 【蚊遣り】
煙でいぶして蚊を追いやること。また,そのために燃やすもの。かやりび。蚊いぶし。蚊ふすべ。[季]夏。
かやり-ぎ【蚊遣り木】🔗⭐🔉
かやり-ぎ [3] 【蚊遣り木】
蚊遣りに焚く木。
かやり-こう【蚊遣り香】🔗⭐🔉
かやり-こう ―カウ [0] 【蚊遣り香】
蚊を追い払うため,除虫菊の粉末などを原料としてつくった線香。蚊取り線香。[季]夏。
かやり-せんこう【蚊遣り線香】🔗⭐🔉
かやり-せんこう ―カウ [4] 【蚊遣り線香】
⇒蚊遣(カヤ)り香(コウ)
かやり-び【蚊遣り火】🔗⭐🔉
かやり-び [3] 【蚊遣り火】
蚊を追い払うために,くすぶらせる煙。蚊火。かやり。[季]夏。
かやり-び-の【蚊遣り火の】🔗⭐🔉
かやり-び-の 【蚊遣り火の】 (枕詞)
(1)「蚊遣り火の燻(ク)ゆる」ことから,同音の「悔ゆる」にかかる。「―悔ゆる心も尽きぬべく/拾遺(雑下)」
(2)蚊遣り火が見えない所で燃えているところから,「した」「そこ」などにかかる。「―いつまでわが身下燃えをせむ/古今(恋一)」
かや【茅】(和英)🔗⭐🔉
かや【茅】
《植》cogon 茅葺きの thatched.
かや【蚊帳】(和英)🔗⭐🔉
かや【蚊帳】
a mosquito net.〜を吊る(はずす) put up (take down) a mosquito net.
かやく【火薬】(和英)🔗⭐🔉
かやく【火薬】
gunpowder.→英和
火薬庫 a (powder) magazine.
大辞林に「かや」で始まるの検索結果 1-57。
 p
p