複数辞典一括検索+![]()
![]()
じんだい‐かぐら【神代神‐楽】🔗⭐🔉
じんだい‐かぐら【神代神‐楽】
 岩戸神楽(いわとかぐら)
岩戸神楽(いわとかぐら)
 岩戸神楽(いわとかぐら)
岩戸神楽(いわとかぐら)
しんだい‐ぐすり【身代薬】🔗⭐🔉
しんだい‐ぐすり【身代薬】
《身代を保つための薬の意》一家の財産を保つために役立つもの。特に、しっかりした女房をいう。「―の女房を早う持って落ち着きや」〈浄・今宮の心中〉
しんたい‐けい【身体刑】🔗⭐🔉
しんたい‐けい【身体刑】
犯罪者の身体に苦痛や侵害を与える刑。入れ墨刑・笞刑(ちけい)など。懲役・禁錮などは身体刑ではないが、俗にこれらも含めていうことがある。体刑。
しんたい‐けん【身体権】🔗⭐🔉
しんたい‐けん【身体権】
人格権の一。不法に身体に侵害を加えられることのない権利。
しんたい‐げんご【身体言語】🔗⭐🔉
しんたい‐げんご【身体言語】
 ボディーランゲージ
ボディーランゲージ
 ボディーランゲージ
ボディーランゲージ
しんたい‐けんさ【身体検査】🔗⭐🔉
しんたい‐けんさ【身体検査】
 身体の発育状態や病気の有無を検査すること。
身体の発育状態や病気の有無を検査すること。 服装や所持品などを検査すること。
服装や所持品などを検査すること。
 身体の発育状態や病気の有無を検査すること。
身体の発育状態や病気の有無を検査すること。 服装や所持品などを検査すること。
服装や所持品などを検査すること。
じん‐だいこ【陣太鼓】ヂン‐🔗⭐🔉
じん‐だいこ【陣太鼓】ヂン‐

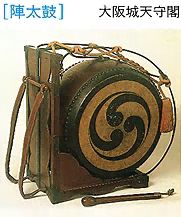 戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。
戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。

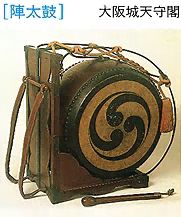 戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。
戦場で、軍勢の進退の合図に打ち鳴らした太鼓。戦鼓。
しん‐だいさんき【新第三紀】🔗⭐🔉
しん‐だいさんき【新第三紀】
地質時代の区分で、新生代第三紀の後半。二四〇〇万年前から一七〇万年前まで。さらに中新世と鮮新世とに二分される。哺乳類が著しく進化し、繁栄した。
しん‐だいさんけい【新第三系】🔗⭐🔉
しん‐だいさんけい【新第三系】
新第三紀に形成された地層や岩石。
しんたい‐し【新体詩】🔗⭐🔉
しんたい‐し【新体詩】
明治後期に口語自由詩が現れる以前の文語定型詩。多く七五調で、明治一五年(一八八二)外山正一らの「新体詩抄」に始まり、北村透谷・島崎藤村・土井晩翠(つちいばんすい)などの作によって発展、やがて近代詩の確立とともに単に「詩」と呼ばれるようになった。
じんだい‐じ【深大寺】🔗⭐🔉
じんだい‐じ【深大寺】
東京都調布市にある天台宗の寺。山号は浮岳山。開創は天平五年(七三三)、開山は満功(まんくう)という。初め法相(ほつそう)宗。寺宝の金銅釈迦如来像は白鳳時代のもの。
大辞泉 ページ 7900。