複数辞典一括検索+![]()
![]()
○筆の尻取るふでのしりとる🔗⭐🔉
○筆の尻取るふでのしりとる
詩歌・文章の添削をする。源氏物語末摘花「―博士ぞなかるべき」
⇒ふで‐の‐しり【筆の尻】
ふで‐の‐すさび【筆の荒び】
筆にまかせて書くこと。なぐさみに書くこと。また、その書いたもの。
ふで‐の‐たより【筆の便り】
手紙でたよりをすること。
ふで‐の‐ながれ【筆の流れ】
筆のはしらせかた。ふでづかい。筆勢。狭衣物語4「墨附、―もあやしくなべてならず」
ふで‐の‐はこび【筆の運び】
筆のつかいかた。運筆。
ふで‐の‐はやし【筆の林】
①書いた詩文の多いのを、林の木の多いのに喩えた語。文林。歌林。詩林。
②文壇。
ふて‐のみ【ふて飲み】
ふてくされて酒をのむこと。
ふで‐ばこ【筆箱】
筆を入れる箱。また、ペン・鉛筆・消しゴムなど筆記用具の携帯用容器。筆入れ。
ふて‐ばり【ふて鉤】
(→)置鉤おきばりに同じ。
ふで‐ぶしょう【筆無精】‥シヤウ
筆をとって手紙や文章を書くのを面倒がること。「―な人」↔筆忠実ふでまめ
ふてぶてし・い
〔形〕[文]ふてぶて・し(シク)
(「不敵不敵しい」「不貞不貞しい」は当て字)大胆不敵である。憎らしいほどずぶとい。黄表紙、天道浮世出星操「―・い。あんな女あまに馬鹿にされるのとは違はアね」。「―・い態度」
ふで‐ぶと【筆太】
文字を太く書くこと。また、その文字。
ふで‐ペン【筆ペン】
軸にインクを内蔵する、毛筆を模したペン。
ふで‐ぼうふう【筆防風】‥バウ‥
〔植〕
①イブキボウフウの別称。
②ボウフウの、根が筆先に似たもの。
ふで‐まき【筆巻】
筆を巻き納めておく小さいすだれ。
ふで‐まめ【筆忠実】
面倒がらずに筆をとって手紙を書き、または文を綴ること。好色五人女3「小遣帳を―にあらため」。「―な人」↔筆無精
ふ‐てまわし【不手回し】‥マハシ
①てまわしの悪いこと。
②家計のきりもりがうまくいかないこと。浮世草子、日本新永代蔵「かならず怠りはあらねど、物事―になる年あり」
ふ‐てまわり【不手回り】‥マハリ
金の都合がうまくつかないこと。手もとが不如意なこと。梅暦「回らぬ暮し常なれど、この節わけて―」
ふで‐むすめ【筆娘】
筆親から鉄漿おはぐろをつけてもらった娘。鉄漿子かなこ。歯黒子はぐろご。→おはぐろおや
ふて‐もの【ふて者】
捨てばちで、やけな振舞をする者。義経記8「あれ程の―に寄り合ふべからずとて」
ふで‐や【筆屋】
筆をつくり、また商う家・人。
ふで‐ゆい【筆結い】‥ユヒ
筆をつくること。また、その業の人。宇津保物語嵯峨院「―の才なむ侍る」
ふてらっこ・い
〔形〕
ふてぶてしい。鉄面皮である。人情本、花街寿々女さとすずめ「跡はともなれ山ざくらと、―・く出かけては来たやうなものの」
プテラノドン【Pteranodon ラテン】
翼竜の一つ。白亜紀の北アメリカに生息。翼開長9メートルに達する。種によって頭骨後部の形状が異なる。歯を持たず尾が著しく短い。
プテラノドン
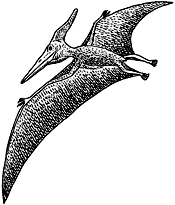 ブデリウム【bdellium】
バルサム樹(ホウセンカ)から採る芳香樹脂。
ふ・てる
〔自下一〕[文]ふ・つ(下二)
①不敵な心をおこす。不敵な心をおこして捨てばちな行動に出る。義経記7「十余人の人々、とてもかくてもとうち―・てて、関屋をさしてぞおはしける」
②強情を張る。狂言、縄綯なわない「たら(誑)いてつかはしましたによつて、きやつが―・てたものでござらう」
③(当て字で「不貞る」とも書く)思うようにならないので自暴自棄になる。ふてくされる。日葡辞書「フテテイル」。「―・てて部屋にとじこもる」
ふ・てる【棄てる】
〔他下一〕[文]ふ・つ(下二)
すてる。大和物語「湯、―・てつ。又水を入る」
ふで‐わけ【筆別け】
①1件ごとに区別して書きしるすこと。
②分筆ぶんぴつ。
ブデリウム【bdellium】
バルサム樹(ホウセンカ)から採る芳香樹脂。
ふ・てる
〔自下一〕[文]ふ・つ(下二)
①不敵な心をおこす。不敵な心をおこして捨てばちな行動に出る。義経記7「十余人の人々、とてもかくてもとうち―・てて、関屋をさしてぞおはしける」
②強情を張る。狂言、縄綯なわない「たら(誑)いてつかはしましたによつて、きやつが―・てたものでござらう」
③(当て字で「不貞る」とも書く)思うようにならないので自暴自棄になる。ふてくされる。日葡辞書「フテテイル」。「―・てて部屋にとじこもる」
ふ・てる【棄てる】
〔他下一〕[文]ふ・つ(下二)
すてる。大和物語「湯、―・てつ。又水を入る」
ふで‐わけ【筆別け】
①1件ごとに区別して書きしるすこと。
②分筆ぶんぴつ。
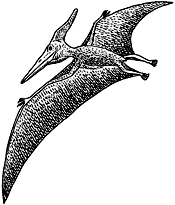 ブデリウム【bdellium】
バルサム樹(ホウセンカ)から採る芳香樹脂。
ふ・てる
〔自下一〕[文]ふ・つ(下二)
①不敵な心をおこす。不敵な心をおこして捨てばちな行動に出る。義経記7「十余人の人々、とてもかくてもとうち―・てて、関屋をさしてぞおはしける」
②強情を張る。狂言、縄綯なわない「たら(誑)いてつかはしましたによつて、きやつが―・てたものでござらう」
③(当て字で「不貞る」とも書く)思うようにならないので自暴自棄になる。ふてくされる。日葡辞書「フテテイル」。「―・てて部屋にとじこもる」
ふ・てる【棄てる】
〔他下一〕[文]ふ・つ(下二)
すてる。大和物語「湯、―・てつ。又水を入る」
ふで‐わけ【筆別け】
①1件ごとに区別して書きしるすこと。
②分筆ぶんぴつ。
ブデリウム【bdellium】
バルサム樹(ホウセンカ)から採る芳香樹脂。
ふ・てる
〔自下一〕[文]ふ・つ(下二)
①不敵な心をおこす。不敵な心をおこして捨てばちな行動に出る。義経記7「十余人の人々、とてもかくてもとうち―・てて、関屋をさしてぞおはしける」
②強情を張る。狂言、縄綯なわない「たら(誑)いてつかはしましたによつて、きやつが―・てたものでござらう」
③(当て字で「不貞る」とも書く)思うようにならないので自暴自棄になる。ふてくされる。日葡辞書「フテテイル」。「―・てて部屋にとじこもる」
ふ・てる【棄てる】
〔他下一〕[文]ふ・つ(下二)
すてる。大和物語「湯、―・てつ。又水を入る」
ふで‐わけ【筆別け】
①1件ごとに区別して書きしるすこと。
②分筆ぶんぴつ。
広辞苑 ページ 17297 での【○筆の尻取る】単語。