複数辞典一括検索+![]()
![]()
○事が延びれば尾鰭が付くことがのびればおひれがつく🔗⭐🔉
○事が延びれば尾鰭が付くことがのびればおひれがつく
事は早く運ばないと余計なことがつきまとってやりにくくなる。
⇒こと【事】
こと‐がま・し【事がまし】
〔形シク〕
ぎょうぎょうしい。おおげさだ。ことごとしい。曾我物語9「その体―・しく出で立ちたり」
こと‐がま・し【言囂し】
〔形シク〕
口やかましい。源氏物語夕霧「さがなく―・しきもしばしはなまむつかしう」
こと‐がみ【琴頭】
琴のかしらの方。武烈紀「―に来ゐる影媛」↔琴尾ことじり
こと‐がら【言柄】
ことばのおもむき。歌の姿。徒然草「今の世の人の詠みぬべき―とは見えず」
こと‐がら【事柄】
①事の内容。事の模様。古今著聞集15「若しやとて―を見せけるに」。「信用にかかわる―には触れない」
②様子。海道記「木綿幣ゆうしで風に乱れたる―にて」
③(コツガラ(骨柄)の転)体格。人品。平治物語「容儀―人に勝れてぞ見えられける」
こと‐き【異木】
異なる木。他の木。枕草子37「桐の木の花…―どもとひとしういふべきにあらず」
こ‐どき【蚕時】
蚕を飼う季節。一説に、コトホキ(言寿)の約で、祝宴の意という。万葉集14「新室にいむろの―に到れば」
こと‐ぎさき【異后】
他のきさき。栄華物語若水「みかどの御母后・妻后を放ちては―のおはしますやうなかりければ」
こと‐きみ【異君】
①別の主君。謡曲、花筐「この君ならで日の本に又―のましますべきか」
②他の人、他の男の尊敬語。
⇒こときみ‐どり【異君取り】
こときみ‐どり【異君取り】
他の人を主君とすること。また、他の男を婿とすること。落窪物語1「何の由にか、―はし奉らむと泣けば」
⇒こと‐きみ【異君】
こと‐ぎれ【事切れ】
①事が終わること。事の止むこと。
②息がたえること。死ぬこと。
⇒ことぎれ‐の‐ごせいばい【事切の御成敗】
⇒ことぎれ‐の‐もんじょ【事切文書】
ことぎれ‐の‐ごせいばい【事切の御成敗】
鎌倉幕府の訴訟で、勝訴者に下知状が下付され、全く結審した裁判。
⇒こと‐ぎれ【事切れ】
ことぎれ‐の‐もんじょ【事切文書】
鎌倉時代、落着した裁判の一件書類。
⇒こと‐ぎれ【事切れ】
こと‐き・れる【事切れる】
〔自下一〕[文]ことき・る(下二)
①終わる。きまる。落着する。十訓抄「東国の庄の事、今まで―・れねば」
②死ぬ。命が絶える。保元物語「午の刻ばかりに、御―・れにけり」
こ‐とく【古徳】
昔の高徳の僧。沙石集2「―の釈によりて」
こ‐どく【孤独】
①みなし子と老いて子なき者。太平記33「窮民・―の飢ゑをたすくるにもあらず」→鰥寡かんか孤独。
②仲間のないこと。ひとりぼっち。「―感」
⇒こどく‐し【孤独死】
ご‐とく【五徳】
①儒教で、温・良・恭・倹・譲の五つの徳目。兵家で、知・信・仁・勇・厳。
②秦漢の儒教で、木・火・土・金・水の五行のこと。帝王の徳を示すものとされ、その循環によって王朝の交替等を説明した。→五行。
③炭火などの上に置き、鉄瓶などをかける3脚または4脚の輪形の器具。鉄または陶器製。上下逆に置くこともある。
五徳
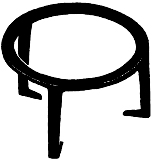 ④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。
ご‐とく【悟得】
悟りをひらいて真理を会得すること。
ご‐どく【誤読】
まちがえて読むこと。
こと‐くさ【異草】
異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」
こと‐ぐさ【言種】
①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」
②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」
③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」
こどく‐し【孤独死】
看取る人もなく一人きりで死ぬこと。
⇒こ‐どく【孤独】
ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】
藤原実定の通称。
ごとく‐ち【後得智】
〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。
こと‐くど・い【事諄い】
〔形〕
「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」
こと‐くに【異国】
①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」
②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」
こ‐とくにん【子徳人】
子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」
ことく‐らく【胡徳楽】
雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。
こと‐くらげ【琴水母】
クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。
ことくらげ
④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。
ご‐とく【悟得】
悟りをひらいて真理を会得すること。
ご‐どく【誤読】
まちがえて読むこと。
こと‐くさ【異草】
異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」
こと‐ぐさ【言種】
①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」
②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」
③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」
こどく‐し【孤独死】
看取る人もなく一人きりで死ぬこと。
⇒こ‐どく【孤独】
ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】
藤原実定の通称。
ごとく‐ち【後得智】
〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。
こと‐くど・い【事諄い】
〔形〕
「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」
こと‐くに【異国】
①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」
②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」
こ‐とくにん【子徳人】
子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」
ことく‐らく【胡徳楽】
雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。
こと‐くらげ【琴水母】
クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。
ことくらげ
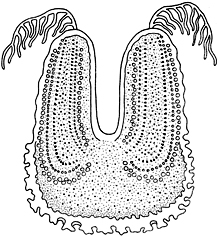 こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」
②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」
こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」
こ‐どけい【子時計】
親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。
こと‐こい【言乞い】‥コヒ
占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」
こと‐こい【異恋】‥コヒ
ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」
こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」
②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」
こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」
こ‐どけい【子時計】
親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。
こと‐こい【言乞い】‥コヒ
占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」
こと‐こい【異恋】‥コヒ
ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」
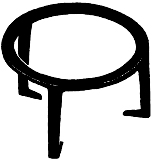 ④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。
ご‐とく【悟得】
悟りをひらいて真理を会得すること。
ご‐どく【誤読】
まちがえて読むこと。
こと‐くさ【異草】
異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」
こと‐ぐさ【言種】
①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」
②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」
③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」
こどく‐し【孤独死】
看取る人もなく一人きりで死ぬこと。
⇒こ‐どく【孤独】
ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】
藤原実定の通称。
ごとく‐ち【後得智】
〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。
こと‐くど・い【事諄い】
〔形〕
「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」
こと‐くに【異国】
①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」
②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」
こ‐とくにん【子徳人】
子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」
ことく‐らく【胡徳楽】
雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。
こと‐くらげ【琴水母】
クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。
ことくらげ
④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。
ご‐とく【悟得】
悟りをひらいて真理を会得すること。
ご‐どく【誤読】
まちがえて読むこと。
こと‐くさ【異草】
異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」
こと‐ぐさ【言種】
①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」
②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」
③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」
こどく‐し【孤独死】
看取る人もなく一人きりで死ぬこと。
⇒こ‐どく【孤独】
ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】
藤原実定の通称。
ごとく‐ち【後得智】
〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。
こと‐くど・い【事諄い】
〔形〕
「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」
こと‐くに【異国】
①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」
②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」
こ‐とくにん【子徳人】
子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」
ことく‐らく【胡徳楽】
雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。
こと‐くらげ【琴水母】
クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。
ことくらげ
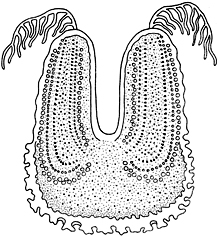 こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」
②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」
こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」
こ‐どけい【子時計】
親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。
こと‐こい【言乞い】‥コヒ
占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」
こと‐こい【異恋】‥コヒ
ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」
こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」
②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」
こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ
〔自下二〕
大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」
こ‐どけい【子時計】
親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。
こと‐こい【言乞い】‥コヒ
占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」
こと‐こい【異恋】‥コヒ
ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」
広辞苑 ページ 7292 での【○事が延びれば尾鰭が付く】単語。