複数辞典一括検索+![]()
![]()
すえ‐かた【末方】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐かた【末方】スヱ‥
宮廷の神楽の演奏で、あとに唱え歌う側。神殿に向かって右側に座る。↔本方もとかた
すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐かなもの【据金物・居文金物】スヱ‥
①かざりにすえる金具。
②甲冑かっちゅうの金具廻まわりや吹返しにすえる金物。→大鎧おおよろい(図)
すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐か・ねる【据え兼ねる】スヱ‥
〔自下一〕
(多く、「腹に―・ねる」の形で使う)
⇒はら(腹)(成句)
すえ‐がま【陶窯】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐がま【陶窯】スヱ‥
陶器を焼くかまど。
すえかわ【末川】スヱカハ🔗⭐🔉
すえかわ【末川】スヱカハ
姓氏の一つ。
⇒すえかわ‐ひろし【末川博】
すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥🔗⭐🔉
すえかわ‐ひろし【末川博】スヱカハ‥
民法学者。山口県生れ。1933年滝川事件に際し、京大教授を辞職。第二次大戦後、立命館大学総長。幅広い著作と実践活動で民主主義・平和運動に貢献。著「権利侵害論」「権利濫用の研究」、編「岩波六法全書」など。(1892〜1977)
末川博
提供:毎日新聞社
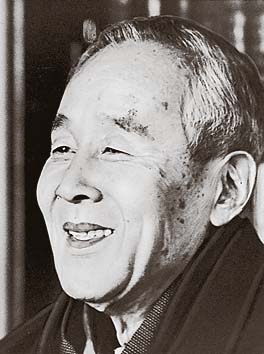 ⇒すえかわ【末川】
⇒すえかわ【末川】
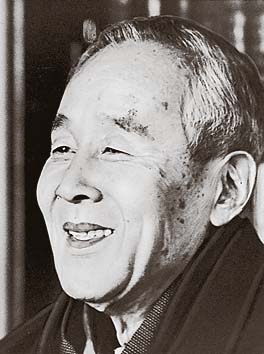 ⇒すえかわ【末川】
⇒すえかわ【末川】
すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐き【須恵器・陶器】スヱ‥
古墳時代中・後期から奈良・平安時代に作られた、朝鮮半島系技術による素焼の土器。良質粘土で、成形にはろくろを使用、あな窯を使い高温の還元炎で焼くため暗青色のものが一般的。食器や貯蔵用の壺・甕かめが多く、祭器もある。祝部いわいべ土器。斎瓮いんべ・いわいべ。
須恵器


ず‐えき【徒役】ヅ‥🔗⭐🔉
ず‐えき【徒役】ヅ‥
律令制で、徒ずの刑に服役すること。
すえ‐きち【末吉】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐きち【末吉】スヱ‥
おみくじで、後に吉となる運勢。
すえ‐くち【末口】スヱ‥🔗⭐🔉
すえ‐くち【末口】スヱ‥
丸太材の細い方の切り口。↔元口。
⇒すえくち‐もの【末口物】
すえくち‐もの【末口物】スヱ‥🔗⭐🔉
すえくち‐もの【末口物】スヱ‥
材種の一つ。長さ4間以上、末口の径1.5尺以上の丸太材などにいう。
⇒すえ‐くち【末口】
広辞苑 ページ 10464。