複数辞典一括検索+![]()
![]()
つくみ【津久見】🔗⭐🔉
つくみ【津久見】
大分県南東部の市。豊後水道の津久見湾に臨む。石灰岩が豊富でセメントなどの工業が盛ん。人口2万1千。
つぐみ【鶫・鶇】🔗⭐🔉
つぐみ【鶫・鶇】
スズメ目ツグミ科の鳥。背面は大体黒褐色で栗色を混じ、顔は黄白色で眼の部分に黒斑がある。シベリア中部・東部で繁殖し、秋、大群をなして日本に渡来。かつて、かすみ網で大量に捕獲、食用にされた。なお、ツグミ科の鳥は、主として林地の地表で昆虫を採食する小鳥で、全長10〜35センチメートル。世界に約300種。日本には約20種が分布。特に、そのうち全長20センチメートル以上のものをツグミと呼ぶ。アカハラ・シロハラ・アカコッコ・マミジロ・マミチャジナイ・クロツグミ・トラツグミなど。チョウマ。ツムギ。〈[季]秋〉
つぐみ
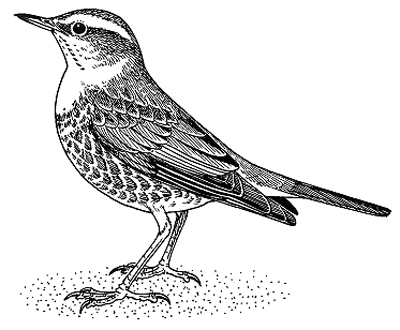 ツグミ
提供:OPO
ツグミ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
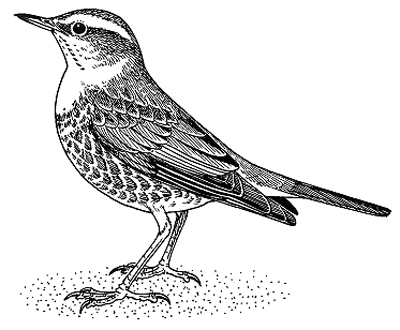 ツグミ
提供:OPO
ツグミ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
つく・む🔗⭐🔉
つく・む
〔他下二〕
(一説に、四段)強く握る。万葉集20「堀江漕ぐ伊豆手の船の揖―・め」
つぐ・む【噤む・鉗む】🔗⭐🔉
つぐ・む【噤む・鉗む】
〔他五〕
(古くはツクムと清音)口を閉じてものを言わない。だまる。もだす。太平記4「群臣口を―・み、万人目を以てす」
つく‐め【附目】🔗⭐🔉
つく‐め【附目】
舟の櫓の腕についている、櫓綱をかけるための突起。万葉集8「妹がりとわが行く道の川にあれば―結ぶと夜そ更降くたちける」
つくも【九十九】🔗⭐🔉
つくも【九十九】
①くじゅうく。→九十九髪つくもがみ。
②〔植〕(「江浦草」と書く)フトイの異称。
⇒つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】
つくも‐かいづか【津雲貝塚】‥カヒ‥🔗⭐🔉
つくも‐かいづか【津雲貝塚】‥カヒ‥
岡山県笠岡市にある縄文時代後期の貝塚。大正年間の発掘で多数の人骨が出土したことで著名。
広辞苑 ページ 13122。